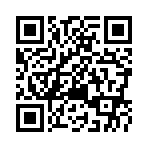2008年08月22日
折れ屋根の家

千葉県の四海道市の住宅地に建てられた折れ屋根のログです。
道路拡幅に伴う代替換地で新興住宅団地の一部に割り当てられてしまいました、元の土地が狭かったので敷地が60坪程度しかなく(周辺は大抵1区画100坪)、様々な規制からプランニングして折れ屋根のコンパクトな建物になりました。
建物で敷地幅は一杯です。
駐車スペース確保は必須なので(関東だと郊外でも駐車場は1万/月位平気でします)表に確保、狭くても戸建てですから庭は欲しいものです。
施主さんはこれまでずっと団地暮らしでしたから念願の戸建てでペットも飼いたいという希望があり庭も確保です。

幸い南に面した敷地なので建物を敷地北側半分程にしてフリープランでびっちり設計しました。
間取りは2LDK+ロフト+Winクローゼットです。
折れ屋根下の手前半分は玄関スペース、奥が寝室から入るクローゼットです。
これまでの生活で蓄えられた荷物が団地の一室を占領、ある程度処分しても捨てられない荷物や箪笥がありますからそういうモノの置き場所をプランニングの時点で予め用意しておく訳です。
そうすれば引越ししてもコレはどこに置く、コレは捨てて持っていかないと予め決められる訳ですね。

かなりコンパクトな間取りなのでダイニングテーブルは作りつけ、キッチンスペースのムダをなくしてリビングの広さを確保しています。普段は夫婦2人住まいでたまにお子さんが帰ってくるという家です。

一階には夫婦の寝室、二階の部屋は息子さんの部屋、そしてロフトに机を作り付けにしてご主人の書斎スペースです。ロフトは奥様も趣味でお使いになります。
息子さんが友人を連れてくるとザコ寝スペースにも・・・

この多機能ぶりで第二のリビングになるのがロフトの良さですね、もちろんバルコニーに出られます。

スペースの関係でバスルームは1616タイプ(1坪)のユニットバスですが洗面脱衣所兼洗濯機置き場が狭くなってしまいました。そこでユニットバスと脱衣場の間の壁に収納を組み込んだ製品を選択。
これだとユーティリティ周りの小物をすっきりと収納出来ます。
通常はここは壁を作ってハリボテになりますが、この壁は半透明なので光も透過して窓の無いバスルーム(予算のメリハリ上高価なバス窓をカットした)ですが、この収納ウォールから脱衣場の窓の明かりが届きます。
まぁバスに窓があったとしても風呂に入るのは夜なので日中はほぼ関係無いんですよね。
乾燥も換気扇ですから・・・

建物北側は日照権絡みの北側斜線規制があります。これを回避する為に屋根の一部を斜めに削って裏側の土地の方の日当たりを確保してあげなくてはなりません。
もしくはこの規制ラインから外れるところまで建物を南に移動させればよい訳ですが、日当たりの悪い北側の土地を空けても使い道が無い訳ですね。
ですから屋根を削ってでも建物を北側に配置して南の日当たりの良い庭と駐車スペースを確保する訳です。
新築当時は周辺区画はまだ空いていましたが、現在はかなり家が建てられています。
大分だとさしずめ高江NTみたいな所ですね。
2008年08月22日
巻きましょう
メンテもいよいよ終盤です。
最大の課題であった東面の二階バルコニーを支えている梁の腐りをどうするか。
雨ざらしでボロボロになっている梁でしたが、シロタの部分はやられていても赤身の部分はしっかりしています。

梁にはポストが立てられて屋根荷重を負担しているようにも見えるのですが、そもそも軒の突き出しが母屋でも1200程度しかなく方杖も入っているので「このポスト自体の過重負担はほとんどない」と判断、ならば心材だけでもデッキ部分は十分に保持できるので梁の補強とか交換はやらずに「銅板を巻いてしまい雨が当らなくする」という方法を取りました。
もちろんコストも考慮した結果です。

梁一本2/3程度まで銅板を巻きつけてもらい、際や柱周りはコーキングして防水しました。
柱の下は以前のメンテで水抜穴があけてあるので柱のクラックから水が入ったとしても下に抜けかつ乾燥できるようにしています。

ガルバリウム鋼板などは安価ではありますがログの凹凸に合わせて加工しないといけないし、経年劣化での変化を考えれば多少材料が高く付いても銅を選んでおくのが良いと思います。
ステンレスは硬くて加工が大変、アルミは悪くないですが見た目がシルバーだしいずれ腐食して粉吹きになっちゃいますし・・・やっぱ銅なんですねぇ。
南側ログウォールのシルログ、裏側の上部がボッコリと腐食して欠損していました。
ここは勝手口の脇で腐食の発見が早かった為に施主さんがブリキ板を打ち付けていました。

お陰で腐りは止まっていたのですがバックアップ材とチンキングで埋めてしまうにも欠損が大きすぎて・・・で余った銅板でカバーしただけで良い事に。
サドルノッチの削りこみ部分があるので上手く板金を叩いて形状を合わせて・・・・
上下を銅釘で留めてログとの取り合いはチンキングしました。

木口方向からは水が入ることもあるかもしれませんが、これだけ大きく開いていれば乾燥もするし上からは雨水は入らないので水が入るのは台風の時位のものです。
このログの反対側はバックアップとチンクで大手術したとこです。
母屋と棟木も再塗装しました。
母屋先端部も腐りが廻っていましたがこちらも整形せずに腐った部分のみを削り落として防腐処理と再塗装です。

形成不要なのは表からは見えない部分なのと、予算の割り振りの都合上です。
確かに水を落す形状にまで削ったので見た目は良くないですが、逆にここに予算をかけて丸いログに再生したところでそのメリットは?という事でもあります。
限られた予算のなかで様々なメンテを行っています。
最大の課題であった東面の二階バルコニーを支えている梁の腐りをどうするか。
雨ざらしでボロボロになっている梁でしたが、シロタの部分はやられていても赤身の部分はしっかりしています。

梁にはポストが立てられて屋根荷重を負担しているようにも見えるのですが、そもそも軒の突き出しが母屋でも1200程度しかなく方杖も入っているので「このポスト自体の過重負担はほとんどない」と判断、ならば心材だけでもデッキ部分は十分に保持できるので梁の補強とか交換はやらずに「銅板を巻いてしまい雨が当らなくする」という方法を取りました。
もちろんコストも考慮した結果です。

梁一本2/3程度まで銅板を巻きつけてもらい、際や柱周りはコーキングして防水しました。
柱の下は以前のメンテで水抜穴があけてあるので柱のクラックから水が入ったとしても下に抜けかつ乾燥できるようにしています。

ガルバリウム鋼板などは安価ではありますがログの凹凸に合わせて加工しないといけないし、経年劣化での変化を考えれば多少材料が高く付いても銅を選んでおくのが良いと思います。
ステンレスは硬くて加工が大変、アルミは悪くないですが見た目がシルバーだしいずれ腐食して粉吹きになっちゃいますし・・・やっぱ銅なんですねぇ。
南側ログウォールのシルログ、裏側の上部がボッコリと腐食して欠損していました。
ここは勝手口の脇で腐食の発見が早かった為に施主さんがブリキ板を打ち付けていました。

お陰で腐りは止まっていたのですがバックアップ材とチンキングで埋めてしまうにも欠損が大きすぎて・・・で余った銅板でカバーしただけで良い事に。
サドルノッチの削りこみ部分があるので上手く板金を叩いて形状を合わせて・・・・
上下を銅釘で留めてログとの取り合いはチンキングしました。

木口方向からは水が入ることもあるかもしれませんが、これだけ大きく開いていれば乾燥もするし上からは雨水は入らないので水が入るのは台風の時位のものです。
このログの反対側はバックアップとチンクで大手術したとこです。
母屋と棟木も再塗装しました。
母屋先端部も腐りが廻っていましたがこちらも整形せずに腐った部分のみを削り落として防腐処理と再塗装です。

形成不要なのは表からは見えない部分なのと、予算の割り振りの都合上です。
確かに水を落す形状にまで削ったので見た目は良くないですが、逆にここに予算をかけて丸いログに再生したところでそのメリットは?という事でもあります。
限られた予算のなかで様々なメンテを行っています。