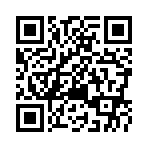2012年11月22日
リノベーション完了
リノベーション工事を行なっていた階段ですが、雨によりなかなか塗装が進みませんでした。
雨の翌日には湿っていて塗装できないからです。
でやっと塗装が終わった階段です。

ちなみにこれがリニューアル前の階段です。

リニューアル後です。

見た目はほぼ変わらないと思います。
まぁ「同じ材料」と「同じデザイン」で作り直していますからね。
塗装は防腐剤塗布の上に、ティックリラのバルチカラー(ステイン)を二回塗りしています。
持ちは3-5年くらいでしょうか?踏み板だけでも3年ペースで追い塗りしておけば持ちは随分と変わります。
雨の翌日には湿っていて塗装できないからです。
でやっと塗装が終わった階段です。

ちなみにこれがリニューアル前の階段です。

リニューアル後です。

見た目はほぼ変わらないと思います。
まぁ「同じ材料」と「同じデザイン」で作り直していますからね。
塗装は防腐剤塗布の上に、ティックリラのバルチカラー(ステイン)を二回塗りしています。
持ちは3-5年くらいでしょうか?踏み板だけでも3年ペースで追い塗りしておけば持ちは随分と変わります。
2012年11月08日
階段のリノベーション
ログハウスではないのですが、木造階段をリノベーションしました。

まずは既存の階段を解体・撤去、既に一部は腐っていますが、一部はまだまだ丈夫です。

解体・撤去終了 ポーチはRCのキャンティレバー

撤去したササラを写して新しいササラを作ります。
材料は2x12です、大分では見つけられなかったので、通販で取り寄せました。
ハンズマンでも2x10までしか置いていません。

ササラは2x12 踏み板も2x12 一発で完成です。

手摺を取り付けました。

ポール上の飾りも再現

あとは塗装ですね。
色の濃い材料は、ACQ防腐剤の注入材です。
色の薄い材料は、ツーバイ材2x12と手摺子だけです。
大工さんと二人で2日で仕上げました。

まずは既存の階段を解体・撤去、既に一部は腐っていますが、一部はまだまだ丈夫です。

解体・撤去終了 ポーチはRCのキャンティレバー

撤去したササラを写して新しいササラを作ります。
材料は2x12です、大分では見つけられなかったので、通販で取り寄せました。
ハンズマンでも2x10までしか置いていません。

ササラは2x12 踏み板も2x12 一発で完成です。

手摺を取り付けました。

ポール上の飾りも再現

あとは塗装ですね。
色の濃い材料は、ACQ防腐剤の注入材です。
色の薄い材料は、ツーバイ材2x12と手摺子だけです。
大工さんと二人で2日で仕上げました。
2012年08月19日
1年点検

下関にて施工させて頂いたログハウスの定期点検(1年点検)を行ないました。
ログハウスは木材を横方向に組みながら積み上げていく工法です。
積み上げて屋根の重さを壁に伝えるのと、木材の乾燥収縮によってログそのものが僅かに痩せる為「セトリング」と呼ばれる乾燥収縮による壁の沈み込みという現象が起きます。
これによって様々なトラブルが起きることはログハウスの宿命のようなものでした。
最新のマシンカットログハウスでは、材料の人口乾燥が適度に行なわれている原材料でログキットが作られている為セトリングの発生量が他のログハウスに比べて「少ない」傾向です。
今回も「通しボルト」の増し締め、基礎や壁のコンディションチェックなどが主な内容でした。
建具は全て木製サッシ、やはり自重で様々に歪んだりたわんだりしようとします。
今回はデッキへの掃き出しドアの調整だけでした。
また、この建物のデザインでは「柱」を多用しています。
先ほどのセトリングして沈む壁に対し、柱は縮まない、縮めないのです。
これでは壁のセトリングと連動出来ないので、柱にはジャッキが噛ませてあり、高さを調整出来るようにしてあるのです。
室外に5本、屋内にも2本のジャッキと柱のある家
ジャッキの調整もやっておきました。
1年の間に、外溝もかなり進んでました。
お隣にも家が建ち、その奥にも家が建てられていました。
このログハウスを中心にちょっとした住宅ラッシュだったようです。
これまではRCの公営団地に長くお住まいだったオーナー様曰く
「快適」
お子さんに見られたアレルギー反応っぽい症状も全く出なくなったそうです。
1年の実生活を通じて、ご満足いただけている様で何よりでした。
ログハウスはメンテナンスが大変な建物、などと言われたりしますが、キチンと作ってあればメンテナンスもそんなに手は掛りません。
それは材料のクオリティも然りですが、やはり施工する大工さんの腕にも左右される事ですね。
2012年05月22日
木製建具のガラス交換 ホンカ編
姉さん、事件です!!
かつてホンカの代理店時代に建てさせて頂いた物件で「事件」は起きました。
ドアのガラスが割れてしまった・・・・

ホンカのフレンチドアやバルコニードア等に採用されていた「KUPドア」です。
玄関などは「HITドア」です。
いずれも採用されていたペアガラスは4㎜+12㎜アルゴンガス+4㎜Low-Eというタイプ
そうそう簡単に割れるガラスではないのですが、不慮の事故により・・・
とりあえずガラスを入替えなきゃいけません。
これまで2度だけガラス交換の経験がありますが、一度は現場で知らないうちに終わっていました。
一度だけガラス交換を見たことがあるのと、ホンカ代理店時代にこの建具を作っていた工場を見学させてもらっていましたので製造工程と仕様等はある程度分っています。
しかし、ホンカに問い合わせてみても「はめこんであるペアガラスのタテヨコサイズ」までは分らない、そして現在はこの建具メーカーの製品は採用していないとの事、現場で実寸を測るしかない・・・
でバラしにかかりました。
バラし方は某T棟梁と一度やっていますので分っています。
木製建具なのでアルミサッシに使われる「ビード」はありません。
木の「押し縁」で押さえてあるだけです、でも押し縁はフィニッシュネイルで打ってあるし、ガラスとの間にはシリコンコーキング
まずシリコンコーキングをカッターで切り取ります。
今、塗装メンテで散々シリコンコーキング切りまくっていたので楽勝です。
次になるべくフレームに傷(凹み)を付けないようにして押し縁を外します。
四方留めになっているので、どこか一面は壊さないと外せません。
押し縁とフレームの間に、ノミ、スクレーパーと挟み込んで隙間を作り、平バールでこじれば押し縁は動きます。鋸で切るか、力技で壊せば外す事が出来ます。

押し縁を外したところです。
フレームに対し一回り小さいサイズでガラスが嵌め込まれているのです。
押し縁との間には弾力性のあるパッキンも挟んであります。
この隙間を採寸すればガラスのサイズが得られます。
最近は4+12+4のアルゴンLow-E仕様のペアガラスも国内で出回るようになっているそうで(以前はこのスペックは無かった)ガラス屋さんに見積依頼です。
でも国産ガラスメーカーさんのは高そう・・・特注サイズやし・・・
さすがにフィンランドからワレモノのガラスを取り寄せるようなマネはしません・・・・
新しいガラスを嵌め込んだら、外した押し縁の使えるパーツは使い、壊した部分は代替品を作り元のように組み付けすれば修理完了となります。
かつてホンカの代理店時代に建てさせて頂いた物件で「事件」は起きました。
ドアのガラスが割れてしまった・・・・

ホンカのフレンチドアやバルコニードア等に採用されていた「KUPドア」です。
玄関などは「HITドア」です。
いずれも採用されていたペアガラスは4㎜+12㎜アルゴンガス+4㎜Low-Eというタイプ
そうそう簡単に割れるガラスではないのですが、不慮の事故により・・・
とりあえずガラスを入替えなきゃいけません。
これまで2度だけガラス交換の経験がありますが、一度は現場で知らないうちに終わっていました。
一度だけガラス交換を見たことがあるのと、ホンカ代理店時代にこの建具を作っていた工場を見学させてもらっていましたので製造工程と仕様等はある程度分っています。
しかし、ホンカに問い合わせてみても「はめこんであるペアガラスのタテヨコサイズ」までは分らない、そして現在はこの建具メーカーの製品は採用していないとの事、現場で実寸を測るしかない・・・
でバラしにかかりました。
バラし方は某T棟梁と一度やっていますので分っています。
木製建具なのでアルミサッシに使われる「ビード」はありません。
木の「押し縁」で押さえてあるだけです、でも押し縁はフィニッシュネイルで打ってあるし、ガラスとの間にはシリコンコーキング
まずシリコンコーキングをカッターで切り取ります。
今、塗装メンテで散々シリコンコーキング切りまくっていたので楽勝です。
次になるべくフレームに傷(凹み)を付けないようにして押し縁を外します。
四方留めになっているので、どこか一面は壊さないと外せません。
押し縁とフレームの間に、ノミ、スクレーパーと挟み込んで隙間を作り、平バールでこじれば押し縁は動きます。鋸で切るか、力技で壊せば外す事が出来ます。

押し縁を外したところです。
フレームに対し一回り小さいサイズでガラスが嵌め込まれているのです。
押し縁との間には弾力性のあるパッキンも挟んであります。
この隙間を採寸すればガラスのサイズが得られます。
最近は4+12+4のアルゴンLow-E仕様のペアガラスも国内で出回るようになっているそうで(以前はこのスペックは無かった)ガラス屋さんに見積依頼です。
でも国産ガラスメーカーさんのは高そう・・・特注サイズやし・・・
さすがにフィンランドからワレモノのガラスを取り寄せるようなマネはしません・・・・
新しいガラスを嵌め込んだら、外した押し縁の使えるパーツは使い、壊した部分は代替品を作り元のように組み付けすれば修理完了となります。
2012年05月05日
ログハウスの外壁塗装

愛媛県八幡浜市S邸ログハウス離れを再塗装 今度は白とグレーのツートンカラーです。
新築みたいになりました。
2001年築ですので11年目にして初の再塗装です。もう数年早く塗っておけば尚良かったですね。

こちらは同じ物件の2005年3月の状態です。雨の当たる部分は結構痛んでいます。
特に屋根の破風と鼻隠しの部分が白く変色してしまっています。

こちらは同じ物件の2003年5月の状態です。まだまだ綺麗ですね。

塗り直した今の状態

2005年3月の状態 下の方に緑色のカビが表面に出ています。

2003年5月の状態 綺麗なままです。
新築当初に塗装したのはティックリラ社のオイルステイン塗料バルチカラー 茶と緑のツートンでした。
新しく塗ったのはティックリラ社の水性塗料ヴィンハ・オパーク 白とグレーのツートンです。
最近の情報なのですが、ヴィンハ・オパークは「杉には不適」との情報がありました。
相性が良くないそうで剥離するらしいのです。
こちらでも実験してみることにします。
米松やウエスタンレッドシーダー、もちろんフィンランドパインには問題なく着色できるのですが・・・
そう言えば杉のログにコレを塗ったことは今までありませんでしたね。
2012年04月09日
色決めは難しい
築20年位のマシンカットログのメンテナンスに入っています。
主には外壁の再塗装です。
古いフィンランドログなのですが、如何せん年月が経っているのと、これまでのメンテナンス状況も決して良好という訳でもありません。
大型の平屋ですが、妻壁の古い塗装をサンダー掛けして落とし、目地に打たれていた古いシリコンコーキングの除去作業と新しくコンシールによる目地シールを行なっています。
新しい塗装には、弊社がレギュラーで採用しているフィンランドのティックリラ社の塗料が採用されました。
水性で塗膜形成し強い耐久性を発揮する「VINHA OPEC」です。
明るい色から深い色まで様々な色が用意されています。
カラーチップで決定して頂いた色は、たまたま使い残しが在庫されていたので、板切れに塗装して現場で壁に当ててみました。
するとやはり施主様がイメージしていたより色が明るい・・・
周辺の景色と近所のログカラーとのマッチング的にも明るすぎで浮いてしまいがち・・・
で急遽色選択をやり直す事に・・・
カラーチップだけで最終決定していたら、結構な量を取り寄せる事になっていたし返品は利かないので大変な事になるところでした。
慎重にやっててヨカッタ
主には外壁の再塗装です。
古いフィンランドログなのですが、如何せん年月が経っているのと、これまでのメンテナンス状況も決して良好という訳でもありません。
大型の平屋ですが、妻壁の古い塗装をサンダー掛けして落とし、目地に打たれていた古いシリコンコーキングの除去作業と新しくコンシールによる目地シールを行なっています。
新しい塗装には、弊社がレギュラーで採用しているフィンランドのティックリラ社の塗料が採用されました。
水性で塗膜形成し強い耐久性を発揮する「VINHA OPEC」です。
明るい色から深い色まで様々な色が用意されています。
カラーチップで決定して頂いた色は、たまたま使い残しが在庫されていたので、板切れに塗装して現場で壁に当ててみました。
するとやはり施主様がイメージしていたより色が明るい・・・
周辺の景色と近所のログカラーとのマッチング的にも明るすぎで浮いてしまいがち・・・
で急遽色選択をやり直す事に・・・
カラーチップだけで最終決定していたら、結構な量を取り寄せる事になっていたし返品は利かないので大変な事になるところでした。
慎重にやっててヨカッタ
2011年11月08日
再塗装終了
築8年目にして行なわれていたログハウスの再塗装メンテナンスが終了しました。
ログ壁、ケーシング(額縁)、破風鼻隠し、ポストなどをティックリラの水性塗料「ヴィンハ・オパーク」で二度塗りです。
私の経験上、かなり耐候性に優れている実績をもつ塗料です、フィンランドパインにはベストマッチ?ではないでしょうか?

再塗装後の姿です。
現ランタサルミの「ゲストハウス」が開発した人気モデル
ホンカの「アウリンコ」です。
かつて私がセールスマン時代に、最も沢山お買い上げ頂いたモデルでもあります。
やはり化粧直しして格好が良いですね。
アウリンコはやっぱり正面が開いているこのデザインが最も格好がいいと思っています。
確かに正面から登って玄関がわに寄るのは面倒っちゃ面倒なのですが、慣れれば・・・

建物の裏側だって格好良いんです。
この建物は勝手口を設けるアレンジが施されています。
他にもオリジナルとはちょっと違う、ウエストガーデンスペシャルアレンジが施されております。
スズメバチの巣はこの妻壁最上部に作られていました。

妻壁上部には換気扇の排気口が設けられています。
夏の暑さ対策として、二階ロフト上部に熱排気用の換気扇を設けたのです。
でこの排気口にスズメが営巣、換気口を完全に塞いでいました。
なのでこのガラリに細工して防鳥網を取り付けました、足場のあるうちにやっておかないとね。

我が家では犬小屋もログハウスなのです。
ログ壁、ケーシング(額縁)、破風鼻隠し、ポストなどをティックリラの水性塗料「ヴィンハ・オパーク」で二度塗りです。
私の経験上、かなり耐候性に優れている実績をもつ塗料です、フィンランドパインにはベストマッチ?ではないでしょうか?

再塗装後の姿です。
現ランタサルミの「ゲストハウス」が開発した人気モデル
ホンカの「アウリンコ」です。
かつて私がセールスマン時代に、最も沢山お買い上げ頂いたモデルでもあります。
やはり化粧直しして格好が良いですね。
アウリンコはやっぱり正面が開いているこのデザインが最も格好がいいと思っています。
確かに正面から登って玄関がわに寄るのは面倒っちゃ面倒なのですが、慣れれば・・・

建物の裏側だって格好良いんです。
この建物は勝手口を設けるアレンジが施されています。
他にもオリジナルとはちょっと違う、ウエストガーデンスペシャルアレンジが施されております。
スズメバチの巣はこの妻壁最上部に作られていました。

妻壁上部には換気扇の排気口が設けられています。
夏の暑さ対策として、二階ロフト上部に熱排気用の換気扇を設けたのです。
でこの排気口にスズメが営巣、換気口を完全に塞いでいました。
なのでこのガラリに細工して防鳥網を取り付けました、足場のあるうちにやっておかないとね。

我が家では犬小屋もログハウスなのです。
2011年11月05日
再塗装

築8年目にしてやっとこさ再塗装を行なっています。
やっぱり5年目くらいが節目でした、塗ろう塗ろうと思いつつタイミングを逸すること2年
昨年の暮に高圧洗浄して冬のあいだにやろうとして・・・・そのまんま・・・

昨年の画像、南側はかなり痛んでいます。
新築当時に塗っていた塗装は、ランタサルミやホンカ推奨のティックリラ
グレーの外壁はバルチカラー オイルステインです。
破風や額縁、ポストなどはヴィンハ・オパーク 水性塗料です。
ヴィンハはオパークの冠の通り塗膜形成して木目が消えてしまうタイプの塗料です。
しかしオイルステインのバルチカラーよりも耐候性能に優れています。

今回はオール ヴィンハ・オパークです。
外壁 カラーコード2681グレー
破風他 カラーコード2661ホワイト
額縁 カラーコード2685青
ドア カラーコード2670ワインレッド
再塗装すると新築みたいに生まれ変わります。
塗装の耐久性については様々な意見がございますが、ティックリラは入手経路は限られますがフィンランドメーカーでホンカと共同開発している塗料メーカーだけに、フィンランドパインとのマッチングはかなりいいレベルだと思っています。
木の塗装は難しく、塗料によって手順が異なります。
ティックリラの塗装も、ベースと呼んでいる防腐剤入りのプライマー塗装をした上に、バルチカラーやヴィンハを塗って仕上げています。仕上げは二階塗りですから、都合3回塗っている訳です。
塗料の性能は、乾くことで揮発する溶剤の後に残される顔料の質と量ですね。
顔料は紫外線によって劣化し、やがて木肌を守れなくなるので、そうなった時がメンテナンスのタイミングです。
建物の環境によっても耐久性は違うし、選ぶカラーによっても違いが有ります。
経験上、薄い茶色が最も劣化が早く、濃い色のほうが長持ちします。
2011年10月19日
再塗装工事
2003年年末竣工の我が家ですが、いよいよ再塗装のメンテナンスに入りました。
時間を見つけて自分で塗ろう、なんて考えていましたが
忙しくてとても無理っ!!
の状態で早3年・・・
さすがに最初に塗ったティックリラのバルチカラーもいよいよ退色してきており、南側はヤバイ状態に・・
なので塗装屋さんに依頼しました。
北側も塗装は残っているものの限界ですね。
バルチカラーのグレー、なかなかよく持ってくれたと思います。
新しい色は・・・
ほぼそのままのグレーです・・・・
但し、バルチカラー・オペックを使用します。
オペックシリーズは塗膜を形成するタイプの水性塗料です。
塗膜を作るので木目は消えてしまいます。
でも仕上がりは綺麗です。
耐久性も申し分ありません。
今日は建物を高圧洗浄で水洗い、少しノッチが染みたり、一部から水が入って来りしています。
全般的に汚れも落ちて綺麗になりました。
明日の足場組の現調に来ていた足場屋さんが、北側の棟下にスズメバチの巣を発見
大きなのが2つありました。
うち1つは放棄巣でした、ハチの居た巣はハチジェットスプレーで攻撃して夕方撤去しました。
割と大きな巣だったのでこっちも必死での作業でした。
ヘタに刺されるとスズメバチはヤバイですから。
時間を見つけて自分で塗ろう、なんて考えていましたが
忙しくてとても無理っ!!
の状態で早3年・・・
さすがに最初に塗ったティックリラのバルチカラーもいよいよ退色してきており、南側はヤバイ状態に・・
なので塗装屋さんに依頼しました。
北側も塗装は残っているものの限界ですね。
バルチカラーのグレー、なかなかよく持ってくれたと思います。
新しい色は・・・
ほぼそのままのグレーです・・・・
但し、バルチカラー・オペックを使用します。
オペックシリーズは塗膜を形成するタイプの水性塗料です。
塗膜を作るので木目は消えてしまいます。
でも仕上がりは綺麗です。
耐久性も申し分ありません。
今日は建物を高圧洗浄で水洗い、少しノッチが染みたり、一部から水が入って来りしています。
全般的に汚れも落ちて綺麗になりました。
明日の足場組の現調に来ていた足場屋さんが、北側の棟下にスズメバチの巣を発見
大きなのが2つありました。
うち1つは放棄巣でした、ハチの居た巣はハチジェットスプレーで攻撃して夕方撤去しました。
割と大きな巣だったのでこっちも必死での作業でした。
ヘタに刺されるとスズメバチはヤバイですから。
2010年04月18日
床下点検
築5年の顧客宅訪問
今回は床下の点検です。
弊社プロデュースのログハウスは、深めの軒を設計します。
しかし、雨が地面に跳ね返って建物外壁のログに当って濡れない様に基礎の高さも一般住宅より高めに設定しています。
最低でもGL+500です。
床は大抵+204なのでGL(グランドレベル)+704が室内床高さですねー
床下に50センチの隙間があるので、人間が容易に潜る事が出来ます。
その潜入口として床下収納など床下への入口も設けています。
給排水管からの漏水、電気配線の異常、シロアリの侵入が無いか?などを点検します。
ついでに床下の乾燥具合もチェックします。
30分以上は床下を外周部中心にゴソゴソと這いずり廻っておりました。
その前には屋根にへばりついての煙突掃除でした。
床下に潜れない家もままあると耳にします。
何か起った時の対応が厄介ですよ、場合によっては床を壊さないと対処出来ない事も・・
シロアリ侵入の発見も遅れがちになります。
出来れば1年に1回、無理でも3年とか5年とか
床下も潜って点検しましょう。
ログハウスだろうと在来建築だろうと軽量鉄骨だろうと、床下の点検は大切ですよ。
何事も無くてあたりまえですが。
今回は床下の点検です。
弊社プロデュースのログハウスは、深めの軒を設計します。
しかし、雨が地面に跳ね返って建物外壁のログに当って濡れない様に基礎の高さも一般住宅より高めに設定しています。
最低でもGL+500です。
床は大抵+204なのでGL(グランドレベル)+704が室内床高さですねー
床下に50センチの隙間があるので、人間が容易に潜る事が出来ます。
その潜入口として床下収納など床下への入口も設けています。
給排水管からの漏水、電気配線の異常、シロアリの侵入が無いか?などを点検します。
ついでに床下の乾燥具合もチェックします。
30分以上は床下を外周部中心にゴソゴソと這いずり廻っておりました。
その前には屋根にへばりついての煙突掃除でした。
床下に潜れない家もままあると耳にします。
何か起った時の対応が厄介ですよ、場合によっては床を壊さないと対処出来ない事も・・
シロアリ侵入の発見も遅れがちになります。
出来れば1年に1回、無理でも3年とか5年とか
床下も潜って点検しましょう。
ログハウスだろうと在来建築だろうと軽量鉄骨だろうと、床下の点検は大切ですよ。
何事も無くてあたりまえですが。
2009年09月10日
浄化槽のプロアが壊れました
田舎の簡易下水道「合併浄化槽」のブロアが壊れました。
何か最近排水が臭うな・・・と思ってたらプロアが動いてない・・・
合併浄化槽は嫌気性バクテリアと好気性バクテリアの両方で汚物を分解処理して排水をクリーンにしてくれるのですが、今の我が家の浄化槽はフロアから空気が供給されない為好気性バクテリアがほぼ全滅していると思われ・・・
浄化槽の管理は「浄化槽法」に則って正しく行なわなくてはならない事になっています。
年に一度は法廷検査もあります。
これによって浄化槽が正しく機能しているかどうかチェックする訳ですね。
もちろん我が家の今の状態では「ダメ」です。
浄化槽そのものは地中に埋められているのでほとんど消耗することはないでしょう。
ただ浄化槽の中にはバクテリアが分解したカスである「汚泥」が溜まります。
この汚泥の蓄積が増えると、浄化機能が低下してしまうので汚泥を除去してやる必要があります。
これは自治体や民間の汚物処理業者に依頼してバキュームカーに来てもらって吸い取ってもらえば良いですね。
浄化槽のメンテナンスポイントは「ブロア」です。
これはモーターで動いている空気ポンプですからいつかは壊れてしまいます。
そして定期メンテナンスと部品交換が必要です。
新しいプロアを見積もったら5万円以上しました。
容量80で2穴平行タイプです。
試しに修理と言って見たら「その機種でしたらまず直せると思います」と言うので外して預けて来ました。
どうやら年に一度交換するダイヤフラムという消耗部品を交換していなかった様子
管理に来る人は何やってんねん・・・
使い始めて6年目
この機会に汚泥を全部バキュームしてもらってリセット状態にしましょうかねー 。
皆さんのお宅の浄化槽
キチンと機能していますか?
あっ「下水」のあるお宅には浄化槽はありませんよー。
何か最近排水が臭うな・・・と思ってたらプロアが動いてない・・・
合併浄化槽は嫌気性バクテリアと好気性バクテリアの両方で汚物を分解処理して排水をクリーンにしてくれるのですが、今の我が家の浄化槽はフロアから空気が供給されない為好気性バクテリアがほぼ全滅していると思われ・・・
浄化槽の管理は「浄化槽法」に則って正しく行なわなくてはならない事になっています。
年に一度は法廷検査もあります。
これによって浄化槽が正しく機能しているかどうかチェックする訳ですね。
もちろん我が家の今の状態では「ダメ」です。
浄化槽そのものは地中に埋められているのでほとんど消耗することはないでしょう。
ただ浄化槽の中にはバクテリアが分解したカスである「汚泥」が溜まります。
この汚泥の蓄積が増えると、浄化機能が低下してしまうので汚泥を除去してやる必要があります。
これは自治体や民間の汚物処理業者に依頼してバキュームカーに来てもらって吸い取ってもらえば良いですね。
浄化槽のメンテナンスポイントは「ブロア」です。
これはモーターで動いている空気ポンプですからいつかは壊れてしまいます。
そして定期メンテナンスと部品交換が必要です。
新しいプロアを見積もったら5万円以上しました。
容量80で2穴平行タイプです。
試しに修理と言って見たら「その機種でしたらまず直せると思います」と言うので外して預けて来ました。
どうやら年に一度交換するダイヤフラムという消耗部品を交換していなかった様子
管理に来る人は何やってんねん・・・
使い始めて6年目
この機会に汚泥を全部バキュームしてもらってリセット状態にしましょうかねー 。
皆さんのお宅の浄化槽
キチンと機能していますか?
あっ「下水」のあるお宅には浄化槽はありませんよー。
2009年09月02日
デッキの塗装

ログハウスではありませんが、在来住宅のウッドデッキを塗装しています。
数年前に建物全体の再塗装工事を請け負ったお客様から、その時には塗らなかったデッキ部分のみの塗装を依頼されたのです。
デッキ材は地元日田杉、新築時に塗装されていたのですが、既にボロボロになっていて水も染み放題でした。
再塗装前に高圧洗浄機でデッキを水洗い。
古い塗膜の残っているところもガッツリと洗っていただきました。
コストダウンの為にこの作業は施主さん自ら行われました。
今回使っている塗料は「オスモカラー ウッドステインプロテクター」です。
デッキオイルでも良かったのですが、プロテクターがキャンペーン価格で安かったもので・・・
塗装も剥げ、紫外線で灰色に痛んでいたデッキですが、洗浄で汚れを落としてやるとまぁまぁのコンディションです。
さりとて雨ざらしとなるデッキですから、杉材での耐久年数は知れたもの。
「ダメになったら張り替える」そんなつもりで居てくださいね、とアドバイスはしていたものの、やはり張り直しよりも塗装のメンテナンスで少しでも寿命を延ばしてやろうという事です。

ウッドステインプロテクターは外部用塗料ですが、UVカット成分は入っていません。
なので数年の耐久性しか期待できないのですが、〇〇ソートなどの安くて手軽に入手できる防腐塗料では色も綺麗じゃないし、特に臭いが石油臭く刺激臭なので「絶対NG」なのです。
建物東西南と3面にあるウッドデッキに二度塗りの予定です。
思いのほか1度目の塗装が木に吸われた為、二度塗りが1/3程度で塗料が尽きてしまいました。
塗料待ちで1日間が開きそうです。
ウッドデッキ、基本的には消耗品ですが、塗装によって耐久性をUPさせ長持ちさせる事が出来ます。
2008年08月22日
巻きましょう
メンテもいよいよ終盤です。
最大の課題であった東面の二階バルコニーを支えている梁の腐りをどうするか。
雨ざらしでボロボロになっている梁でしたが、シロタの部分はやられていても赤身の部分はしっかりしています。

梁にはポストが立てられて屋根荷重を負担しているようにも見えるのですが、そもそも軒の突き出しが母屋でも1200程度しかなく方杖も入っているので「このポスト自体の過重負担はほとんどない」と判断、ならば心材だけでもデッキ部分は十分に保持できるので梁の補強とか交換はやらずに「銅板を巻いてしまい雨が当らなくする」という方法を取りました。
もちろんコストも考慮した結果です。

梁一本2/3程度まで銅板を巻きつけてもらい、際や柱周りはコーキングして防水しました。
柱の下は以前のメンテで水抜穴があけてあるので柱のクラックから水が入ったとしても下に抜けかつ乾燥できるようにしています。

ガルバリウム鋼板などは安価ではありますがログの凹凸に合わせて加工しないといけないし、経年劣化での変化を考えれば多少材料が高く付いても銅を選んでおくのが良いと思います。
ステンレスは硬くて加工が大変、アルミは悪くないですが見た目がシルバーだしいずれ腐食して粉吹きになっちゃいますし・・・やっぱ銅なんですねぇ。
南側ログウォールのシルログ、裏側の上部がボッコリと腐食して欠損していました。
ここは勝手口の脇で腐食の発見が早かった為に施主さんがブリキ板を打ち付けていました。

お陰で腐りは止まっていたのですがバックアップ材とチンキングで埋めてしまうにも欠損が大きすぎて・・・で余った銅板でカバーしただけで良い事に。
サドルノッチの削りこみ部分があるので上手く板金を叩いて形状を合わせて・・・・
上下を銅釘で留めてログとの取り合いはチンキングしました。

木口方向からは水が入ることもあるかもしれませんが、これだけ大きく開いていれば乾燥もするし上からは雨水は入らないので水が入るのは台風の時位のものです。
このログの反対側はバックアップとチンクで大手術したとこです。
母屋と棟木も再塗装しました。
母屋先端部も腐りが廻っていましたがこちらも整形せずに腐った部分のみを削り落として防腐処理と再塗装です。

形成不要なのは表からは見えない部分なのと、予算の割り振りの都合上です。
確かに水を落す形状にまで削ったので見た目は良くないですが、逆にここに予算をかけて丸いログに再生したところでそのメリットは?という事でもあります。
限られた予算のなかで様々なメンテを行っています。
最大の課題であった東面の二階バルコニーを支えている梁の腐りをどうするか。
雨ざらしでボロボロになっている梁でしたが、シロタの部分はやられていても赤身の部分はしっかりしています。

梁にはポストが立てられて屋根荷重を負担しているようにも見えるのですが、そもそも軒の突き出しが母屋でも1200程度しかなく方杖も入っているので「このポスト自体の過重負担はほとんどない」と判断、ならば心材だけでもデッキ部分は十分に保持できるので梁の補強とか交換はやらずに「銅板を巻いてしまい雨が当らなくする」という方法を取りました。
もちろんコストも考慮した結果です。

梁一本2/3程度まで銅板を巻きつけてもらい、際や柱周りはコーキングして防水しました。
柱の下は以前のメンテで水抜穴があけてあるので柱のクラックから水が入ったとしても下に抜けかつ乾燥できるようにしています。

ガルバリウム鋼板などは安価ではありますがログの凹凸に合わせて加工しないといけないし、経年劣化での変化を考えれば多少材料が高く付いても銅を選んでおくのが良いと思います。
ステンレスは硬くて加工が大変、アルミは悪くないですが見た目がシルバーだしいずれ腐食して粉吹きになっちゃいますし・・・やっぱ銅なんですねぇ。
南側ログウォールのシルログ、裏側の上部がボッコリと腐食して欠損していました。
ここは勝手口の脇で腐食の発見が早かった為に施主さんがブリキ板を打ち付けていました。

お陰で腐りは止まっていたのですがバックアップ材とチンキングで埋めてしまうにも欠損が大きすぎて・・・で余った銅板でカバーしただけで良い事に。
サドルノッチの削りこみ部分があるので上手く板金を叩いて形状を合わせて・・・・
上下を銅釘で留めてログとの取り合いはチンキングしました。

木口方向からは水が入ることもあるかもしれませんが、これだけ大きく開いていれば乾燥もするし上からは雨水は入らないので水が入るのは台風の時位のものです。
このログの反対側はバックアップとチンクで大手術したとこです。
母屋と棟木も再塗装しました。
母屋先端部も腐りが廻っていましたがこちらも整形せずに腐った部分のみを削り落として防腐処理と再塗装です。

形成不要なのは表からは見えない部分なのと、予算の割り振りの都合上です。
確かに水を落す形状にまで削ったので見た目は良くないですが、逆にここに予算をかけて丸いログに再生したところでそのメリットは?という事でもあります。
限られた予算のなかで様々なメンテを行っています。
2008年08月05日
積みましょう
外部塗装が行われているのと同時進行で室内ではストーブの炉台の作り替え工事です。
まず室内の煙突を外してストーブをどかします。

ストーブはモルソーの1510、既にラインナップにはないストーブです。
現行の炉台はオーナーがセルフで作ったもの、35ミリ厚のレンガを何故か縦使いで積み上げたもので安定性もイマイチだし対火性能でも不安が残るところです。
まぁストーブのフルメンテナンスと合わせて作り直すことになりました。

ハツリ機まで持ち込みましたが、薄いレンガゆえちよっとハツって手で壊せてしまいました。
うーん、大きな地震が来れば自壊していたかも・・・です。
古い炉台を壊している間にストーブのチェック

内部の耐火レンガにヒビが見られます、このまま使い続けられなくもないのですが、背面とサイドの一枚を交換することになりました。
新しい炉台はベルギーレンガの赤白で赤目にて作ります。
レンガは350個用意しました。
メーカー発注でも良いのですが、ダイレクトに頼むとレンガの送料が凄いことになります。
結構メジャーなメーカーの品物がHCの軒先に積んであったりしますし、HCはトラック貸してくれたりするので近くのHCの品揃えから選びました。

底はコンパネ補強(もともと基礎から補強してある)してシート張ってレンガを並べ壁を積んでいきます。

その間に煙突も掃除しておきます。
屋根に登って角煙突のトップを開けると・・・いやー溜まりに溜まっておりました。
2-3センチも煤が堆積していたのですがヘラで削って袋に・・・
炎天下の屋根の上で汗べっとりで煤と格闘です。
室内はカバーしてあるとはいうものの余り煤は落せないので出来るだけ上で回収です。
煙突は掃除ブラシで中の煤をこそぎ落します。

炉台が積み上がりました。
サイドには小物入れも設けています、あとは目地を詰めれば・・・

白目地を詰めていい感じに仕上がりました。
当初はもう少し高くする予定でしたが、隣の冷蔵庫扉の開閉に干渉してしまうのでこの高さで止めました。

ストーブを戻して煙突を繋げばOKです。
外した煙突は室外で中の掃除をしておきます。
スーパーの袋一杯分の煤が出てきました。
炉台底は以前より高くなり、端も厚くなったのでストーブの位置が若干変わりました、煙突がそのまま付かなければ切断など加工をしなくてはなりません。
半ば強引でしたが外したののま煙突でなんとか繋ぐことが出来ました。

これで一段落、後は耐火レンガの交換のみです。
まず室内の煙突を外してストーブをどかします。

ストーブはモルソーの1510、既にラインナップにはないストーブです。
現行の炉台はオーナーがセルフで作ったもの、35ミリ厚のレンガを何故か縦使いで積み上げたもので安定性もイマイチだし対火性能でも不安が残るところです。
まぁストーブのフルメンテナンスと合わせて作り直すことになりました。

ハツリ機まで持ち込みましたが、薄いレンガゆえちよっとハツって手で壊せてしまいました。
うーん、大きな地震が来れば自壊していたかも・・・です。
古い炉台を壊している間にストーブのチェック

内部の耐火レンガにヒビが見られます、このまま使い続けられなくもないのですが、背面とサイドの一枚を交換することになりました。
新しい炉台はベルギーレンガの赤白で赤目にて作ります。
レンガは350個用意しました。
メーカー発注でも良いのですが、ダイレクトに頼むとレンガの送料が凄いことになります。
結構メジャーなメーカーの品物がHCの軒先に積んであったりしますし、HCはトラック貸してくれたりするので近くのHCの品揃えから選びました。

底はコンパネ補強(もともと基礎から補強してある)してシート張ってレンガを並べ壁を積んでいきます。

その間に煙突も掃除しておきます。
屋根に登って角煙突のトップを開けると・・・いやー溜まりに溜まっておりました。
2-3センチも煤が堆積していたのですがヘラで削って袋に・・・
炎天下の屋根の上で汗べっとりで煤と格闘です。
室内はカバーしてあるとはいうものの余り煤は落せないので出来るだけ上で回収です。
煙突は掃除ブラシで中の煤をこそぎ落します。

炉台が積み上がりました。
サイドには小物入れも設けています、あとは目地を詰めれば・・・

白目地を詰めていい感じに仕上がりました。
当初はもう少し高くする予定でしたが、隣の冷蔵庫扉の開閉に干渉してしまうのでこの高さで止めました。

ストーブを戻して煙突を繋げばOKです。
外した煙突は室外で中の掃除をしておきます。
スーパーの袋一杯分の煤が出てきました。
炉台底は以前より高くなり、端も厚くなったのでストーブの位置が若干変わりました、煙突がそのまま付かなければ切断など加工をしなくてはなりません。
半ば強引でしたが外したののま煙突でなんとか繋ぐことが出来ました。

これで一段落、後は耐火レンガの交換のみです。
2008年07月30日
補修しましょう
チンキングによるログの部分補修です。
南東角のシルログ(一番下のログ)、クラックから入った水でログ上部が大きく腐食、腐った部分を取り除いて防腐剤でベタベタにしてからチンキングです。
まずそのままチンク材をつめるとカートリッジ1本あっちゅーまに飲み込んでしまいそうなのでチンク材を節約する為にもバックアップ材でかさ上げです。

クラックだとその割れ目にバックアップ材を詰め込んでやれば良いのですが、広い面となればバックアップ材が動かないようにタッカーで留めてしまいます。
深いところには太い奴を、浅いところには細い奴を、こうやってある程度凹を埋めてやります。
バックアップ材を使わずにある種のコンクリートボンドを放り込んで埋める手もあります。

今度はビッグストレッチを塗りたくって表面を形成します。
ビッグストレッチも水性なので荒整形したあとに指先に水をつけてペタペタなぞると綺麗な表面になります。上手くやれば先端の¬部も綺麗に形成できそうですが、ヘラとか使いきれないので曲面仕上げにしました。一晩乾かして塗装すればこの通りです。
一見するとこの部分が欠損していたとは分かりません。

そして東面のシルログ、ペンキが塗ってあるので表面的には良さそうですがペンキの裏側では確実に腐朽が進行していました。


サンダーをかけているとボッコリ穴が開いて木屑がボロボロ出てきます。
腐ってしまった部分を掘り出すとシロタの部分はほぼダメでした、赤身の芯近くはまだしっかりしていたためそこまでほじくって防腐剤をタップリと塗って・・・さぁて仕上げはと゜うしたものか。


当初は檜丸太からログの形に削りだした材をダミーカバーとして付ける予定でした、でもコストが更に積み増しされてしまうしこちら側は建物の裏側なので来客の目に触れる場所でもありません。
板でカバーしてくれりゃいいと言われても、ペラペラの板では役不足だし板金処理もまた目立ち過ぎてしまいます。そこでツーバイ材の41x140という板を上手く合わせてカバーしてみました。
板も厚みがあるので存在感は十分だし塗装すれば割といいマッチングです。(塗装した板を取り付けて更に再塗装しています)
他のログとの取り合いをシールしてやれば良さそうな仕上がりです。



そもそもこのシルログが傷んでしまった原因は「浅い軒」と「海からの湿った風」「東面」「ログギリギリまでのウッドデッキ施工」など複合要因によるものと分析しています。浅い軒で濡れたシルログ、東面で正午前には日影になってしまい十分に乾燥させることが出来ない場所です、さらに眼下の海から湿った風が吹き寄せ乾きにくいコンディションです。
追い討ちをかけるかのようにログギリギリまで張られているウッドデッキによってデッキに落ちた水が風に押されてシルログを濡らしてしまうような構造になっていました。
軒を伸ばすことは今更出来ないのでまずはウッドデッキの端を切って3-5センチのクリアランスを設けました。これでデッキに落ちる雨水がデッキの手前で落ちてくれます。ハネ返りの雨水からは塗装で守ります。更にカバーの板が腐っても容易に取り替えられます。

元はこんな風にデッキ板がログギリギリまで延ばされていました。
これでは風で水が押されてログをよじ登ってしまいます、また濡れたログの乾きも悪いですね。

デッキ板の端を少し切り落としました。これで雨水対策は結構改善されるはずです。
この対策で今後どれだけ半分腐ったシルログをガードし続けられるか・・です。
最初の設計時にもっと軒を長くしていればこんな事にはなっていなかったと思われます。
木造の建物は寺社仏閣のように深い軒で構造を雨水から守る、これは設計のセオリーとも言えますが、最近の建物はコストダウンやデザイン優先で軒を短くすることが多いですね。
あっ、軒先を貸して母屋を取られないようにしているのかもしれません。
南東角のシルログ(一番下のログ)、クラックから入った水でログ上部が大きく腐食、腐った部分を取り除いて防腐剤でベタベタにしてからチンキングです。
まずそのままチンク材をつめるとカートリッジ1本あっちゅーまに飲み込んでしまいそうなのでチンク材を節約する為にもバックアップ材でかさ上げです。

クラックだとその割れ目にバックアップ材を詰め込んでやれば良いのですが、広い面となればバックアップ材が動かないようにタッカーで留めてしまいます。
深いところには太い奴を、浅いところには細い奴を、こうやってある程度凹を埋めてやります。
バックアップ材を使わずにある種のコンクリートボンドを放り込んで埋める手もあります。

今度はビッグストレッチを塗りたくって表面を形成します。
ビッグストレッチも水性なので荒整形したあとに指先に水をつけてペタペタなぞると綺麗な表面になります。上手くやれば先端の¬部も綺麗に形成できそうですが、ヘラとか使いきれないので曲面仕上げにしました。一晩乾かして塗装すればこの通りです。
一見するとこの部分が欠損していたとは分かりません。

そして東面のシルログ、ペンキが塗ってあるので表面的には良さそうですがペンキの裏側では確実に腐朽が進行していました。


サンダーをかけているとボッコリ穴が開いて木屑がボロボロ出てきます。
腐ってしまった部分を掘り出すとシロタの部分はほぼダメでした、赤身の芯近くはまだしっかりしていたためそこまでほじくって防腐剤をタップリと塗って・・・さぁて仕上げはと゜うしたものか。


当初は檜丸太からログの形に削りだした材をダミーカバーとして付ける予定でした、でもコストが更に積み増しされてしまうしこちら側は建物の裏側なので来客の目に触れる場所でもありません。
板でカバーしてくれりゃいいと言われても、ペラペラの板では役不足だし板金処理もまた目立ち過ぎてしまいます。そこでツーバイ材の41x140という板を上手く合わせてカバーしてみました。
板も厚みがあるので存在感は十分だし塗装すれば割といいマッチングです。(塗装した板を取り付けて更に再塗装しています)
他のログとの取り合いをシールしてやれば良さそうな仕上がりです。



そもそもこのシルログが傷んでしまった原因は「浅い軒」と「海からの湿った風」「東面」「ログギリギリまでのウッドデッキ施工」など複合要因によるものと分析しています。浅い軒で濡れたシルログ、東面で正午前には日影になってしまい十分に乾燥させることが出来ない場所です、さらに眼下の海から湿った風が吹き寄せ乾きにくいコンディションです。
追い討ちをかけるかのようにログギリギリまで張られているウッドデッキによってデッキに落ちた水が風に押されてシルログを濡らしてしまうような構造になっていました。
軒を伸ばすことは今更出来ないのでまずはウッドデッキの端を切って3-5センチのクリアランスを設けました。これでデッキに落ちる雨水がデッキの手前で落ちてくれます。ハネ返りの雨水からは塗装で守ります。更にカバーの板が腐っても容易に取り替えられます。

元はこんな風にデッキ板がログギリギリまで延ばされていました。
これでは風で水が押されてログをよじ登ってしまいます、また濡れたログの乾きも悪いですね。

デッキ板の端を少し切り落としました。これで雨水対策は結構改善されるはずです。
この対策で今後どれだけ半分腐ったシルログをガードし続けられるか・・です。
最初の設計時にもっと軒を長くしていればこんな事にはなっていなかったと思われます。
木造の建物は寺社仏閣のように深い軒で構造を雨水から守る、これは設計のセオリーとも言えますが、最近の建物はコストダウンやデザイン優先で軒を短くすることが多いですね。
あっ、軒先を貸して母屋を取られないようにしているのかもしれません。
2008年07月27日
塗りましょう
古いアクリルペンキの剥離が終われば新しい塗装工程です。

最初に施主さんが塗った塗料はシッケンズ・セトール7でした。そしてシッケンズで部分的なメンテをやった後にアクリルペンキを塗ってしまったそうな・・・
で今回のメンテナンスにおいてはフィンランドのティックリラの塗料を使う事になりました。

最初はもっと安価で入手の易いものを塗る予定だったのですが、ネタは高い安いはあっても塗る手間賃はほとんど変わりません。(実際には1工程増えるのでそれなりにコスト増なのですが・・・)それに「色と耐久性」という課題において安価な塗料に「綺麗で明るい色」というのは皆無に近いですね。
現状濃茶のログウォールですがティックリラを使えばこれを真っ白にでも真っ青や真っ赤にでも出来てしまいます、そして選んだ色は「明るい茶色」です。
ログのメンテナンス塗装においては新築時が一番明るくて、時を重ねるごとに色を深くしていく傾向が多いかと思います。この建物も当初は更に濃い色にする予定でした。しかし塗料から揮発する臭いに奥様が難色を示され、結果追加料金ですがこの塗装になりました。
当初のネタに比べて塗料代で数倍近のコスト増なのですが、トータルでは追加ン万円ですからよい判断をしていただいたと思っています。
こちらとしても最初の油性塗料を塗るのは汚れと臭いから覚悟が必要でしたので・・・
ティックリラを使うのであればそれなりにちゃんと使いたいものです。
まず最初に無垢の木肌にベース剤を塗布します。ティックリラベースというこの製品は防腐防カビ剤です、そして塗料を吸込む木肌に塗ることで塗料の吸い込みを抑える働きもあります。
このベースは無垢木肌の時だけしか使えない(塗装面に使っても浸透しないので意味が無い)ので剥離作業をやった今だけしか施工できません。新築の際にも最初の塗装時にのみ施工しますが「これを塗っておくのと塗らないのとでは後で大違い」なのです。
で下塗りみたいなものなので助っ人さんにベタベタとタップリ塗ってもらいます。
剥離してからずっと晴天続きでログ表面も十分に乾いており理想的な工程です。
これを塗ってしまえば雨が降ってもカビが出たりすることはもうありません。
ベースを乾かして本ネタを塗ります。
ティックリラのヴィンハ・オパークというこの製品、水性塗料で塗膜形成タイプです。
オスモのカントリーカラーに似ていますが向うは油性塗料、ちなみに水性油性とは塗料の顔料成分を油で溶いてあるのか水で溶いてあるのかの違いですから「水性だと雨が降れば塗装が流れてしまう・・・」なんてことはアルワケない。水も油も塗布後に乾いて無くなってしまい、木には顔料成分が残される訳です。
水性だと道具の洗浄も水洗いでOKだし、何と言っても油性溶剤のあの鼻につく独特の臭いもありません。実は施工する私たちも楽なのです。
そして最大のメリットは、塗幕形成タイプなのでヌリムラが出にくく仕上がりが綺麗なのです。
この塗装を二度塗り、ベースと合わせて3度塗って仕上がりです。

一度塗りでも画像では塗装部分がクッキリですね、゛も近くで見ると一度はやはり薄いです。
午前中は日差しの強い東面を避けて日影の南面を、午後から日陰になった東面をと日影を求めての作業です。

一発目が半分位まで進んだ東面、背後は海です。海風は心地よいのですが・・・日射が・・・

南面はニ発目も終わって完成、あのボッコリと腐って埋めたログのところも綺麗に何事もなかったかのように仕上がってます。
西面は何もやっていません、こちらはアクリルペンキも塗られていないし、デッキから低い脚立で容易にメンテできるのとほとんど傷んでないのでオーナーさんのセルフメンテです。
色の違いがクッキリとして・・・まぁ次期メンテで同じ色を塗ってもらえれば・・です。

塗装面のアップです。
真中少し上にチンキングしたクラックの部分があります。
このチンク材は上に塗装が綺麗に乗るのがグッドですね。
既に予算オーバーなので手間のかかるマスキングは行っていません、そういう意味では丁寧な仕事とは言えないのかもしれません。でも出来るだけ安く上げ、かつ良いものを使う為にオーナーに目をつぶってもらった部分でもあります。もっともオーナー自身セルフメンテでマスキングなんてやってないんですけどね。
右のドアとの取り合い部分に残っているシリコンコーキング、これにも一応塗料は乗りますが、乾くとやがてペリペリと剥離してしまいます。
へアーラインクラックくらいの細いひび割れもこの塗膜でカバー出来るのがグッドですね。
塗装の目的は木肌を劣化の原因となる紫外線や、腐りの原因となる水からガードする事にあります。
無垢の木を使うログに「割れ」は不可欠、乾燥気候の北米や北欧ならいざしらず、ここは高温多湿の日本ですからやはり環境にあった塗装とメンテナンスが建物を長持ちさせる為には不可欠です。
一応メンテ1年前と塗装後の比較です。



最初に施主さんが塗った塗料はシッケンズ・セトール7でした。そしてシッケンズで部分的なメンテをやった後にアクリルペンキを塗ってしまったそうな・・・
で今回のメンテナンスにおいてはフィンランドのティックリラの塗料を使う事になりました。

最初はもっと安価で入手の易いものを塗る予定だったのですが、ネタは高い安いはあっても塗る手間賃はほとんど変わりません。(実際には1工程増えるのでそれなりにコスト増なのですが・・・)それに「色と耐久性」という課題において安価な塗料に「綺麗で明るい色」というのは皆無に近いですね。
現状濃茶のログウォールですがティックリラを使えばこれを真っ白にでも真っ青や真っ赤にでも出来てしまいます、そして選んだ色は「明るい茶色」です。
ログのメンテナンス塗装においては新築時が一番明るくて、時を重ねるごとに色を深くしていく傾向が多いかと思います。この建物も当初は更に濃い色にする予定でした。しかし塗料から揮発する臭いに奥様が難色を示され、結果追加料金ですがこの塗装になりました。
当初のネタに比べて塗料代で数倍近のコスト増なのですが、トータルでは追加ン万円ですからよい判断をしていただいたと思っています。
こちらとしても最初の油性塗料を塗るのは汚れと臭いから覚悟が必要でしたので・・・
ティックリラを使うのであればそれなりにちゃんと使いたいものです。
まず最初に無垢の木肌にベース剤を塗布します。ティックリラベースというこの製品は防腐防カビ剤です、そして塗料を吸込む木肌に塗ることで塗料の吸い込みを抑える働きもあります。
このベースは無垢木肌の時だけしか使えない(塗装面に使っても浸透しないので意味が無い)ので剥離作業をやった今だけしか施工できません。新築の際にも最初の塗装時にのみ施工しますが「これを塗っておくのと塗らないのとでは後で大違い」なのです。
で下塗りみたいなものなので助っ人さんにベタベタとタップリ塗ってもらいます。
剥離してからずっと晴天続きでログ表面も十分に乾いており理想的な工程です。
これを塗ってしまえば雨が降ってもカビが出たりすることはもうありません。
ベースを乾かして本ネタを塗ります。
ティックリラのヴィンハ・オパークというこの製品、水性塗料で塗膜形成タイプです。
オスモのカントリーカラーに似ていますが向うは油性塗料、ちなみに水性油性とは塗料の顔料成分を油で溶いてあるのか水で溶いてあるのかの違いですから「水性だと雨が降れば塗装が流れてしまう・・・」なんてことはアルワケない。水も油も塗布後に乾いて無くなってしまい、木には顔料成分が残される訳です。
水性だと道具の洗浄も水洗いでOKだし、何と言っても油性溶剤のあの鼻につく独特の臭いもありません。実は施工する私たちも楽なのです。
そして最大のメリットは、塗幕形成タイプなのでヌリムラが出にくく仕上がりが綺麗なのです。
この塗装を二度塗り、ベースと合わせて3度塗って仕上がりです。

一度塗りでも画像では塗装部分がクッキリですね、゛も近くで見ると一度はやはり薄いです。
午前中は日差しの強い東面を避けて日影の南面を、午後から日陰になった東面をと日影を求めての作業です。

一発目が半分位まで進んだ東面、背後は海です。海風は心地よいのですが・・・日射が・・・

南面はニ発目も終わって完成、あのボッコリと腐って埋めたログのところも綺麗に何事もなかったかのように仕上がってます。
西面は何もやっていません、こちらはアクリルペンキも塗られていないし、デッキから低い脚立で容易にメンテできるのとほとんど傷んでないのでオーナーさんのセルフメンテです。
色の違いがクッキリとして・・・まぁ次期メンテで同じ色を塗ってもらえれば・・です。

塗装面のアップです。
真中少し上にチンキングしたクラックの部分があります。
このチンク材は上に塗装が綺麗に乗るのがグッドですね。
既に予算オーバーなので手間のかかるマスキングは行っていません、そういう意味では丁寧な仕事とは言えないのかもしれません。でも出来るだけ安く上げ、かつ良いものを使う為にオーナーに目をつぶってもらった部分でもあります。もっともオーナー自身セルフメンテでマスキングなんてやってないんですけどね。
右のドアとの取り合い部分に残っているシリコンコーキング、これにも一応塗料は乗りますが、乾くとやがてペリペリと剥離してしまいます。
へアーラインクラックくらいの細いひび割れもこの塗膜でカバー出来るのがグッドですね。
塗装の目的は木肌を劣化の原因となる紫外線や、腐りの原因となる水からガードする事にあります。
無垢の木を使うログに「割れ」は不可欠、乾燥気候の北米や北欧ならいざしらず、ここは高温多湿の日本ですからやはり環境にあった塗装とメンテナンスが建物を長持ちさせる為には不可欠です。
一応メンテ1年前と塗装後の比較です。


2008年07月22日
埋めましょう
ダメな塗装を削った後はクラックを埋めましょう。
ペンキを剥離すると下からクラックが出てきました。
クラックはシリコンコーキングされてからシーラーを塗布、そしてペンキを塗ってあったのですね。大変な手間隙を掛けられていた訳ですが、これらが全て「裏目」に出ていたと分かった施主様は「俺達何やってたんだろう」と奥様と消沈されていました。

一枚目の画像 シリコンコーキングは最初はいいものの、硬化して月日が経つとログの乾燥収縮の動きについていけず接着面が剥離してしまいます。ですから窓周りの防水とか何度もシリコンで防水しても水が入ってきてしまうのはこの為です。
クラックの場合、剥離した隙間から水が入り抜けないし乾燥しづらいのでどんどんと腐りの原因となってしまいます。
一部腐朽の激しい場所もありました。本当は腐朽部はガッツリ取り除いたほうが良いのですが(腐朽菌が入っている為)今回はそこのでの予算が無いので現状でメンテします。

まずは古いシリコンコーキングを除去、これは厄介でカッターナイフで切って取り除くしかありません。細いところまで全部は無理なので除去できるところのみチマチマと取り除きます。

シリコンを取り除くと大きなクラックが現れます。
バックアップ材もナシで単にシリコンぶち込んだだけのメンテナンス跡が生々しいですね。
木に付着したシリコンも出来るだけ剥がしておきます。

クラックの掃除か済んだら新しくチンキングしていきます。
割れ目にチンク材を充填していく訳ですがチンク材ってなーに?
チンク材は木専用品を使います、ホームセンターなどでは売られていません。
ウチが使用しているのはアメリカのサシュコ社の製品、今回はビッグストレッチという製品を使います。これはオガクズを木工ボンドで溶いたような奴ですが、乾くとゴム化してログの乾燥収縮に合わせて伸び縮みするのです。

まずは割れ目にバックアップ材を詰めていきます、こうしないとチンク材が幾らあっても足りないですからね。バックアップ材は発泡スチロールの紐を何種類課の太さで使ってます。
大きな割れ目にはバックアップ材をタッカーで留めたりする事も。
バックアップ材を付けたらコーキングガンを使ってチンク剤を塗布していきます。
チンク剤はシリコンと違って水性です、指についても簡単に落ちます。隙間無く充填するのにヘラとか使いますが結局指で形成していくのが最も早かったり・・・・

ビッグストレッチは新しい塗装が上に乗るので多少はみ出したりとか余り気にせず、とにかくタップリと塗りたいものです。ノーマルサイズのカートリッジだとあっちゅーまにカラになってしまいます。やはりハンドカットだと29ozのデカカートリッジが良いのかも。
カラーはサンタフェトレイルという茶色らしい茶色です。他にグレーとか焦げちゃとかあります。

最後に濡れ雑巾で表面を均したりすると良いらしいですが、今回はこのまま乾燥させます。

でこの作業をやっているのは比較的高所、南側の壁の上から2段目のログでした。
足場を組まないとアプローチできない壁ですから結構作業は大変でした。
ペンキを剥離すると下からクラックが出てきました。
クラックはシリコンコーキングされてからシーラーを塗布、そしてペンキを塗ってあったのですね。大変な手間隙を掛けられていた訳ですが、これらが全て「裏目」に出ていたと分かった施主様は「俺達何やってたんだろう」と奥様と消沈されていました。

一枚目の画像 シリコンコーキングは最初はいいものの、硬化して月日が経つとログの乾燥収縮の動きについていけず接着面が剥離してしまいます。ですから窓周りの防水とか何度もシリコンで防水しても水が入ってきてしまうのはこの為です。
クラックの場合、剥離した隙間から水が入り抜けないし乾燥しづらいのでどんどんと腐りの原因となってしまいます。
一部腐朽の激しい場所もありました。本当は腐朽部はガッツリ取り除いたほうが良いのですが(腐朽菌が入っている為)今回はそこのでの予算が無いので現状でメンテします。

まずは古いシリコンコーキングを除去、これは厄介でカッターナイフで切って取り除くしかありません。細いところまで全部は無理なので除去できるところのみチマチマと取り除きます。

シリコンを取り除くと大きなクラックが現れます。
バックアップ材もナシで単にシリコンぶち込んだだけのメンテナンス跡が生々しいですね。
木に付着したシリコンも出来るだけ剥がしておきます。

クラックの掃除か済んだら新しくチンキングしていきます。
割れ目にチンク材を充填していく訳ですがチンク材ってなーに?
チンク材は木専用品を使います、ホームセンターなどでは売られていません。
ウチが使用しているのはアメリカのサシュコ社の製品、今回はビッグストレッチという製品を使います。これはオガクズを木工ボンドで溶いたような奴ですが、乾くとゴム化してログの乾燥収縮に合わせて伸び縮みするのです。

まずは割れ目にバックアップ材を詰めていきます、こうしないとチンク材が幾らあっても足りないですからね。バックアップ材は発泡スチロールの紐を何種類課の太さで使ってます。
大きな割れ目にはバックアップ材をタッカーで留めたりする事も。
バックアップ材を付けたらコーキングガンを使ってチンク剤を塗布していきます。
チンク剤はシリコンと違って水性です、指についても簡単に落ちます。隙間無く充填するのにヘラとか使いますが結局指で形成していくのが最も早かったり・・・・

ビッグストレッチは新しい塗装が上に乗るので多少はみ出したりとか余り気にせず、とにかくタップリと塗りたいものです。ノーマルサイズのカートリッジだとあっちゅーまにカラになってしまいます。やはりハンドカットだと29ozのデカカートリッジが良いのかも。
カラーはサンタフェトレイルという茶色らしい茶色です。他にグレーとか焦げちゃとかあります。

最後に濡れ雑巾で表面を均したりすると良いらしいですが、今回はこのまま乾燥させます。

でこの作業をやっているのは比較的高所、南側の壁の上から2段目のログでした。
足場を組まないとアプローチできない壁ですから結構作業は大変でした。
2008年07月17日
削りましょう
某所で始まったハンドカットログハウスのメンテナンスです。
実はこの物件、今までも少しメンテ修理させていただいていたし、そもそも私は建築中も見に行った事があって古くから知っていたりします。
ログハウスはメンテナンスが大変と言われますが、メンテナンスもいろいろあって難しいのから簡単なの迄、そもそも作り方や仕様でもそのメンテにかかる手間隙は雲泥の差となります。
さてさてこのログハウス、ビルダーがチェンソーで刻んで手作りするハンドカットタイプです。
メンテナンスとしては手強い相手、しかもウチが建てた物件でもないし、過去のメンテナンスもオーナー任せで頼りない限りでした。
そもそもオーナーがビルダー(遠く)のアドバイスで2面にアクリルペンキ(普通私たちがペンキと呼んでいる奴)を塗ってしまったのが今回のコトの発端
ペンキは表面に分厚い塗膜を形成し、木が吸湿したり放出したりするのを妨げてしまいます。
寝ている人の顔に濡れ雑巾・・・とまでは言い過ぎですが、それ位木にダメージを与えてしまいます。
防水も最初の頃はいいけど木の収縮でやがては剥離、そこから雨水が侵入するとなお酷い事に・・・

この建物もそうやって傷み始めています。傷み始めたのが分かってからでは遅すぎるのですが、一昨年に二階のベランダの柱の一本を交換する工事とかやらせていただいております。
その際に東側(海側)のシルログの腐食について相談がありました。
傷みを止めるべく、かつ低予算と相反する条件でのメンテナンス
最初はオーナー自らペンキの剥離作業をやっていたがあえなくギブアップ
そりゃそうだ、高所作業+道具の振動と頭からオガクズを浴びて耳も鼻もオガクズだらけ+この暑さ
でこっちにお鉢が廻ってきたという訳です。

とりあえず塗られたペンキを全て剥離して再塗装、そして傷みのケア
+ストーブと煙突掃除まで依頼されてしまいました。

朝から晩までベビーサンダーでひたすらログを削ること5日、途中単管パイプで足場を組み(予算節約で足場屋にも頼めず・・)頭から茶色になりながら剥離作業は完了。

ペンキを剥離した場所とそうでない場所、クッキリと違いますね。

ログを削るのはベビーサンダーにこの木工サンダーバッドを取り付けてゴリゴリ削っていきます。
半日もやっていればすぐに目詰まりしたりヤスリがボロボロになるので使い捨て感覚で使います。

随分と綺麗になりました。
剥離した部分と未工事部分がクッキリと分かれますね。
実はこの物件、今までも少しメンテ修理させていただいていたし、そもそも私は建築中も見に行った事があって古くから知っていたりします。
ログハウスはメンテナンスが大変と言われますが、メンテナンスもいろいろあって難しいのから簡単なの迄、そもそも作り方や仕様でもそのメンテにかかる手間隙は雲泥の差となります。
さてさてこのログハウス、ビルダーがチェンソーで刻んで手作りするハンドカットタイプです。
メンテナンスとしては手強い相手、しかもウチが建てた物件でもないし、過去のメンテナンスもオーナー任せで頼りない限りでした。
そもそもオーナーがビルダー(遠く)のアドバイスで2面にアクリルペンキ(普通私たちがペンキと呼んでいる奴)を塗ってしまったのが今回のコトの発端
ペンキは表面に分厚い塗膜を形成し、木が吸湿したり放出したりするのを妨げてしまいます。
寝ている人の顔に濡れ雑巾・・・とまでは言い過ぎですが、それ位木にダメージを与えてしまいます。
防水も最初の頃はいいけど木の収縮でやがては剥離、そこから雨水が侵入するとなお酷い事に・・・

この建物もそうやって傷み始めています。傷み始めたのが分かってからでは遅すぎるのですが、一昨年に二階のベランダの柱の一本を交換する工事とかやらせていただいております。
その際に東側(海側)のシルログの腐食について相談がありました。
傷みを止めるべく、かつ低予算と相反する条件でのメンテナンス
最初はオーナー自らペンキの剥離作業をやっていたがあえなくギブアップ
そりゃそうだ、高所作業+道具の振動と頭からオガクズを浴びて耳も鼻もオガクズだらけ+この暑さ
でこっちにお鉢が廻ってきたという訳です。

とりあえず塗られたペンキを全て剥離して再塗装、そして傷みのケア
+ストーブと煙突掃除まで依頼されてしまいました。

朝から晩までベビーサンダーでひたすらログを削ること5日、途中単管パイプで足場を組み(予算節約で足場屋にも頼めず・・)頭から茶色になりながら剥離作業は完了。

ペンキを剥離した場所とそうでない場所、クッキリと違いますね。

ログを削るのはベビーサンダーにこの木工サンダーバッドを取り付けてゴリゴリ削っていきます。
半日もやっていればすぐに目詰まりしたりヤスリがボロボロになるので使い捨て感覚で使います。

随分と綺麗になりました。
剥離した部分と未工事部分がクッキリと分かれますね。