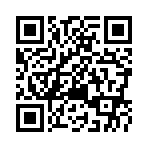2009年04月20日
ウッドデッキ作ってます



弊社ではログハウスの設計施工キット販売などを行なっています、その傍ら最近では薪ストーブ屋さんと化しておるのですが、ウットデッキの製作なんぞもやっております。
まぁログ新築の際には、建物と別に広いウッドデッキを併設することも多いのです。

こんなのとか

こんなのとか

こんなのとか・・・
まぁいろいろ作ってきました。
ですから別にログに限った話ではなく、ウッドデッキだけってのも当然作れる訳でして・・
それに気付いたのはお隣からデッキが欲しいと相談されたからでした。
隣のよしみで余材引っ張り出して作ったウッドデッキがコレです。

次男がアレルギー体質で犬の毛に反応する為、室内犬だったミニチュアダックスを外で飼わざるを得なくなったんだが、土の上では可哀想だし汚くなるし・・でデッキで飼うと。
予算が無いからあり合わせの材料で安く作ってくれと・・・
逃亡防止にフェンスを回すのですが、隣が持っていたラティスフェンスを使いゲートも付けてくれと・・
で重たいデッキになりました。
そのデッキを見たさらにお隣(家主の親族)からウチにも作って欲しいと頼まれ、余材ギリギリで作ったのがこのデッキ

塗装は余ってたネタ(一応高級な木専用塗料)提供したらオーナーご自身でペタペタ塗りました。だから緑と白のツートンカラーです。
最初に3枚の画像にあるデッキは約4mx2.5mで10平米
材料はフィンランドパイン厚さ20ミリの板です。
これは上の2つのデッキを見た地区の方から依頼を受けて、ちゃんとお客様仕様で作ったものです。
手摺もありがちなXのバッテン手摺ではなく、少し格好の良いデザインにしています。
家の引き戸を開けて、少ない段差で出られるようにしています。
ここでフトンを干したりお昼寝したりするそうです。
防虫防腐剤塗った上に、オスモのカントリーカラーっぽい仕上がりになるフィランド・ティックリラ社の塗料を二度塗りしてあります。
このサイズで塗装込み工事価格20万円ってとこです。無塗装渡しなら15万円ですね。
パインは大分では入手が易しくないので、檜に置き換えてこんなもんでしょうか?
杉だともっと安く提供できます。
まぁ自作しても難易度はそれほど難しいものではありません。
ポカポカ陽気の日にはウッドデッキでのんびりするのってとっても気持ちがいいですよ。
2009年04月19日
照明いろいろ
照明器具は家をデザインするにあたり重要なアイテムです。
照明デザインによって、室内空間はモダンにもカントリーにもサイケにでも出来ます。
一時、大正モダンっぽいのも流行りましたね。
新築の場合、照明はどうにでも出来なくてはならないポイント、もし制約を課されるようだと要注意です。
照明プランに当っては、専門用語?のオンパレードで目が白黒してしまいそうです。
簡単にその分類を説明します。
まず器具はタイプによって分けられます。

「ペンダント」
文字通りペンダントのようにチェーンやコードで「吊り下げ」て使う照明器具です。
吊り下げるので空間を占有するので使う部屋や照らす目的など熟考が求められます。
でもダイニングテーブルは手許を明るくする事が求められるのでペンダントタイプの照明が用いられることが多いですね。
電球や蛍光電球、ハロゲンランプなどのタイプがあります。
1つのものや3連・5連といった集合タイプなど様々です。
画像のものはルイス・ポールセンの傑作PHライト、PH-5です。

「シーリング」と「ブラケット」
天井に器具を直付けするタイプをシーリングライトと呼びます。
壁に直付けするタイプはブラケットライトと呼びます。
建売や賃貸ではシーリング1点照明というのが多いですね。
シーリング紐スイッチとかありますが、私はまず採用しません。照明は部屋の入り口のスイッチでオンオフ、最近はリモコンタイプもあります。
シーリングとブラケットは1つの器具で両方使えるタイプもあるので呼び方に注意が必要です。
シーリングはODELIC社製のアメリカンクラシックタイプ、ブラケットはマックスレイ社のモダンタイプ
これ棒状の電球なんです。

「ダウンライト」と「レールシステム」
ダウンライトは天井などに埋め込んであるタイプの照明器具です。
店舗などで多用されてきましたが、最近は住宅にも使われています。
ダウンライトを巧く使うことで間接照明や調光システムにも使えます。
ただダウンライトは熱を持つので仕様をよく検討する必要があります。
レールシステムとは、店舗用に開発された器具の移動が容易く出来る照明システムです。
レールの溝に器具を取り付けるので、位置も個数も自由に出来ます。
レールの器具は規格なので他の場所の器具と交換も出来ます。デザインに飽きたら交換も容易です。
このライトはDAIKO社製、円筒ガラスセードに蛍光電球
レールを使うメリットは
採用した照明が暗すぎた・・レールなら器具を容易に追加できる。減らすことも出来る。
3つの照明を付けるに、ブラケットなら配線工事が3個所分必要、レールは1箇所だけで済む。
レールのデメリット
レール1本にスイッチ1つなので個別の照明コントロールはオプションのコントローラが必要。

最近流行っているモダン系のライティング
レールシステムにダイクロハロゲンランプのスポットライト。ODELIC社です。

屋外の防滴ブラケットライト
玄関など屋外で使うブラケットライト、屋外なので防水性能が要求されます。
画像の機器はマックスレイ社製
玄関照明は個性あるものを選びたいですね。

屋外のスポットライト、こちらも防滴仕様です。
これはODELICの屋外ライト
照明器具はタイプとデザイン、そしてランプの種類です。
一般的な「電球」と呼ばれているのはE26ソケットタイプ
ミニ電球タイプはE17ソケットタイプ
蛍光灯はFLと呼びます。
最近はLEDによるランプも登場していますが、器具のソケットとランプのソケットは同じである必要があります。
ソケットもある程度揃えておくことで、予備のランプの使いまわしや調達の容易さも検討が必要です。
ダイクロハロゲンなどはE17ソケットの電球の仲間ですが、蛍光電球に比べ消費電力が大きく、これをレールで3連で使うとハロゲン50wx3で150wの電力、方や蛍光電球だと19wx3で57wです。
ライトの使用頻度も計算に入れなくてはなりませんね。
そして最近のランプには電球色、昼間色、白色など色目の種類もあります。
たくさんありすぎで混乱してしまいますね。
今お住まいのお部屋の照明を変えるだけでも、部屋の雰囲気が変わり、明るさが変わり、ひいては人生も変わるかも・・・ですよ。
毎夜使うものだけに、こういう所はこだわっていただきたいものです。
照明デザインによって、室内空間はモダンにもカントリーにもサイケにでも出来ます。
一時、大正モダンっぽいのも流行りましたね。
新築の場合、照明はどうにでも出来なくてはならないポイント、もし制約を課されるようだと要注意です。
照明プランに当っては、専門用語?のオンパレードで目が白黒してしまいそうです。
簡単にその分類を説明します。
まず器具はタイプによって分けられます。

「ペンダント」
文字通りペンダントのようにチェーンやコードで「吊り下げ」て使う照明器具です。
吊り下げるので空間を占有するので使う部屋や照らす目的など熟考が求められます。
でもダイニングテーブルは手許を明るくする事が求められるのでペンダントタイプの照明が用いられることが多いですね。
電球や蛍光電球、ハロゲンランプなどのタイプがあります。
1つのものや3連・5連といった集合タイプなど様々です。
画像のものはルイス・ポールセンの傑作PHライト、PH-5です。

「シーリング」と「ブラケット」
天井に器具を直付けするタイプをシーリングライトと呼びます。
壁に直付けするタイプはブラケットライトと呼びます。
建売や賃貸ではシーリング1点照明というのが多いですね。
シーリング紐スイッチとかありますが、私はまず採用しません。照明は部屋の入り口のスイッチでオンオフ、最近はリモコンタイプもあります。
シーリングとブラケットは1つの器具で両方使えるタイプもあるので呼び方に注意が必要です。
シーリングはODELIC社製のアメリカンクラシックタイプ、ブラケットはマックスレイ社のモダンタイプ
これ棒状の電球なんです。

「ダウンライト」と「レールシステム」
ダウンライトは天井などに埋め込んであるタイプの照明器具です。
店舗などで多用されてきましたが、最近は住宅にも使われています。
ダウンライトを巧く使うことで間接照明や調光システムにも使えます。
ただダウンライトは熱を持つので仕様をよく検討する必要があります。
レールシステムとは、店舗用に開発された器具の移動が容易く出来る照明システムです。
レールの溝に器具を取り付けるので、位置も個数も自由に出来ます。
レールの器具は規格なので他の場所の器具と交換も出来ます。デザインに飽きたら交換も容易です。
このライトはDAIKO社製、円筒ガラスセードに蛍光電球
レールを使うメリットは
採用した照明が暗すぎた・・レールなら器具を容易に追加できる。減らすことも出来る。
3つの照明を付けるに、ブラケットなら配線工事が3個所分必要、レールは1箇所だけで済む。
レールのデメリット
レール1本にスイッチ1つなので個別の照明コントロールはオプションのコントローラが必要。

最近流行っているモダン系のライティング
レールシステムにダイクロハロゲンランプのスポットライト。ODELIC社です。

屋外の防滴ブラケットライト
玄関など屋外で使うブラケットライト、屋外なので防水性能が要求されます。
画像の機器はマックスレイ社製
玄関照明は個性あるものを選びたいですね。

屋外のスポットライト、こちらも防滴仕様です。
これはODELICの屋外ライト
照明器具はタイプとデザイン、そしてランプの種類です。
一般的な「電球」と呼ばれているのはE26ソケットタイプ
ミニ電球タイプはE17ソケットタイプ
蛍光灯はFLと呼びます。
最近はLEDによるランプも登場していますが、器具のソケットとランプのソケットは同じである必要があります。
ソケットもある程度揃えておくことで、予備のランプの使いまわしや調達の容易さも検討が必要です。
ダイクロハロゲンなどはE17ソケットの電球の仲間ですが、蛍光電球に比べ消費電力が大きく、これをレールで3連で使うとハロゲン50wx3で150wの電力、方や蛍光電球だと19wx3で57wです。
ライトの使用頻度も計算に入れなくてはなりませんね。
そして最近のランプには電球色、昼間色、白色など色目の種類もあります。
たくさんありすぎで混乱してしまいますね。
今お住まいのお部屋の照明を変えるだけでも、部屋の雰囲気が変わり、明るさが変わり、ひいては人生も変わるかも・・・ですよ。
毎夜使うものだけに、こういう所はこだわっていただきたいものです。
2009年04月16日
熱源はどうする?
キッチンや給湯などの熱源についてです。
最近はオール電化住宅が流行っています、猫も杓子もエコキュートエコキュートです。
オール電化とは
キッチンの熱源はIHヒーターやラジエントなどの電熱ヒーター
給湯機器は電気温水器やエコキュートなど、電気系給湯器
を組み合わせたモデルです。
キッチンがガスコンロ
または
給湯器が石油又はガスボイラー
などの組み合わせはオール電化ではありません。
例外的にキッチンにはIHヒーターとガスレンジのダブル熱源などがあります。
オール電化では、消費電力量が大きいので専用の契約プランが用意されています。
各電力会社毎に呼び名は少し違いますが、大抵一日を4分割して電気料金を割り引きます。
でも不思議な事に日中は割高となります、なぜ割高な料金に設定されなくてはならないのか???
ですが、自分たちのライフスタイルに合わせて適当なものを選んで頂きたいものです。
オール電化のメリットとして
ガスは固定料金があるしLPガスはエネルギーコストは相対的に高いです。
灯油はコストは安いのですが、原油高などでは高くなったりします。
変動幅が電気よりは大きいですね
そして石油やLPGは補給が必要です、都市ガスは不要ですね。
電気は不可欠なのでガスをなくす事で家庭のエネルギーコストを相対的に引き下げる事ができるようです。
オール電化のデメリットとして
停電したら何も使えなくなります。まぁガスボイラなども電気が無ければ動かないので同条件ですが・・
日中の電気代は割高なので、日中にエアコンを使ったりすると電気代はバーンと・・・
とにかく日中は外出して何も使っていないなどが理想なので時間の制約を感じる
これは洗濯機や食器洗浄器なども一番電気代の安い深夜帯に行う(タイマー制御)など時間に振り回される生活になりがち。
Noオール電化のメリット
ガスコンロは好みの問題ですが火力が強いのと鍋が振れる・・・
Noオール電化のデメリット
LPGや石油は補充が必要
ガスボイラや石油ボイラは価格は安いが寿命は電気温水器より短い傾向
電気代のほかにガスは基本料金+使用料などコストは高くつきやすい
まぁ何にしてもその方々のライフスタイルでコストは増減するのでメリットデメリットをよく考えて選んで欲しいですね。
夫婦共働きで昼間は誰も家に居ないという方にはオール電化は良いのかもしれません。
でも爺様婆様が居れば、夏の昼間にエアコンやIHを使うと結構な事になります。
ちなみに家庭で使われる電気は、冷蔵庫、エアコンがその大半と言われています。
以外にも電気ポットと炊飯器の保温などは電気を食います。
我が家はNon電化です。
キッチンはIHヒーターです。
給湯は石油ボイラーです。
これに太陽光温水器の温水もあります。
ガスを使っていないのでガス代はありません。
石油(灯油)は使った分だけです、配達も頼めますがタンクで買って来ます。
太陽光温水器の温水があるので夏場はほとんどボイラー炊きません。
冬は18L/月程度灯油を消費します。
電気代はIHのせいで月1万円程度、契約60アンペア
水道代は安いので
電気ガス水道で15000円/月程度です。夏はもっと安いです。
エコキュートは確かにランニングコストは安いです、ただイニシャルコストは高いので回収までも結構かかります。個人的には単純な電気温水器の深夜電力で十分ではないかと思います。
IHヒーターもイニシャルコストは高めですが、グレードの高いガスコンロとの価格差は縮まっています。
ガス代は都市ガス以外はとにかく高いので、ガスレスにするメリットは大きいです。
エアコンは標高の高いところに住んでいますので、夏の夜に寝室で少し使う程度です。
年間で100時間程度でしょうか?
ライフスタイルをよく考えてストレスの無いライフスタイルでそれぞれに合ったものを選択されることをお勧めします。
最近はオール電化住宅が流行っています、猫も杓子もエコキュートエコキュートです。
オール電化とは
キッチンの熱源はIHヒーターやラジエントなどの電熱ヒーター
給湯機器は電気温水器やエコキュートなど、電気系給湯器
を組み合わせたモデルです。
キッチンがガスコンロ
または
給湯器が石油又はガスボイラー
などの組み合わせはオール電化ではありません。
例外的にキッチンにはIHヒーターとガスレンジのダブル熱源などがあります。
オール電化では、消費電力量が大きいので専用の契約プランが用意されています。
各電力会社毎に呼び名は少し違いますが、大抵一日を4分割して電気料金を割り引きます。
でも不思議な事に日中は割高となります、なぜ割高な料金に設定されなくてはならないのか???
ですが、自分たちのライフスタイルに合わせて適当なものを選んで頂きたいものです。
オール電化のメリットとして
ガスは固定料金があるしLPガスはエネルギーコストは相対的に高いです。
灯油はコストは安いのですが、原油高などでは高くなったりします。
変動幅が電気よりは大きいですね
そして石油やLPGは補給が必要です、都市ガスは不要ですね。
電気は不可欠なのでガスをなくす事で家庭のエネルギーコストを相対的に引き下げる事ができるようです。
オール電化のデメリットとして
停電したら何も使えなくなります。まぁガスボイラなども電気が無ければ動かないので同条件ですが・・
日中の電気代は割高なので、日中にエアコンを使ったりすると電気代はバーンと・・・
とにかく日中は外出して何も使っていないなどが理想なので時間の制約を感じる
これは洗濯機や食器洗浄器なども一番電気代の安い深夜帯に行う(タイマー制御)など時間に振り回される生活になりがち。
Noオール電化のメリット
ガスコンロは好みの問題ですが火力が強いのと鍋が振れる・・・
Noオール電化のデメリット
LPGや石油は補充が必要
ガスボイラや石油ボイラは価格は安いが寿命は電気温水器より短い傾向
電気代のほかにガスは基本料金+使用料などコストは高くつきやすい
まぁ何にしてもその方々のライフスタイルでコストは増減するのでメリットデメリットをよく考えて選んで欲しいですね。
夫婦共働きで昼間は誰も家に居ないという方にはオール電化は良いのかもしれません。
でも爺様婆様が居れば、夏の昼間にエアコンやIHを使うと結構な事になります。
ちなみに家庭で使われる電気は、冷蔵庫、エアコンがその大半と言われています。
以外にも電気ポットと炊飯器の保温などは電気を食います。
我が家はNon電化です。
キッチンはIHヒーターです。
給湯は石油ボイラーです。
これに太陽光温水器の温水もあります。
ガスを使っていないのでガス代はありません。
石油(灯油)は使った分だけです、配達も頼めますがタンクで買って来ます。
太陽光温水器の温水があるので夏場はほとんどボイラー炊きません。
冬は18L/月程度灯油を消費します。
電気代はIHのせいで月1万円程度、契約60アンペア
水道代は安いので
電気ガス水道で15000円/月程度です。夏はもっと安いです。
エコキュートは確かにランニングコストは安いです、ただイニシャルコストは高いので回収までも結構かかります。個人的には単純な電気温水器の深夜電力で十分ではないかと思います。
IHヒーターもイニシャルコストは高めですが、グレードの高いガスコンロとの価格差は縮まっています。
ガス代は都市ガス以外はとにかく高いので、ガスレスにするメリットは大きいです。
エアコンは標高の高いところに住んでいますので、夏の夜に寝室で少し使う程度です。
年間で100時間程度でしょうか?
ライフスタイルをよく考えてストレスの無いライフスタイルでそれぞれに合ったものを選択されることをお勧めします。
2009年04月14日
土地の話
家を建てるにあたり不可欠なのは「敷地」です。
では土地さえあれば、どこでも何でも建てていいのか?
と言えば、そうは問屋が卸しません。
土地には行政によって、勝手に一方的に制限がつけられています。
これは国土法や建築基準法や都市計画法、消防法や災害条例など国や地方の条例、更には住宅地や別荘地では近隣周辺での「自主規制」まで様々な法律が入り混じっています。
その中でも一番分かりやすいのは都市計画法ですね。
これは各自治体において大きく市街化地域(大いに街にするエリア)と市街化調整区域(田畑メインで街にしたくないエリア)とその他(未線引き地域)に三分し、さらに市街化地域の中で工業地域とか商業地域、第一種住宅地域とか第一種高層住宅地域とか用途指定別に分けて定めています。
これは住宅地の真中にいきなり工場が出来たり、高層マンションが建ったり、学校の隣に大型スーパーが出来たりなどの乱開発を防ぐ目的で定められています。
これらは不動産売買においては説明義務のある項目ですが、家を建てるつもりで土地を買う場合にはチェックは必要です。第一種中高層に指定されている土地であれば、隣に高層ビルが建てられても文句言えない訳です。
自分が今住んでいる場所がどういう指定を受けているのか、役所の都市計画化で聞けば教えてくれます。
実際には人が住んでいる上に網をかけているので、本来住宅が建てられない地域でありながら既存住宅が存在するなどがありますが、それらは法律が後追いなので割愛します。
そして基本的に市街化調整区域では「家を建てることはできません」
市街化することを抑制する地域です。
まぁ例外はあります、既存宅地とか既存不適格とかのキーワードで検索してみてください。
この辺りはとてもややこしいので割愛
そして家が建てられる土地は、地目は「宅地」である必要があり「農地」に家を建てることは出来ません。農地に家を建てる場合、各自治体に設けてある農業委員会に「農地転用」の申請を出し、農地を他の目的に変更する為の許可を得る必要があるのです。
つまり農地に家を建てると、登記地目が農地から宅地に変更になるのです。この地目変更の際に許可証が不可欠です。転用手続き無くして家を建ててしまうと「違法建築」となります。
農地に建てられる建物は、農業用の倉庫など一定の要件のものに制限されています。
これは農地法です。
家を建てられる地目として、宅地・原野・山林・雑種地などです。農地(田・畑)は転用必要、第一種農地(改良農地)は転用がとても難しいので注意が必要です。
これらは比較的たくさんの情報があり、ネットでも調べればややこしいですが大抵の事は分かります。
そして不動産屋が住宅地として販売している土地などは予めリサーチしてあることがほとんどです。
では問題になりやすいのは何か?
これは最初に書いた「その他の未線引き地域」です。
都市計画法は昭和51年かそこいらに全国の自治体に都市計画を定めるよう指示を出し、将来の町の姿を決めさせました。ここに道路を作るとか、こっちに工業団地を作るとか、駅前は再開発して住宅と商業ゾーンにするとか・・・これらをある程度「勝手に」作っているのです。
その中でも私が今住んでいるような「僻地」は利用価値もなくほったらかしにされています。
つまり必要な部分だけ囲って(線引きして)、あとは未線引きのままにしてあるのです。
未線引きなので市街化地域でもなく、市街化調整区域でもないので自由?
まぁ自由っちゃー自由なのですが、定めが無いから何をしてもいいのか?と言えばそれなりに大きな国土法などでカバーされている訳です。
田中角栄元首相は列島改造と叫び、日本にも別荘地など近代的な住環境整備が進められました。
その影で暗躍したのは原野商法と呼ばれた「価値の無い山奥の二束三文の原野を高値で売りつけた商売」が社会問題化します。
そして国は原野商法や乱開発を防ごうと市街化地域では500平米、それ以外でも1000平米とか3000平米(約1000坪)以上の土地の形状をいじくる場合には「開発行為申請」を出して許可を得るよう義務付けました。
田舎の広い土地を売買する場合、登記簿通りに丸々買えば問題は少ないのですが、広い土地を分割して小さくして買い、そこに家を建てようとすれば「開発申請」から求められる事があるので注意が必要です。
いざ家を建てるには「建築確認申請」の手続きを行ないます。
これは上で述べた用件をクリアしていることを証明し、法的に問題無いことをまさに「確認」する手続きです。ただ未線引き地域では確認してもらうにも、確認の根拠となる規制がない為確認のしようが無いですね、なので未線引き地域では確認不要で「工事届」を提出するだけでokという場合もあります。
ただこれも一定の大きさがあるので、城みたいなデカイ規制を超える大きさの家を建てる場合には他の手続きが必要になったりします。
ちなみに弊社の周辺は未線引き地域なので、普通の住宅程度の建物であれば工事届の提出のみで建てる事が出来ます。ただし、農地は転用手続きが必要です、原野はそのまま建てられます。
これらとは別に建築基準法では防火地域・準防火地域とかの火災予防上の制約もあります。消防法とはまた別ですよ。
そして防火の最も低い規制は建築法第22.23条指定地域です。
まぁ市街化地域は全域これに該当しますね。
敷地境界から一階部分で3m、二階部分で5m以上後退させれば良いのですが、そんなこと住宅地でやろうとしたらどんだけ広大な敷地が必要になるか・・・
その場合外壁は一定の耐火基準を満たす仕上げにする事でクリアできます。
皆さんの周りの住宅が、サイディングとかモルタル吹き付けの仕上げになっているのもばっかりなのはこういう背景があります。
そしてログハウスなど木を表に出す建物は「耐火基準を満たしていない」として制約されていました。
現在はログ壁自体の耐火性能が基準をクリアしている事を国が認めていますので、これらの仕上げや木板張りも耐火基準を満たす不燃加工された製品を用いることで可能となっています。
では土地さえあれば、どこでも何でも建てていいのか?
と言えば、そうは問屋が卸しません。
土地には行政によって、勝手に一方的に制限がつけられています。
これは国土法や建築基準法や都市計画法、消防法や災害条例など国や地方の条例、更には住宅地や別荘地では近隣周辺での「自主規制」まで様々な法律が入り混じっています。
その中でも一番分かりやすいのは都市計画法ですね。
これは各自治体において大きく市街化地域(大いに街にするエリア)と市街化調整区域(田畑メインで街にしたくないエリア)とその他(未線引き地域)に三分し、さらに市街化地域の中で工業地域とか商業地域、第一種住宅地域とか第一種高層住宅地域とか用途指定別に分けて定めています。
これは住宅地の真中にいきなり工場が出来たり、高層マンションが建ったり、学校の隣に大型スーパーが出来たりなどの乱開発を防ぐ目的で定められています。
これらは不動産売買においては説明義務のある項目ですが、家を建てるつもりで土地を買う場合にはチェックは必要です。第一種中高層に指定されている土地であれば、隣に高層ビルが建てられても文句言えない訳です。
自分が今住んでいる場所がどういう指定を受けているのか、役所の都市計画化で聞けば教えてくれます。
実際には人が住んでいる上に網をかけているので、本来住宅が建てられない地域でありながら既存住宅が存在するなどがありますが、それらは法律が後追いなので割愛します。
そして基本的に市街化調整区域では「家を建てることはできません」
市街化することを抑制する地域です。
まぁ例外はあります、既存宅地とか既存不適格とかのキーワードで検索してみてください。
この辺りはとてもややこしいので割愛
そして家が建てられる土地は、地目は「宅地」である必要があり「農地」に家を建てることは出来ません。農地に家を建てる場合、各自治体に設けてある農業委員会に「農地転用」の申請を出し、農地を他の目的に変更する為の許可を得る必要があるのです。
つまり農地に家を建てると、登記地目が農地から宅地に変更になるのです。この地目変更の際に許可証が不可欠です。転用手続き無くして家を建ててしまうと「違法建築」となります。
農地に建てられる建物は、農業用の倉庫など一定の要件のものに制限されています。
これは農地法です。
家を建てられる地目として、宅地・原野・山林・雑種地などです。農地(田・畑)は転用必要、第一種農地(改良農地)は転用がとても難しいので注意が必要です。
これらは比較的たくさんの情報があり、ネットでも調べればややこしいですが大抵の事は分かります。
そして不動産屋が住宅地として販売している土地などは予めリサーチしてあることがほとんどです。
では問題になりやすいのは何か?
これは最初に書いた「その他の未線引き地域」です。
都市計画法は昭和51年かそこいらに全国の自治体に都市計画を定めるよう指示を出し、将来の町の姿を決めさせました。ここに道路を作るとか、こっちに工業団地を作るとか、駅前は再開発して住宅と商業ゾーンにするとか・・・これらをある程度「勝手に」作っているのです。
その中でも私が今住んでいるような「僻地」は利用価値もなくほったらかしにされています。
つまり必要な部分だけ囲って(線引きして)、あとは未線引きのままにしてあるのです。
未線引きなので市街化地域でもなく、市街化調整区域でもないので自由?
まぁ自由っちゃー自由なのですが、定めが無いから何をしてもいいのか?と言えばそれなりに大きな国土法などでカバーされている訳です。
田中角栄元首相は列島改造と叫び、日本にも別荘地など近代的な住環境整備が進められました。
その影で暗躍したのは原野商法と呼ばれた「価値の無い山奥の二束三文の原野を高値で売りつけた商売」が社会問題化します。
そして国は原野商法や乱開発を防ごうと市街化地域では500平米、それ以外でも1000平米とか3000平米(約1000坪)以上の土地の形状をいじくる場合には「開発行為申請」を出して許可を得るよう義務付けました。
田舎の広い土地を売買する場合、登記簿通りに丸々買えば問題は少ないのですが、広い土地を分割して小さくして買い、そこに家を建てようとすれば「開発申請」から求められる事があるので注意が必要です。
いざ家を建てるには「建築確認申請」の手続きを行ないます。
これは上で述べた用件をクリアしていることを証明し、法的に問題無いことをまさに「確認」する手続きです。ただ未線引き地域では確認してもらうにも、確認の根拠となる規制がない為確認のしようが無いですね、なので未線引き地域では確認不要で「工事届」を提出するだけでokという場合もあります。
ただこれも一定の大きさがあるので、城みたいなデカイ規制を超える大きさの家を建てる場合には他の手続きが必要になったりします。
ちなみに弊社の周辺は未線引き地域なので、普通の住宅程度の建物であれば工事届の提出のみで建てる事が出来ます。ただし、農地は転用手続きが必要です、原野はそのまま建てられます。
これらとは別に建築基準法では防火地域・準防火地域とかの火災予防上の制約もあります。消防法とはまた別ですよ。
そして防火の最も低い規制は建築法第22.23条指定地域です。
まぁ市街化地域は全域これに該当しますね。
敷地境界から一階部分で3m、二階部分で5m以上後退させれば良いのですが、そんなこと住宅地でやろうとしたらどんだけ広大な敷地が必要になるか・・・
その場合外壁は一定の耐火基準を満たす仕上げにする事でクリアできます。
皆さんの周りの住宅が、サイディングとかモルタル吹き付けの仕上げになっているのもばっかりなのはこういう背景があります。
そしてログハウスなど木を表に出す建物は「耐火基準を満たしていない」として制約されていました。
現在はログ壁自体の耐火性能が基準をクリアしている事を国が認めていますので、これらの仕上げや木板張りも耐火基準を満たす不燃加工された製品を用いることで可能となっています。
2009年04月13日
富士ハウス倒産のニュース
報道に出ていた静岡の富士ハウス倒産の事例
中にはまだ家が着工前にも関わらず、代金の全額を支払っていた人も居たそうな・・・
倒産する方もする方ですが、払うほうも払うほうです。
無知としか言いようが無い、そもそも着工前に払っている事自体が有り得ない事だし、なんでまぁそんだけ払ってしまったのか。
普通、そのタイミングでそんだけの支払い要求する会社なんざ信用にも値せず、求められた時点でキャンセルものです。
我々ログ屋の世界でも似たような事はよくあります。
某社でも数社は倒産したり夜逃げしたりしています。
そして今、地元建築業界も「どこが倒産してもおかしくない」ほど冷え込んでいる訳でして・・・
明日は我が身かもしれません。
では、そういうリスクはどうやってヘッジすれば良いのでしょう?
答えは簡単です。
基本的に、家の工事代金などは「出来高払い」すれば良いのです。
工務店とか建築会社は、仕入れ代金は「後払い」(掛で仕入)なので工事の進行に合わせて支払いをしてあげればよい訳です。
究極は日払い・・・その日の工事分を支払う。
まぁ常識的には一週間単位でしょうね、一般的にはこれは契約時・着工時・上棟時・引渡し時の4回程度に分割する訳ですが、契約はあくまで業者と施主間の約束なので別に業者側の支払いを鵜呑みにする必要は無いわけです。5回とか8回とか、お互いに納得のいく支払い回数で分割すれば良いのです。
まぁローンで支払う場合は上棟して一時金融資実行時と、完成して残金融資実行時など施主の資金調達に合わせる事が多いですけどね。
自分の家を建てて貰う代金の支払いは、前払いする必要は特に無く、出来高払いでも問題ないという業者に依頼するのが一番です。それはその会社の経済基盤がしっかりしている事を意味しますから。
まだ形もないのに説明できない代金を前払いさせようとするのは、何かの返済資金に流用したいなど会社の資金繰り上の都合以外に理由がないと思います。
もちろん設計士への報酬だとか、申請費用だとか必要なものは支払う必要があると思いますが、それらに対する会社の利益を含めても金額はそんなに高額にならないです。
ちなみに弊社のログの場合、ログキットを海外から輸入したりしますので前払いは多くなります。
海外メーカーとの取引では前金が当たり前だからです。
ログメーカーの多くは、キット受注時に5/10、キットを輸出した段階で3/10、現場で引き渡して2/10を要求して来ます。ですから弊社もそれに併せたお支払いをお願いしています。
そして工事代金は、契約時1割、着工時3割、上棟時3割、完成時3割でお願いしています。
もちろん毎週の出来高払いでもOKです。
くれぐれもまだ何もやっていない段階で、高額な支払いをしてはダメです。
理由のない支払いを要求してくる会社は要注意なんです。
中にはまだ家が着工前にも関わらず、代金の全額を支払っていた人も居たそうな・・・
倒産する方もする方ですが、払うほうも払うほうです。
無知としか言いようが無い、そもそも着工前に払っている事自体が有り得ない事だし、なんでまぁそんだけ払ってしまったのか。
普通、そのタイミングでそんだけの支払い要求する会社なんざ信用にも値せず、求められた時点でキャンセルものです。
我々ログ屋の世界でも似たような事はよくあります。
某社でも数社は倒産したり夜逃げしたりしています。
そして今、地元建築業界も「どこが倒産してもおかしくない」ほど冷え込んでいる訳でして・・・
明日は我が身かもしれません。
では、そういうリスクはどうやってヘッジすれば良いのでしょう?
答えは簡単です。
基本的に、家の工事代金などは「出来高払い」すれば良いのです。
工務店とか建築会社は、仕入れ代金は「後払い」(掛で仕入)なので工事の進行に合わせて支払いをしてあげればよい訳です。
究極は日払い・・・その日の工事分を支払う。
まぁ常識的には一週間単位でしょうね、一般的にはこれは契約時・着工時・上棟時・引渡し時の4回程度に分割する訳ですが、契約はあくまで業者と施主間の約束なので別に業者側の支払いを鵜呑みにする必要は無いわけです。5回とか8回とか、お互いに納得のいく支払い回数で分割すれば良いのです。
まぁローンで支払う場合は上棟して一時金融資実行時と、完成して残金融資実行時など施主の資金調達に合わせる事が多いですけどね。
自分の家を建てて貰う代金の支払いは、前払いする必要は特に無く、出来高払いでも問題ないという業者に依頼するのが一番です。それはその会社の経済基盤がしっかりしている事を意味しますから。
まだ形もないのに説明できない代金を前払いさせようとするのは、何かの返済資金に流用したいなど会社の資金繰り上の都合以外に理由がないと思います。
もちろん設計士への報酬だとか、申請費用だとか必要なものは支払う必要があると思いますが、それらに対する会社の利益を含めても金額はそんなに高額にならないです。
ちなみに弊社のログの場合、ログキットを海外から輸入したりしますので前払いは多くなります。
海外メーカーとの取引では前金が当たり前だからです。
ログメーカーの多くは、キット受注時に5/10、キットを輸出した段階で3/10、現場で引き渡して2/10を要求して来ます。ですから弊社もそれに併せたお支払いをお願いしています。
そして工事代金は、契約時1割、着工時3割、上棟時3割、完成時3割でお願いしています。
もちろん毎週の出来高払いでもOKです。
くれぐれもまだ何もやっていない段階で、高額な支払いをしてはダメです。
理由のない支払いを要求してくる会社は要注意なんです。
2009年04月13日
住宅ローンはどこで借りるか
住宅ローンはどこで借りるか?
家を建てようとすると大きな問題です。
いきなり結論ですが・・・
「貸してくれるところから借りる」
です。

まぁ公務員さんとか、上場企業のような有名大企業にお勤めの方ならイザ知らず。
中小企業でかつ年収が400万にも満たないと、住宅ローンのハードルはとても高いです。
大分で有名なガメラ?の会社でさえ年収400以上の人なんて幹部クラス以上じゃないかと思います。
住宅ローンは「借りる」じゃないんです、「貸していただく」なのです。
これは銀行の窓口で苦渋をなめて初めて分かります。
「貸す」か「貸さない」かは相手が決める事なのです。
特に自営業者の方は、大金のローンを組むにあたり如何に銀行の真の姿が分かるというものです。
どこが金利が安いとか、手数料が・・という前に、そこが貸してくれるかどうかお伺いを立ててからの話ですね。
まぁ以前も最強の住宅ローンと書きましたが、ローンを借りるにあたり
銀行(銀行・信用組合・信用金庫ETC)
JAバンク(要JA組合員加入?)
労働金庫(ろうきん、基本的に公務員が使う、だからろうきんが出てくるところは大抵公務員、民間でろうきんを使っている人はめずらしい)
生命保険会社、一時やっていましたが今はやっているかどうか・・・
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)これは国です。
などが挙げられます。
最近ではソニー銀行とかもやってますね。
そして郵便局も民営化されたのでゆうちょでもいずれ住宅ローンを始めるでしょう。
で前の話ですが、住宅ローンは各金融機関ごとに様々な商品があり金利も様々です。
金利以外にも融資手数料や保証料、繰上げ返済手数料など諸費用なども差があります。
一番有利なところで借りたいのは誰しも一緒、でもね、そもそも「貸してくれなきゃ始まらない」のですよ。
ココで借りたいと思っても「貴方には貸せません」とか「貸せるのは幾らまでです」言われると正直凹みますよ。
ここで銀行は何を基準に融資の可否を諮るかと言えば、ズバリ
「返済能力」
これは年収の2.5-3倍と言われています。
年収400万で借りられるのは1200万円程度って事ですね。
もちろん頭金の有無はありますが、そもそも「頭金も貯金できない人に、何十年ものローンが返せる訳が無いでしょ?」というのが金融機関の考え方です。
ですから定期預金とか積み立て預金とかをやっている人は有利ですし、とにかく頭金があればあるほど融資の審査ハードルは低くなります。逆に頭金ゼロで融資なんて貸すほうもハイリスクなので金利も不利になるのは当たり前の事ですね。
そして融資審査のハードルが一番低いのは「住宅金融支援機構」です、現在は直接融資は行っておらず「フラット35」として各金融機関を通じて利用します。
田舎の山奥では土地の資産価値が低く、土地が担保としての役割を果たせないので銀行は融資に及び腰になります。その点フラット35では土地の担保価値は余り問われないのです。これは銀行が受けない融資の最後の受け皿的な意味合いがあるのです。
でもね、フラット35は金利が一定とは言っても、今の低金利時代、昨年の世界的金融不安からも当面市場金利が上がる事はないと言えます。
だって金利上げると借金漬けの日本の国が破綻してしまうからです。そんなことできる訳ない。
だからフラット35は銀行等のローン金利2%とかに敵わない・・・
まぁ何をどう判断するのかは各人次第ですけどね。
公務員さんなど金融会社から見た良いお客さんの場合、ローンは大抵のところから借りる事ができるでしょう。
ならばあちこち比較して選び放題ですね。
まぁ以前も書きました(あえてリンクは付けません)が、いずれはマイホームをと考えている方は、明日からでも住宅財形を始める事を強くお勧めしておきます。
家を建てようとすると大きな問題です。
いきなり結論ですが・・・
「貸してくれるところから借りる」
です。

まぁ公務員さんとか、上場企業のような有名大企業にお勤めの方ならイザ知らず。
中小企業でかつ年収が400万にも満たないと、住宅ローンのハードルはとても高いです。
大分で有名なガメラ?の会社でさえ年収400以上の人なんて幹部クラス以上じゃないかと思います。
住宅ローンは「借りる」じゃないんです、「貸していただく」なのです。
これは銀行の窓口で苦渋をなめて初めて分かります。
「貸す」か「貸さない」かは相手が決める事なのです。
特に自営業者の方は、大金のローンを組むにあたり如何に銀行の真の姿が分かるというものです。
どこが金利が安いとか、手数料が・・という前に、そこが貸してくれるかどうかお伺いを立ててからの話ですね。
まぁ以前も最強の住宅ローンと書きましたが、ローンを借りるにあたり
銀行(銀行・信用組合・信用金庫ETC)
JAバンク(要JA組合員加入?)
労働金庫(ろうきん、基本的に公務員が使う、だからろうきんが出てくるところは大抵公務員、民間でろうきんを使っている人はめずらしい)
生命保険会社、一時やっていましたが今はやっているかどうか・・・
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)これは国です。
などが挙げられます。
最近ではソニー銀行とかもやってますね。
そして郵便局も民営化されたのでゆうちょでもいずれ住宅ローンを始めるでしょう。
で前の話ですが、住宅ローンは各金融機関ごとに様々な商品があり金利も様々です。
金利以外にも融資手数料や保証料、繰上げ返済手数料など諸費用なども差があります。
一番有利なところで借りたいのは誰しも一緒、でもね、そもそも「貸してくれなきゃ始まらない」のですよ。
ココで借りたいと思っても「貴方には貸せません」とか「貸せるのは幾らまでです」言われると正直凹みますよ。
ここで銀行は何を基準に融資の可否を諮るかと言えば、ズバリ
「返済能力」
これは年収の2.5-3倍と言われています。
年収400万で借りられるのは1200万円程度って事ですね。
もちろん頭金の有無はありますが、そもそも「頭金も貯金できない人に、何十年ものローンが返せる訳が無いでしょ?」というのが金融機関の考え方です。
ですから定期預金とか積み立て預金とかをやっている人は有利ですし、とにかく頭金があればあるほど融資の審査ハードルは低くなります。逆に頭金ゼロで融資なんて貸すほうもハイリスクなので金利も不利になるのは当たり前の事ですね。
そして融資審査のハードルが一番低いのは「住宅金融支援機構」です、現在は直接融資は行っておらず「フラット35」として各金融機関を通じて利用します。
田舎の山奥では土地の資産価値が低く、土地が担保としての役割を果たせないので銀行は融資に及び腰になります。その点フラット35では土地の担保価値は余り問われないのです。これは銀行が受けない融資の最後の受け皿的な意味合いがあるのです。
でもね、フラット35は金利が一定とは言っても、今の低金利時代、昨年の世界的金融不安からも当面市場金利が上がる事はないと言えます。
だって金利上げると借金漬けの日本の国が破綻してしまうからです。そんなことできる訳ない。
だからフラット35は銀行等のローン金利2%とかに敵わない・・・
まぁ何をどう判断するのかは各人次第ですけどね。
公務員さんなど金融会社から見た良いお客さんの場合、ローンは大抵のところから借りる事ができるでしょう。
ならばあちこち比較して選び放題ですね。
まぁ以前も書きました(あえてリンクは付けません)が、いずれはマイホームをと考えている方は、明日からでも住宅財形を始める事を強くお勧めしておきます。