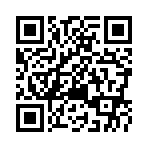2012年07月04日
雨樋
梅雨真っ盛りですね
大分県では中津市(と言っても耶馬溪)や日田市で甚大な被害が出ている模様です。

建物で雨といえば「雨樋」ですね
大抵の建物には「雨樋」が付けられているものです。
雪が多い地域では、雪で雨樋が壊されてしまうためつけない地域もありますが、九州でそれをやっているところは少ないですね。
今時の家に共通したデザインの傾向として
・軒が短い
・基礎が低い
ことが挙げられます。
これらの家で、もし雨樋を付けないとしたら・・・・
屋根から落ちてきた雨水は、地面で跳ね返り、建物壁を濡らしてしまいます。
建物は濡れてしまうと傷みの原因となります。
なので雨樋の施工は必須とも言えます。
ランタサルミや弊社設計ログハウスの特徴として
・軒が長い
・基礎が高い
ので、雨樋がなくとも地面に落ちた雨の跳ね返りは基礎に当たることはあってもログには当たりません。ログは濡らすと腐りの原因となってしまいます。
当たらないからと言っても、別荘ならイザ知らず、住宅であれば雨の日に家の周りを歩くこともあるでしょう。
なので雨樋は付けています。
しかし、二階の屋根は雨樋を付けていません。
二階のドーマー屋根から落ちる雨水は、一階の屋根の上に落ちるため雨樋は要らないのです。
もちろん付けても良いのですが・・・
縦樋が建物のデザインを台無しにしてしまいますね。
そして雨樋は「詰る」もの、詰った雨樋の掃除という仕事も増えてしまいますね。
建物をデザインする上で、雨樋の存在は無視出来ないですね。
大分県では中津市(と言っても耶馬溪)や日田市で甚大な被害が出ている模様です。

建物で雨といえば「雨樋」ですね
大抵の建物には「雨樋」が付けられているものです。
雪が多い地域では、雪で雨樋が壊されてしまうためつけない地域もありますが、九州でそれをやっているところは少ないですね。
今時の家に共通したデザインの傾向として
・軒が短い
・基礎が低い
ことが挙げられます。
これらの家で、もし雨樋を付けないとしたら・・・・
屋根から落ちてきた雨水は、地面で跳ね返り、建物壁を濡らしてしまいます。
建物は濡れてしまうと傷みの原因となります。
なので雨樋の施工は必須とも言えます。
ランタサルミや弊社設計ログハウスの特徴として
・軒が長い
・基礎が高い
ので、雨樋がなくとも地面に落ちた雨の跳ね返りは基礎に当たることはあってもログには当たりません。ログは濡らすと腐りの原因となってしまいます。
当たらないからと言っても、別荘ならイザ知らず、住宅であれば雨の日に家の周りを歩くこともあるでしょう。
なので雨樋は付けています。
しかし、二階の屋根は雨樋を付けていません。
二階のドーマー屋根から落ちる雨水は、一階の屋根の上に落ちるため雨樋は要らないのです。
もちろん付けても良いのですが・・・
縦樋が建物のデザインを台無しにしてしまいますね。
そして雨樋は「詰る」もの、詰った雨樋の掃除という仕事も増えてしまいますね。
建物をデザインする上で、雨樋の存在は無視出来ないですね。
2012年06月26日
カギを増やそう

先日お引渡しを終えた中津の市街地に建つログハウス
外部ドアは2箇所
うち1箇所は普通のシリンダータイプのカギ
もう一箇所は室内からのサムターンのみ、つまり外部からは開錠出来ないドアでした。
これが多少不便との事で外部からも開錠できるようシリンダーを追加しました。
こんな時、日本だと新しいシリンダーにはそれ用のキーが付いて来ます。
つまり2箇所のドアはそれぞれ別のキーで開錠することになります。
「何言ってんだ、当たり前じゃないか」
日本のカギ事情だと普通そうなります。
でも私たちは拘っています。
1つの建物で外部ドア毎にカギが違い、違うカギをいくつも持つのは面倒です。
なのでシリンダーメーカーに最初からあるもう1つのシリンダーと同じパターンのシリンダーをオーダーして送ってもらいました。
FINLANDから・・・・
これで同じキーで2つのドアのシリンダーが開錠できるようになりました。
新しいシリンダーにもキーが付いて来たので、これらはスペアキーとして保管しておいて頂くことに。
1本のキーで建物のどこのドアも開錠できるのは便利ですよ。
ちなみにこのカギは外国製でちょっと・・・なのでピッキングが利きません。
利きそうなのですが、プロが我が家のカギで挑みましたがピッキング開錠出来ませんでした。
ちょっとしたことですが、住む人にとっては大きな事です。
2012年06月08日
デタラメログハウス
弊社のログキットはパイン100%です
ウチのは全部ウエスタンレッドシーダーですよ
かつてログハウス輸入業者の謳い文句は、デザインよりも材料の品質やスペックなどを前面に出している時代がありました。
「本当にそうなのか?」
客の立場としては、業者側の言うことを信頼する以外、それを確かめる手段があっただろうか?
輸入されるログキットのボリュームは国際輸送コンテナ複数本
我が家のキットは40ftコンテナ2本 20ftコンテナ1本というボリュームだ
その量たるや莫大・・・とても材料の1つ1つをチェックするなど不可能だし、そもそもチェックできたとしても素人が木を見ただけで「これは何の木」などと判断などつけられる訳がない。
杉の中に檜が混じっていると言うような簡単なレベルではないからだ。
ホームセンターでSPFと称されて売られているツーバイ規格の輸入材、以前にも書いたがSPFなどという植物は存在しない、SPFという「木」は無いのだ。
S=スプルース(トウヒ属)
P=パイン(マツ属)
F=ファー(モミ属)
これらの強度の似通った木材をツーバイ規格で製材した混ぜこぜ材がSPFと1括りにされて売られている訳だ。さらに各材とも亜種でそれぞれ分類され植物学の分類では数種類の木が混ぜこぜになっている。製材所によってもブレンド内容は偏りがあるみたいなので、最早SPFとされたティンバー材を正確に仕分けするのはほぼ不可能だろう。まとめ買いした人の中には、明らかに「重さが違う」事に気付いた人も居るかもしれない、一般的にパイン系は重くスプルース系は軽い。
私が自宅ログハウスの材料を弄くっている時、明らかに「軽い」材料が交じっていることがあった。
垂木や間仕切りに使われる規格材だ、木材を長く扱っていると、人工乾燥材である程度均一な材料が用意された場合それらの重さはほとんど変わらない。明らかに2/3程度とか持てば分るレベルで重さが違う事は滅多にあることではない。重さが違うという事は比重が違うという事であり、それは材の個体差というよりは「違う材種の材料が交じっている」という事を指していると考えた方が自然だ。
ウチのログは素材100%この木ですよ と断言できるログキットは世間にどれだけ存在するのだろうか?
工場側が間違える事もあるだろうし、意図的に混入させるケースもあってもおかしくはない。
木材は日本であれ外国であれ「市場」で取引されるものだから、どこか一社だけが市場から格安に仕入れるなんてことは無い。特に森林管理が厳格に為されていれば為されているほど無い。
というのも山の所有者に、市場価格より安い値段で特定の相手に自分の木を売ろうなんてお人好しはそうは居ないからだ。
市場価格が分れば、ボリュームディスカウントはあるにせよその原料調達価格に大差は無い訳で、あとは加工の手間賃と建具などの調達価格、メーカーの利益だけがキット価格の構成要因となる。
価格競争に晒されている中で、自分の取り分だけは何が何でも確保しなくてはならないとなれば・・・
安いものには安い理由があり、高いものには高い理由がちゃんとあるのだ。
「信用」は「信頼」からしか生み出されないのではあるが・・・
裏切られたことが無いわけではない。
本物に出会ってしまったから。
ウチのは全部ウエスタンレッドシーダーですよ
かつてログハウス輸入業者の謳い文句は、デザインよりも材料の品質やスペックなどを前面に出している時代がありました。
「本当にそうなのか?」
客の立場としては、業者側の言うことを信頼する以外、それを確かめる手段があっただろうか?
輸入されるログキットのボリュームは国際輸送コンテナ複数本
我が家のキットは40ftコンテナ2本 20ftコンテナ1本というボリュームだ
その量たるや莫大・・・とても材料の1つ1つをチェックするなど不可能だし、そもそもチェックできたとしても素人が木を見ただけで「これは何の木」などと判断などつけられる訳がない。
杉の中に檜が混じっていると言うような簡単なレベルではないからだ。
ホームセンターでSPFと称されて売られているツーバイ規格の輸入材、以前にも書いたがSPFなどという植物は存在しない、SPFという「木」は無いのだ。
S=スプルース(トウヒ属)
P=パイン(マツ属)
F=ファー(モミ属)
これらの強度の似通った木材をツーバイ規格で製材した混ぜこぜ材がSPFと1括りにされて売られている訳だ。さらに各材とも亜種でそれぞれ分類され植物学の分類では数種類の木が混ぜこぜになっている。製材所によってもブレンド内容は偏りがあるみたいなので、最早SPFとされたティンバー材を正確に仕分けするのはほぼ不可能だろう。まとめ買いした人の中には、明らかに「重さが違う」事に気付いた人も居るかもしれない、一般的にパイン系は重くスプルース系は軽い。
私が自宅ログハウスの材料を弄くっている時、明らかに「軽い」材料が交じっていることがあった。
垂木や間仕切りに使われる規格材だ、木材を長く扱っていると、人工乾燥材である程度均一な材料が用意された場合それらの重さはほとんど変わらない。明らかに2/3程度とか持てば分るレベルで重さが違う事は滅多にあることではない。重さが違うという事は比重が違うという事であり、それは材の個体差というよりは「違う材種の材料が交じっている」という事を指していると考えた方が自然だ。
ウチのログは素材100%この木ですよ と断言できるログキットは世間にどれだけ存在するのだろうか?
工場側が間違える事もあるだろうし、意図的に混入させるケースもあってもおかしくはない。
木材は日本であれ外国であれ「市場」で取引されるものだから、どこか一社だけが市場から格安に仕入れるなんてことは無い。特に森林管理が厳格に為されていれば為されているほど無い。
というのも山の所有者に、市場価格より安い値段で特定の相手に自分の木を売ろうなんてお人好しはそうは居ないからだ。
市場価格が分れば、ボリュームディスカウントはあるにせよその原料調達価格に大差は無い訳で、あとは加工の手間賃と建具などの調達価格、メーカーの利益だけがキット価格の構成要因となる。
価格競争に晒されている中で、自分の取り分だけは何が何でも確保しなくてはならないとなれば・・・
安いものには安い理由があり、高いものには高い理由がちゃんとあるのだ。
「信用」は「信頼」からしか生み出されないのではあるが・・・
裏切られたことが無いわけではない。
本物に出会ってしまったから。
2011年06月06日
2010年11月09日
ハンガーパイプ

クローゼットの枕棚下にハンガーパイプを取り付けました。
ハンガーを引っ掛けて洋服を吊るすアレですね。

25φのパイプを買ってきて、余計な部分はパイプカッターで切り落とします。
シールを剥がして残ったノリを刷毛洗い液のシンナーで溶かして拭きます。
両サイドの金具で取り付けです。
2010年10月26日
ブタ鼻

通称「ブタ鼻」 正式名称「ベントキャップ」
近年、換気扇の排気口に多用されている丸いキャップです。
画像のこれはキッチンのレンジフード換気扇の排気口です。
150φの大きな奴です。
このブタ鼻を取り付ける為の穴
綺麗に丸く開ける必要があります。

ログ壁は木壁なのでホールソーで開けることが出来ます。
ただ木工用の160φ(有効150の穴を穿孔するには一回り大きなサイズとなる)のホールソーなんて使う頻度は少なく、道具はバカ高い(5万円以上します)ので持っている人なんて余程です。
今回は設備屋さんが持っていた、ボードなどを穿孔できるコアをお借りして穿孔しました。
まぁこんだけの穿孔工事なので貫通まで30分以上はドリドリやってました。

外側からだけ切っていくと、内側にバリが出て汚くなります。
内側は換気扇なのでカバーがキッチリと付くように、内側からも穴を開けておいて綺麗に丸くくり貫けるようにします。
コアにはセンターに先行ドリルがついているのでドリル穴を逆にセットすればよい訳です。
これだけの大きな穿孔では、クラッチ付のドリルでないと手首を持っていかれますので要注意ですね。
2010年10月22日
日本語読めませんか?

玄関アプローチでもある外部ウッドデッキも張られています。
屋根下にも関わらず、防腐剤の加圧注入材があてがわれています。
これは相当長く持つでしょう。

ところで
弊社の現場は基本として「土足厳禁」です。
しっかしまぁ、この現場に現れる「ほぼ全ての方」が、土足で犬走りに上がって大工さんのカミナリに打たれています。
「土足厳禁」
あちこちにベタベタ書いて置いてあるのですが・・・・
コンクリートに泥を擦り付けてしまうと「汚れが落ちない」んです。
また土足で上がるから仕上がったところが汚されてしまうのです。
「アンタら日本語読めないのか?」
現場に入るプロの職人として、下足を持っているのは当然の事です。
本日納品に来た兄ちゃん、張ったばかりの新品のデッキの上を靴のままで堂々と上がってくれたそうです。
「テメーケンカ売ってんのか?ブッ殺すぞ!!」
大工さんの罵声が飛んで来そうです。
※もちろん面と向かってここまでは言いません
無垢の木肌につけられた足跡、これを消すのも大変な作業なのです。
2010年09月20日
トリムボード

ランタサルミのトリムボードです。
日本語で言うと「額縁」ですね。
ランタサルミではオリジナルデザインのトリムボードを数種類の中から選ぶことが出来ます。
基本は2種類
画像はBタイプというプレーンな板のAタイプとは異なり、デザインを付けてあります。
トリムボードの厚みは30ミリ
分厚いトリムボードによって窓周りの凹凸が鮮明となり、建物のアクセントとなります。

セトリングが起きるログハウスにおいては
窓周りの防水対策
が重要課題でした。
建具には「キリヨケ」と呼ばれる小庇を取り付けますが、かつてはキリヨケもトリムボードと一体でしたのでセトリングによって建具上部の水密が取れず、雨漏りの原因となっていました。
ホンカも採用しているタイプのキリヨケを用いることで、窓上部からの浸水は大幅に改善され、ほぼ無くなりました。
そしてキリヨケのデザインもよりオリジナルなタイプに。
今では似たようなデザインのログハウスでも、キリヨケの違いを見ることでプランドが分かりそうです。
このキリヨケの収まりは少々特殊です。
2010年09月15日
断熱材充填

断熱材を施工しています。
ランタサルミの標準としてはGW64k-25ミリ+GW16k-100ミリのダブルです。
もちろん関東ベースですが。
こちら九州地区の公庫仕様準拠だとGW10k-50ミリでもok?
まぁ公庫仕様は準寒冷地の山間部だろうと、亜熱帯の湾岸部も全部一緒ですから。
無責任かついい加減な仕様と言わざるを得ません。
その辺りは本来設計者が考えて設定すべきことなのです。
しかし実態は・・・
大分の建材屋さんに、16キロの100ミリ厚というグラスウールは在庫されていません。
出ないそうです、いつも取り寄せしてもらってます。
弊社スタンダードはグラスウール16kを厚さ100ミリです。
屋根垂木は195ミリ、下から100ミリ断熱材が入りますので95ミリの通気層が確保されています。

床も同じくGW16k-100ミリです。
弊社オプションとして
GW150ミリ仕様
羊毛断熱材仕様(天然ウール)
をご用意しております。
ウレタン吹き付けは、通気層確保の観点から別仕様として。
セルロースファイバーも出来なくはありません。
2010年09月14日
軒天井の張り方

軒裏天井の事は「軒天」と呼びます。
ログハウスの軒天は大抵が板材です。
※準防火地域とかだと不燃材にする必要があります。
ランタサルミの標準軒天材は15x120ミリです。

軒天施工前です。
「垂木表し」状態です。
このままでも構わないのですが、下から見上げると野地板の合板が見えて格好悪いです。
垂木表し仕様にする際には、野地は合板を使わずに野地板を用いたいものです。
今時の住宅では軒天は新建材のオンパレードですね。

軒天を施工する準備です。
軒天材・ピンネイラー・ピンネイラーの弾・木工ボンド・テープメジャーなど

軒天材は「目透かし」の実加工されています。
まず材をセットして長さや収まりの確認をします。

破風板には予め溝を掘っておいて、軒天材を差し込めるようにしておきます。
破風板を取り付けてから溝を掘ることは出来ませんので(ノミでチマチマ掘れば出来なくは無い)、破風板は予め溝突き加工してから取り付ける訳です。
こうすると材が乾燥して痩せても、隙間が見えないようになります。
※施工者によっては溝を掘らずに施工する人も居ます。すると材が痩せて隙間が出来る恐れも。

切った材のサイズが良ければ、垂木にボンドをつけて実際に留めて行きます。

ちゃんと溝に差し込んで・・・

ピンネイルだけだと材が抜けてしまう事があるので、ボンドで確実に接着します。
ピンネイルはボンドが乾くまでの「押さえ」に過ぎません。
どんどん張っていき、終わり近くになればテープメジャーで桁までの距離を測り、正しく平行に張れているかチェックします。偏りしていたら、残りを少しずつずらして調整します。
ここでは妻壁部分の軒天なので短い方です。
これが桁側になると・・・家の幅に長く軒天をセットして留める事になります。
この作業は割りと大変です。
母屋や桁部分の入り隅部分の収まりは、屋根がスライドする「ゲープルエンド」仕様と、固められている「ティンバーゲーブル」仕様では収まりが異なります。
この辺りは各施工者によって少しずつ違うところですね。
2009年12月09日
電気が足りない
家づくりをするにあたって、こだわっているのが電力の契約アンペアです。
これによって基本料金が変ります。
低ければ低いほど、基本料金は安いのですが、逆に増やしたからといって大幅にUPするものでも無いです。が・・・毎月毎年と積み上がって行く費用なので100円差でも年間1200円10年で12000円ですからね。
この基本料金は従量契約と深夜電力契約、オール電化の契約など契約によっても異なりますし、各電力会社ごとに少しずつ違ったりします。
ちなみにオール電化の契約では契約アンペア数は無条件で100Aです。100Vで10000ワット、一般家庭のどこでそんだけ電気使うかってーの。
我が家は42坪のログですが、従量40A契約です。
3kwのIHヒーター使ってます。
一般的な電力消費と契約アンペアの求め方では、我が家の形態で40Aは少ないから60Aとかの契約を勧められます、しかし本当に60Aの契約でないと不自由するのか?
そこで40Aのままなのですが、全く不自由しておりません。
IHヒーターフルパワー(まず無い)に電子レンジと炊飯器とドライヤーと電気ポットとコーヒーメーカー程度を同時使用すればブレーカー落ちるかもしれませんが、そんなケースはまず無い訳でして・・・
理論上こうだからこんだけ必要、ってのは否定しませんが、足りるんならそれでいいじゃん。
というのが弊社の考え方です。
というのも、契約アンペアは増やす分(電力会社にとってプラス)には費用が掛らないのですが、減らす分については費用がかかるのです。まぁどちらも親ブレーカーを交換する訳ですが、増やす分には基本料金収入が増えるからそこからブレーカー代捻出しますって事ですな、減らすと収入減なのでブレーカー代頂きますと・・・つまり電力会社は「損しない方法」を地で行ってるだけ。
足りなくなれば増やせばいいじゃん・・・世間ではセコイとも言います。
さて、お客さんからブレーカーを落してしまったと相談がありました。
当初はガスファンヒーターによる個室暖房の設定でガス管を配管したり、コンセントを用意したりでした。ところが実際には電気式のオイルヒーターを各部屋に配して使おうとしたらしい・・・・
脱衣所と3寝室、ゲストルームと1200Wのオイルヒーターが5基・・・フルパワーで6000W=100Vで60A
(実際はコンセントには110V位来ているから60Aには到達しないんですけどね)
当然これに電灯やウォシュレットなどありとあらゆる生活家電の消費電力も加わる訳です。
しかもこのお宅、4kwのサウナストーブも付けています。
200v仕様なので20A・・・フルに使えば60Aオーバーなんて簡単なのです。
契約は40A、でも配電盤の割り振りで実際には60A程度使えるのですが、やはりオイルヒーター数台とサウナの同時稼動ではメインブレーカーが落ちました。
当たり前っちゃー当たり前です。
ブレーカーが落ちるというので子ブレーカーが落ちる=コンセントの回路分けで解決できると思っていたら、子ブレーカーの容量は間に合っていましてメインブレーカーが落ちることを確認
まぁ「電気が足りなくなった」訳です。
お客さんには契約アンペアを60程度に上げてくださいとご報告しておきました。
多分月々の基本料金が数百円UPだけの費用負担です。
私は電気については素人、あまり詳しくないし勉強もした訳ではありません。
サラリーマンの時にPCに詳しかった為にあれこれ重宝に使われていました、事務所移転の際に社内LANの構築はオマエがやれ(高いから外注するなという事)という事でシコシコやっていた訳ですが、そん時に親会社から出向で来ていた電気担当の技術職の方にシゴカレタのです。
「ペーター君、君はPCの配線とコンセント数をこうしろああしろと言うけど、容量はどうなっているんだね?」
「は?容量ですか?何ですかそれ?」
「いいかいペーター君、電気ってのはブレーカーから回路に分けて引っ張ってくる訳だが、それらの容量ってのは決まっているんだよ、それによって使うコードの太さも変える必要がある。ひとつの回路の容量は20Aだ、そこにどれだけのプリンター(1500W)やパソコンを繋げようと言うんだね?」
「そもそも容量が分らないのですが・・・」
「君は中学校でオームの法則って習わなかったかい?E=IRだろ?」
つまりアンペア=ワット/電圧って事、一回路に流せるのは20Aで電圧は100Vと決まっているので、回路で使ってよいのは2000Wまでって事だから、1500Wのプリンターやコピー機の繋がるコンセントは回路を分け1つ当り2000W以下に抑えておかないと(他にもいろんな機器が接続されるから)ダメだよという事でした。
私の作った配線プラン(ただどこにコンセントに幾つ付けてくださいってだけのもの)はあえなく却下され、それから残業して全てのPCやOA機器の消費電力を調べてリストに落して・・・
何度かダメ出しされた後にやっとOK貰って、電気工事会社へ依頼して新しい事務所の電気配線が工事され、僕は電気の線と一緒に埋めてもらうLANケーブルをシコシコと作っていた(100m巻のケーブル買ってきてコネクターを取り付ける)
そうやって現場で1つ1つ基本を教えてもらったから今があるんですねー。
これによって基本料金が変ります。
低ければ低いほど、基本料金は安いのですが、逆に増やしたからといって大幅にUPするものでも無いです。が・・・毎月毎年と積み上がって行く費用なので100円差でも年間1200円10年で12000円ですからね。
この基本料金は従量契約と深夜電力契約、オール電化の契約など契約によっても異なりますし、各電力会社ごとに少しずつ違ったりします。
ちなみにオール電化の契約では契約アンペア数は無条件で100Aです。100Vで10000ワット、一般家庭のどこでそんだけ電気使うかってーの。
我が家は42坪のログですが、従量40A契約です。
3kwのIHヒーター使ってます。
一般的な電力消費と契約アンペアの求め方では、我が家の形態で40Aは少ないから60Aとかの契約を勧められます、しかし本当に60Aの契約でないと不自由するのか?
そこで40Aのままなのですが、全く不自由しておりません。
IHヒーターフルパワー(まず無い)に電子レンジと炊飯器とドライヤーと電気ポットとコーヒーメーカー程度を同時使用すればブレーカー落ちるかもしれませんが、そんなケースはまず無い訳でして・・・
理論上こうだからこんだけ必要、ってのは否定しませんが、足りるんならそれでいいじゃん。
というのが弊社の考え方です。
というのも、契約アンペアは増やす分(電力会社にとってプラス)には費用が掛らないのですが、減らす分については費用がかかるのです。まぁどちらも親ブレーカーを交換する訳ですが、増やす分には基本料金収入が増えるからそこからブレーカー代捻出しますって事ですな、減らすと収入減なのでブレーカー代頂きますと・・・つまり電力会社は「損しない方法」を地で行ってるだけ。
足りなくなれば増やせばいいじゃん・・・世間ではセコイとも言います。
さて、お客さんからブレーカーを落してしまったと相談がありました。
当初はガスファンヒーターによる個室暖房の設定でガス管を配管したり、コンセントを用意したりでした。ところが実際には電気式のオイルヒーターを各部屋に配して使おうとしたらしい・・・・
脱衣所と3寝室、ゲストルームと1200Wのオイルヒーターが5基・・・フルパワーで6000W=100Vで60A
(実際はコンセントには110V位来ているから60Aには到達しないんですけどね)
当然これに電灯やウォシュレットなどありとあらゆる生活家電の消費電力も加わる訳です。
しかもこのお宅、4kwのサウナストーブも付けています。
200v仕様なので20A・・・フルに使えば60Aオーバーなんて簡単なのです。
契約は40A、でも配電盤の割り振りで実際には60A程度使えるのですが、やはりオイルヒーター数台とサウナの同時稼動ではメインブレーカーが落ちました。
当たり前っちゃー当たり前です。
ブレーカーが落ちるというので子ブレーカーが落ちる=コンセントの回路分けで解決できると思っていたら、子ブレーカーの容量は間に合っていましてメインブレーカーが落ちることを確認
まぁ「電気が足りなくなった」訳です。
お客さんには契約アンペアを60程度に上げてくださいとご報告しておきました。
多分月々の基本料金が数百円UPだけの費用負担です。
私は電気については素人、あまり詳しくないし勉強もした訳ではありません。
サラリーマンの時にPCに詳しかった為にあれこれ重宝に使われていました、事務所移転の際に社内LANの構築はオマエがやれ(高いから外注するなという事)という事でシコシコやっていた訳ですが、そん時に親会社から出向で来ていた電気担当の技術職の方にシゴカレタのです。
「ペーター君、君はPCの配線とコンセント数をこうしろああしろと言うけど、容量はどうなっているんだね?」
「は?容量ですか?何ですかそれ?」
「いいかいペーター君、電気ってのはブレーカーから回路に分けて引っ張ってくる訳だが、それらの容量ってのは決まっているんだよ、それによって使うコードの太さも変える必要がある。ひとつの回路の容量は20Aだ、そこにどれだけのプリンター(1500W)やパソコンを繋げようと言うんだね?」
「そもそも容量が分らないのですが・・・」
「君は中学校でオームの法則って習わなかったかい?E=IRだろ?」
つまりアンペア=ワット/電圧って事、一回路に流せるのは20Aで電圧は100Vと決まっているので、回路で使ってよいのは2000Wまでって事だから、1500Wのプリンターやコピー機の繋がるコンセントは回路を分け1つ当り2000W以下に抑えておかないと(他にもいろんな機器が接続されるから)ダメだよという事でした。
私の作った配線プラン(ただどこにコンセントに幾つ付けてくださいってだけのもの)はあえなく却下され、それから残業して全てのPCやOA機器の消費電力を調べてリストに落して・・・
何度かダメ出しされた後にやっとOK貰って、電気工事会社へ依頼して新しい事務所の電気配線が工事され、僕は電気の線と一緒に埋めてもらうLANケーブルをシコシコと作っていた(100m巻のケーブル買ってきてコネクターを取り付ける)
そうやって現場で1つ1つ基本を教えてもらったから今があるんですねー。
2009年11月28日
コンセントは多めに
ログハウスのみならず、家を建てる際に配慮したい事
それは・・・
コンセントは沢山付ける
という事
普通に付けられているコンセントって大抵2口タイプ
我が家のコンセントは大抵が・・・

3口タイプです。
何かと家電製品を使う現代生活のライフスタイル
コンセントが足りないとタップなどのタコ足配線が必要になり、さらにタップはそのコードが邪魔になります。
だから最初からタップリとコンセントを用意しておく事をお勧めしておきます。
ちなみに3つ口コンセントだろうと2つ口だろうと、コストはほとんど変わらないのです。
とは言うものの、コンセントの数はいくつ用意したら良いのか?

答えは簡単、今使っている電化製品機器の数だけ、そして今後増やすであろう数だけ用意します。
この画像は、我が家のテレビ裏のコンセントです。
テレビ
ビデオデッキx2台
スカパーチューナー
AVアンプ
これだけでも5口必要です。
だから3つ口コンセントを二連にして6口用意しておけば、将来何か増えても対応できますね。

こちらは台所のカウンター上のコンセント
台所周りもまたコンセントは沢山必要です。
しかも、トースターや電子レンジ、電気ポットに炊飯機と電気を食う機器が沢山です。
コンセントに繋がるブレーカーの回路も電線も、定格容量は20A(100Vで2000W)なので、1200Wの炊飯器のコンセントに繋がった電子レンジで1500W使うと当然子ブレーカーが落ちてしまいます。
つまり、こういう電気を沢山食う機器は別々のコンセント(正確には別の回路)に繋ぐ事で同時使用が出来るのです。
我が家は炊飯機と電子レンジはキャビネットにありますが、炊飯器の電源は冷蔵庫と一緒のコンセント、電子レンジはキャビネットが繋げている別のコンセント、他はこの集合コンセントから取るようになっています。
しかもこの2連コンセントは別々の回路にしてあるのです。
だからこれらでコーヒーメーカーとトースーターとジューサーやホットプレート同時使用でも問題ない訳です。
恐らく、現在の生活で台所の電気の制約を受けている方って少なくないと思います。
建売やマンションなどはコストを削る為にコンセントの数も絞り込んでいたりしますし、欲しい場所にコンセントが無いのでタップで延長しているとか・・・
弊社では家を作る際には、予め家具の配置を決め、どこでどういう電化製品をどう使うのか?
携帯電話の充電場所は?
掃除機のコンセントはどこに差す?
など、生活のありとあらゆるシーンを想定した上でコンセントを配しています。
だからコンセントはあるんだけど、家具の裏で使えない(ToT)という意味の無い事もありません。
ただ、既に1つ計算違いだった部分も出てしまっています。
それは光電話
NTTの光プレミアムを導入した事で、電話線を繋ぐVoIPアダプタが増えてしまいました。
電話機周りは、電話機本体、コピーマシン、コピーマシンをネットでシェアするターミナルと3つのコンセントは全部埋まっていた為、VoIPアダプタの電源が足りません。
ここは仕方ないのでタップで凌いでいます。
そもそも新築時に光プレミアムは存在していなかったので止む無しです。
ちなみに光の末端装置などは別の場所に置いてあり、そちらもコンセントテンコ盛です。
それは・・・
コンセントは沢山付ける
という事
普通に付けられているコンセントって大抵2口タイプ
我が家のコンセントは大抵が・・・

3口タイプです。
何かと家電製品を使う現代生活のライフスタイル
コンセントが足りないとタップなどのタコ足配線が必要になり、さらにタップはそのコードが邪魔になります。
だから最初からタップリとコンセントを用意しておく事をお勧めしておきます。
ちなみに3つ口コンセントだろうと2つ口だろうと、コストはほとんど変わらないのです。
とは言うものの、コンセントの数はいくつ用意したら良いのか?

答えは簡単、今使っている電化製品機器の数だけ、そして今後増やすであろう数だけ用意します。
この画像は、我が家のテレビ裏のコンセントです。
テレビ
ビデオデッキx2台
スカパーチューナー
AVアンプ
これだけでも5口必要です。
だから3つ口コンセントを二連にして6口用意しておけば、将来何か増えても対応できますね。

こちらは台所のカウンター上のコンセント
台所周りもまたコンセントは沢山必要です。
しかも、トースターや電子レンジ、電気ポットに炊飯機と電気を食う機器が沢山です。
コンセントに繋がるブレーカーの回路も電線も、定格容量は20A(100Vで2000W)なので、1200Wの炊飯器のコンセントに繋がった電子レンジで1500W使うと当然子ブレーカーが落ちてしまいます。
つまり、こういう電気を沢山食う機器は別々のコンセント(正確には別の回路)に繋ぐ事で同時使用が出来るのです。
我が家は炊飯機と電子レンジはキャビネットにありますが、炊飯器の電源は冷蔵庫と一緒のコンセント、電子レンジはキャビネットが繋げている別のコンセント、他はこの集合コンセントから取るようになっています。
しかもこの2連コンセントは別々の回路にしてあるのです。
だからこれらでコーヒーメーカーとトースーターとジューサーやホットプレート同時使用でも問題ない訳です。
恐らく、現在の生活で台所の電気の制約を受けている方って少なくないと思います。
建売やマンションなどはコストを削る為にコンセントの数も絞り込んでいたりしますし、欲しい場所にコンセントが無いのでタップで延長しているとか・・・
弊社では家を作る際には、予め家具の配置を決め、どこでどういう電化製品をどう使うのか?
携帯電話の充電場所は?
掃除機のコンセントはどこに差す?
など、生活のありとあらゆるシーンを想定した上でコンセントを配しています。
だからコンセントはあるんだけど、家具の裏で使えない(ToT)という意味の無い事もありません。
ただ、既に1つ計算違いだった部分も出てしまっています。
それは光電話
NTTの光プレミアムを導入した事で、電話線を繋ぐVoIPアダプタが増えてしまいました。
電話機周りは、電話機本体、コピーマシン、コピーマシンをネットでシェアするターミナルと3つのコンセントは全部埋まっていた為、VoIPアダプタの電源が足りません。
ここは仕方ないのでタップで凌いでいます。
そもそも新築時に光プレミアムは存在していなかったので止む無しです。
ちなみに光の末端装置などは別の場所に置いてあり、そちらもコンセントテンコ盛です。
2009年08月12日
静岡にて大地震
静岡で大きな地震がありましたね。
私が東京でログの営業マンをやっていた頃建てさせて頂いたお客さんのログも、最大震度レベルのエリアに数棟あります。
幸い一般住宅でも全壊半壊は無いと報道されているようですね。
まぁあれしきの地震で被災するような建物を建てた覚えはございませんが・・・
ログハウス(丸太組工法)という、校倉様式の建物は、おそらく木造では最強の強度を誇る建築様式ですね。科学的データも既に備わり、一般的な木造軸組工法に比べても断然強いデータを記録しています。
ある木造平屋に拘る建築士さんは
座っている大仏はひっぱるとコケルけど、寝ている大仏さんは引いてもコケナイ
と言いました。
つまり重心が低い建物は、揺れには強いという事です。
さらにログは揺れを吸収できる構造ですし、積み重ねたログによる「面」の強度が備わるので無類の強さ。
まぁ私がこのログハウスに拘って仕事している理由の1つでもあります。
様々なハウスメーカーがやれ耐震装置だの免震装置だのを数百万円とかでやっていますが、私の作るログハウスでは「もれなく」高い耐震性能が付いて来ます。追加ナシですわ。
そういう意味でもログハウスの値段って「非常に安い」と思うのは私だけでしょうか?
建物として「壊れない」だけじゃなく、大きな地震の後でもそのまま住み続けられるというのが利点なのです。壊れなくても「危なくて入るのもためらう」という家は多いですからね。

2年前の行なわれたログハウスの絶対強度を実証した実験の記事です。
------------------------------------------------------------------
ログハウスの耐震性を確認 日本ログハウス協会
2007年07月11日
日本ログハウス協会は7月11日、土木研究所(茨城県つくば市)で、「ログハウス実大振動実験」を行い、ログハウスに阪神淡路大震災に相当する揺れを与えたが、倒壊しなかった。ログハウスの実大振動実験は世界初とされる。
実験では、躯体サイズ7.28m×7.28mの国産杉材2階建てのログハウスに、震度5程度の揺れと、阪神淡路大震災時に神戸海洋気象台が観測した地震波(震度6程度)を3次元で再現した揺れを与えた。
ログの交差するノッチの一部で、内側と外側で2カ所ずつに
わずかなヒビが視認されたが、構造躯体に損傷はなく、強い揺れにも倒壊しない耐震性能を確認した。
同協会では、今回の試験データを基に、08年度以降をめどに
耐震等級2から3の耐震性能の認定を得ていきたいとしている。
ログハウスの丸太組構法は、丸太を横積みにして壁をつくる構造。同協会では、地震の揺れに対し、ログ同士が個々にスライドし、その摩擦力で地震力を吸収する制震性能があると考えており、試験データを基に実証していきたいとしている。
9月には3階建てを想定したログハウスの試験体で実験を行い、将来的に3階建てログハウスの実現を目指していきたいとしている。
-------------------------------------
これは朝日新聞からの引用です。
私が東京でログの営業マンをやっていた頃建てさせて頂いたお客さんのログも、最大震度レベルのエリアに数棟あります。
幸い一般住宅でも全壊半壊は無いと報道されているようですね。
まぁあれしきの地震で被災するような建物を建てた覚えはございませんが・・・
ログハウス(丸太組工法)という、校倉様式の建物は、おそらく木造では最強の強度を誇る建築様式ですね。科学的データも既に備わり、一般的な木造軸組工法に比べても断然強いデータを記録しています。
ある木造平屋に拘る建築士さんは
座っている大仏はひっぱるとコケルけど、寝ている大仏さんは引いてもコケナイ
と言いました。
つまり重心が低い建物は、揺れには強いという事です。
さらにログは揺れを吸収できる構造ですし、積み重ねたログによる「面」の強度が備わるので無類の強さ。
まぁ私がこのログハウスに拘って仕事している理由の1つでもあります。
様々なハウスメーカーがやれ耐震装置だの免震装置だのを数百万円とかでやっていますが、私の作るログハウスでは「もれなく」高い耐震性能が付いて来ます。追加ナシですわ。
そういう意味でもログハウスの値段って「非常に安い」と思うのは私だけでしょうか?
建物として「壊れない」だけじゃなく、大きな地震の後でもそのまま住み続けられるというのが利点なのです。壊れなくても「危なくて入るのもためらう」という家は多いですからね。

2年前の行なわれたログハウスの絶対強度を実証した実験の記事です。
------------------------------------------------------------------
ログハウスの耐震性を確認 日本ログハウス協会
2007年07月11日
日本ログハウス協会は7月11日、土木研究所(茨城県つくば市)で、「ログハウス実大振動実験」を行い、ログハウスに阪神淡路大震災に相当する揺れを与えたが、倒壊しなかった。ログハウスの実大振動実験は世界初とされる。
実験では、躯体サイズ7.28m×7.28mの国産杉材2階建てのログハウスに、震度5程度の揺れと、阪神淡路大震災時に神戸海洋気象台が観測した地震波(震度6程度)を3次元で再現した揺れを与えた。
ログの交差するノッチの一部で、内側と外側で2カ所ずつに
わずかなヒビが視認されたが、構造躯体に損傷はなく、強い揺れにも倒壊しない耐震性能を確認した。
同協会では、今回の試験データを基に、08年度以降をめどに
耐震等級2から3の耐震性能の認定を得ていきたいとしている。
ログハウスの丸太組構法は、丸太を横積みにして壁をつくる構造。同協会では、地震の揺れに対し、ログ同士が個々にスライドし、その摩擦力で地震力を吸収する制震性能があると考えており、試験データを基に実証していきたいとしている。
9月には3階建てを想定したログハウスの試験体で実験を行い、将来的に3階建てログハウスの実現を目指していきたいとしている。
-------------------------------------
これは朝日新聞からの引用です。
2008年05月19日
ログハウスのビス
ログハウスを作る際には釘も使いますがビスも多用します。
そのビスですが仕上げになると始末が悪いのです。

これは県内にある別のログ会社の物件ですが窓周りのケーシング(額縁)のビスがこれだけ離れていてもすぐに分かります。
近くで見ると・・

こんなんです、これを許せるかどうかは施主次第かと思いますが私にとっては「とんでもねぇ」です。
今時下手くそな住宅屋の家でもこんなのは無いですね。

ウチのオープンハウスの玄関ドアですが同じくビスで留めてあります。でもみっともないビス仕上げではありません。

ケーシングを留める際に予め下穴をあけてそこでビス留めしています。
下穴は丸棒を突っ込んで埋木してしまいます。

ちょっと手間なのですが材料費は安いもんです。

こんな感じに綺麗に仕上げることが出来ます。これに塗装すると赤いドアのような仕上がりになります。
木に金属はキラキラして目立っちゃって仕方ないです。
室内も同様です。

他所のログ屋さんのはこんな感じ、おいおいって感じですね。せっかくの木が台無しだと思うのは私だけでしょうか?

一応メーカー指示はスリムビスで留める事になっていますが、上の画像のようにビスは金属も目立つし+も目立ちます。ですからウチではビス留めしないでフィニッシュネイルを使います。
ゴマ粒みたいな打ち込跡は近くで見ると分かりますが、ビスのやぼったさに比べると全然マシだと思っています。
ウチはこのビス頭隠しの仕上げを標準仕様にしています。ただ二階妻壁(バルコニーなどを除く)など下から見上げるだけとかの間近で直接見えない位置にあるものは省かせて頂いたりしますが。
そのビスですが仕上げになると始末が悪いのです。

これは県内にある別のログ会社の物件ですが窓周りのケーシング(額縁)のビスがこれだけ離れていてもすぐに分かります。
近くで見ると・・

こんなんです、これを許せるかどうかは施主次第かと思いますが私にとっては「とんでもねぇ」です。
今時下手くそな住宅屋の家でもこんなのは無いですね。

ウチのオープンハウスの玄関ドアですが同じくビスで留めてあります。でもみっともないビス仕上げではありません。

ケーシングを留める際に予め下穴をあけてそこでビス留めしています。
下穴は丸棒を突っ込んで埋木してしまいます。

ちょっと手間なのですが材料費は安いもんです。

こんな感じに綺麗に仕上げることが出来ます。これに塗装すると赤いドアのような仕上がりになります。
木に金属はキラキラして目立っちゃって仕方ないです。
室内も同様です。

他所のログ屋さんのはこんな感じ、おいおいって感じですね。せっかくの木が台無しだと思うのは私だけでしょうか?

一応メーカー指示はスリムビスで留める事になっていますが、上の画像のようにビスは金属も目立つし+も目立ちます。ですからウチではビス留めしないでフィニッシュネイルを使います。
ゴマ粒みたいな打ち込跡は近くで見ると分かりますが、ビスのやぼったさに比べると全然マシだと思っています。
ウチはこのビス頭隠しの仕上げを標準仕様にしています。ただ二階妻壁(バルコニーなどを除く)など下から見上げるだけとかの間近で直接見えない位置にあるものは省かせて頂いたりしますが。