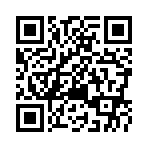2011年08月21日
住まいの歴史
住まいである「家」を作る仕事をする上で、「何を持っていい家なのか?」という命題にブチ当ります。
かつて「良いモノが売れるのではなくて、売れたモノが良いものなんだ」という結論に落ち着いたこともあり、つまりは大衆迎合して広く普及して認められたものが大勢として良いものなのだろう、と結論付けています。
もちろん「一般論」としてです。
それに絡めて考えさせられるのは歴史です。
日本の住まいの歴史を紐解いていくと、様々なものが見えてくるような気がします。
世界的に見ても、家を作る材料として選ばれているものの結果は
「手に入りやすいもの」です。
木がある地域の人々は、木を使って家を作ってきました。
木は無いけど石はある、という地域の人々は石で家を作ってきました。
木も石も無いという地域の人々は、例えばモンゴルなどであれば遊牧民達は家畜の毛から作るフエルトを骨組みに被せるゲルを住まいとしています。
アフリカなどでは家畜の糞を乾かしたプロックで家を作っているところもあります。
それに気候環境がプラス要因されます。
東南アジアなどでは木はあるけど、より身近にある竹で家を作ったりします。
その方が簡単だし木を切るより竹を切る方が入手が易く、また竹で網のように編んだ風通しの良い家の方が快適だからなのでしょう。
日本の家を見てみると、300年間も続いた江戸時代の建築を見てみるとその答えが出ているように思われます。
建物は伝統工法とも呼ばれる木造軸組工法です。
基礎は束石、大きめの石を置いてその上に柱を立てていました。
コンクリートが登場する大正以前においては、基礎は比較的安定した地盤の場所を叩いて転圧し、表面が平らな石を置いたものが基礎でした。結構なお屋敷でもこれで支えられています。
建物を構成する材料は、柱や梁の木、壁を形成している小舞の竹、ワラ縄と土壁の土、スサとなるワラなどです。屋根はお金持ちは陶器瓦、一般的には「茅葺」ですね。
江戸時代には重たいものを遠くへ運ぶことは困難であり、身近なところで沢山調達できる材料を使って家が建てられていました。
柱は山で切り倒した木をそのまま使ったり、製材したりです。切り出しには近所や知り合いなど沢山の手を借りて人力で切り倒し、馬などで引っ張って運んでいたのでしょう。
大黒柱などは四角く製材された材を使うものの、梁などは曲っている木を「チョウナ」で削っただけのものを使ったり、束柱などは皮を剥いで荒製材したもので構成されていました。
今のように全ての柱や梁が四角く製材された材では無かった訳です。それは製材自体が大鋸とカンナによる手作業であり大変なものだったからでしょうね。
日本にも「校倉造り」「井楼造り」として材木を積み上げて壁を作る工法は存在しました。
しかし、この工法はたくさんの木材を必要とする為、一般には普及せず、穀物を保管する倉庫など大切な建物として使われていました。
四角い空間を作るのに、軸組工法であれば12本の材木があればフレームが造れます、しかし校倉で12本ではたったの3段分にしかならないのです。
最小限の木材でフレームを作り、その壁にそこら中でタダ同然で簡単に手に入る竹を切ってきて割り、竹で編んだ網を張って竹小舞を造ります。
当時の日本は稲作を主とした農耕文化でした、壁に塗るための土は田んぼに行けば幾らでもあります、またそこいらを掘っても土はタダ同然で手に入りました。
土だけを塗ったのでは雨が良く降り台風も来る日本の家屋の壁は持たないので、短く切ったワラを土に混ぜ込み醗酵させる事で接着性質を向上、こうして竹小舞に何層かの土壁を塗ることで強度があって簡単には壊れない土の壁が作れました。
お金持ちは更に表面に「漆喰」によって美しく仕上げて冨を主張していた訳ですね。
一般の農民などは最低限の資源で家を作っていた訳ですね。
当時はドアなんてありませんから入り口はワラで編んだムシロとかです。紙でさえ貴重品という時代ですから障子なんてのは町の侍やお金持ちの商人達のものだったのでしょう。
屋根もまた、垂木に竹を縛り付け、そこいらに幾らでも生えていたであろうカヤを刈ってきて茅葺屋根に、お金持ちは竹の上に檜の皮や杉の皮を張り、土をのせた上に瓦を敷いていました。
古い日本の家の材料構成を見ていると、わざわざ遠くから運んでくるようなものは無く、大抵はおらが村で調達できるような材料で作られていたわけです。
当時の物流事情といえば、牛馬か人力で大八車とかを引いて品物を港まで運び、船で運んでいたでしょうから大きなものや長いものの長距離運搬は難しかったのでしょう。
材木はつい最近まで川を流して運ぶのが当たり前でした。
最近の家づくりでは「ビスとか釘」などはごく当たり前ですが、昔の家では鉄が貴重品なのですから釘なども最低限です。地震がありますから「木組み」の技術が発達し、貫など地震に対抗出来る工法へと進化していきました。「ほぞ」もまた西洋ではマイナーな技術です。
我々がログハウスの材料を調達しているフィンランド、この地域では木は沢山ありますが土が少なかった・・・・地面は1メートルも掘れば岩盤、土も落ち葉やコケの堆積物ですから日本の土壁に使っているような土はあまり無い、だからひたすら木を組上げていたのでしょう。
幸いにもフィンランドには山は無く、木を引いてくれるトナカイは居ました。
隣国スウェーデンには良質な鉄があり、よく切れる刃物があったのでしょうね。
この時代には機械製材はありませんから、やはりハンドカットログハウスのような建物が主流だったようです、WW2のドイツとロシアの戦いの記録などでは、ログハウスの住宅が戦火に焼かれているシーンが見受けられるのです。
エジプトが栄えていた太古の昔、やはり建物は木造が多く、今の砂漠の大地は森だったそうです。
再生スピード以上に木を切りつづけた結果、エジプトは木を失い、残された砂と石で家をつくらなくてはならなくなったそうで・・・・
中国でもシルクロードの砂漠に埋もれた遺跡には、昔の軸組工法の建物の柱などがあるようです。
オーストラリアのアボリジニや、アフリカのブッシュマンなどは家らしい家を持たないようです、そもそもシェルター機能を必要としない地域では、建物としての家の必然性すら無いわけで・・・
とにかく身近に豊富にあって、入手が易くて経済的にも安いもの、こういう材料を使って人々の住まいは作られてきた訳ですね。
WW2中、米軍は日本の家屋が「木と紙だけで出来ている」と分析し、焼夷弾を開発して日本の都市を焼き払いました。
「地震・雷・火事・オヤジ」と日本の人々は耐震性が高いとは言えない工法、燃えやすい木と紙の家の脆弱性をよく理解していたのでしょうね。
実家は江戸末期の家ですから築140年近くになります。
未だに両親が住んでおり、それなりに近代的に手を入れたりはされていますが、基本的には建てられた当時のままの部分が多いです。
かなり凝った意匠の部分もあれば、訳の分からない部分もあったりします。
柱を触れば江戸時代、畳の下の板もまた江戸時代のままなんです・・・
かつて「良いモノが売れるのではなくて、売れたモノが良いものなんだ」という結論に落ち着いたこともあり、つまりは大衆迎合して広く普及して認められたものが大勢として良いものなのだろう、と結論付けています。
もちろん「一般論」としてです。
それに絡めて考えさせられるのは歴史です。
日本の住まいの歴史を紐解いていくと、様々なものが見えてくるような気がします。
世界的に見ても、家を作る材料として選ばれているものの結果は
「手に入りやすいもの」です。
木がある地域の人々は、木を使って家を作ってきました。
木は無いけど石はある、という地域の人々は石で家を作ってきました。
木も石も無いという地域の人々は、例えばモンゴルなどであれば遊牧民達は家畜の毛から作るフエルトを骨組みに被せるゲルを住まいとしています。
アフリカなどでは家畜の糞を乾かしたプロックで家を作っているところもあります。
それに気候環境がプラス要因されます。
東南アジアなどでは木はあるけど、より身近にある竹で家を作ったりします。
その方が簡単だし木を切るより竹を切る方が入手が易く、また竹で網のように編んだ風通しの良い家の方が快適だからなのでしょう。
日本の家を見てみると、300年間も続いた江戸時代の建築を見てみるとその答えが出ているように思われます。
建物は伝統工法とも呼ばれる木造軸組工法です。
基礎は束石、大きめの石を置いてその上に柱を立てていました。
コンクリートが登場する大正以前においては、基礎は比較的安定した地盤の場所を叩いて転圧し、表面が平らな石を置いたものが基礎でした。結構なお屋敷でもこれで支えられています。
建物を構成する材料は、柱や梁の木、壁を形成している小舞の竹、ワラ縄と土壁の土、スサとなるワラなどです。屋根はお金持ちは陶器瓦、一般的には「茅葺」ですね。
江戸時代には重たいものを遠くへ運ぶことは困難であり、身近なところで沢山調達できる材料を使って家が建てられていました。
柱は山で切り倒した木をそのまま使ったり、製材したりです。切り出しには近所や知り合いなど沢山の手を借りて人力で切り倒し、馬などで引っ張って運んでいたのでしょう。
大黒柱などは四角く製材された材を使うものの、梁などは曲っている木を「チョウナ」で削っただけのものを使ったり、束柱などは皮を剥いで荒製材したもので構成されていました。
今のように全ての柱や梁が四角く製材された材では無かった訳です。それは製材自体が大鋸とカンナによる手作業であり大変なものだったからでしょうね。
日本にも「校倉造り」「井楼造り」として材木を積み上げて壁を作る工法は存在しました。
しかし、この工法はたくさんの木材を必要とする為、一般には普及せず、穀物を保管する倉庫など大切な建物として使われていました。
四角い空間を作るのに、軸組工法であれば12本の材木があればフレームが造れます、しかし校倉で12本ではたったの3段分にしかならないのです。
最小限の木材でフレームを作り、その壁にそこら中でタダ同然で簡単に手に入る竹を切ってきて割り、竹で編んだ網を張って竹小舞を造ります。
当時の日本は稲作を主とした農耕文化でした、壁に塗るための土は田んぼに行けば幾らでもあります、またそこいらを掘っても土はタダ同然で手に入りました。
土だけを塗ったのでは雨が良く降り台風も来る日本の家屋の壁は持たないので、短く切ったワラを土に混ぜ込み醗酵させる事で接着性質を向上、こうして竹小舞に何層かの土壁を塗ることで強度があって簡単には壊れない土の壁が作れました。
お金持ちは更に表面に「漆喰」によって美しく仕上げて冨を主張していた訳ですね。
一般の農民などは最低限の資源で家を作っていた訳ですね。
当時はドアなんてありませんから入り口はワラで編んだムシロとかです。紙でさえ貴重品という時代ですから障子なんてのは町の侍やお金持ちの商人達のものだったのでしょう。
屋根もまた、垂木に竹を縛り付け、そこいらに幾らでも生えていたであろうカヤを刈ってきて茅葺屋根に、お金持ちは竹の上に檜の皮や杉の皮を張り、土をのせた上に瓦を敷いていました。
古い日本の家の材料構成を見ていると、わざわざ遠くから運んでくるようなものは無く、大抵はおらが村で調達できるような材料で作られていたわけです。
当時の物流事情といえば、牛馬か人力で大八車とかを引いて品物を港まで運び、船で運んでいたでしょうから大きなものや長いものの長距離運搬は難しかったのでしょう。
材木はつい最近まで川を流して運ぶのが当たり前でした。
最近の家づくりでは「ビスとか釘」などはごく当たり前ですが、昔の家では鉄が貴重品なのですから釘なども最低限です。地震がありますから「木組み」の技術が発達し、貫など地震に対抗出来る工法へと進化していきました。「ほぞ」もまた西洋ではマイナーな技術です。
我々がログハウスの材料を調達しているフィンランド、この地域では木は沢山ありますが土が少なかった・・・・地面は1メートルも掘れば岩盤、土も落ち葉やコケの堆積物ですから日本の土壁に使っているような土はあまり無い、だからひたすら木を組上げていたのでしょう。
幸いにもフィンランドには山は無く、木を引いてくれるトナカイは居ました。
隣国スウェーデンには良質な鉄があり、よく切れる刃物があったのでしょうね。
この時代には機械製材はありませんから、やはりハンドカットログハウスのような建物が主流だったようです、WW2のドイツとロシアの戦いの記録などでは、ログハウスの住宅が戦火に焼かれているシーンが見受けられるのです。
エジプトが栄えていた太古の昔、やはり建物は木造が多く、今の砂漠の大地は森だったそうです。
再生スピード以上に木を切りつづけた結果、エジプトは木を失い、残された砂と石で家をつくらなくてはならなくなったそうで・・・・
中国でもシルクロードの砂漠に埋もれた遺跡には、昔の軸組工法の建物の柱などがあるようです。
オーストラリアのアボリジニや、アフリカのブッシュマンなどは家らしい家を持たないようです、そもそもシェルター機能を必要としない地域では、建物としての家の必然性すら無いわけで・・・
とにかく身近に豊富にあって、入手が易くて経済的にも安いもの、こういう材料を使って人々の住まいは作られてきた訳ですね。
WW2中、米軍は日本の家屋が「木と紙だけで出来ている」と分析し、焼夷弾を開発して日本の都市を焼き払いました。
「地震・雷・火事・オヤジ」と日本の人々は耐震性が高いとは言えない工法、燃えやすい木と紙の家の脆弱性をよく理解していたのでしょうね。
実家は江戸末期の家ですから築140年近くになります。
未だに両親が住んでおり、それなりに近代的に手を入れたりはされていますが、基本的には建てられた当時のままの部分が多いです。
かなり凝った意匠の部分もあれば、訳の分からない部分もあったりします。
柱を触れば江戸時代、畳の下の板もまた江戸時代のままなんです・・・