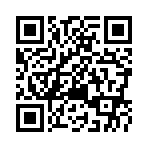2009年02月26日
地球温暖化と木
難しいお話です。
地球温暖化が叫ばれ、大気中のco2濃度の上昇が元凶であるとする説が有力視され支持を集めています。
その矢面に立たされているのが化石燃料であることは周知の通りですね。
地下深く封印されていた過去の時代のco2の塊たる化石燃料、原油に天然ガスなど、私達はこれらを資源として地上へ持ち出し、使い終わったカスとしてco2化して大気中にバラマクという行為をこの僅か100数十年の間に急速に行いました。
その結果地球を覆っているオゾン層にオゾンホールが・・・
という訳で「木」が注目されています。
なぜなら「木は地球上で唯一co2を長期固定化できる物質だからです」
だからどんどん木を育て、木を使って温暖化を防止しようなどと言われています。
ここで多くの誤解が生じています。
「地球温暖化を防止する為にはco2の削減が必要である」 これはyesだと思います。
「その為に木を植えましょう」 これはNOです。
「その為に植物を育てましょう」これは△です。
co2削減の為にはエネルギーの消費絶対量を減らす必要があります。
化石エネルギーを非化石エネルギーで代替する事が必要であるとされ、バイオマス発電だのペレット燃料だのと言われています。
もし、大気中に放出されてしまったco2がどこにも吸着、固定されないとすれば、例えバイオマスだろうとペレットだろうと原子力だろうと、大気中のco2は減りません。ただ増加スピードが鈍くなるだけですね。
発生するco2を環境負荷なく固定できる能力を持っているのは植物のみです。
植物は大気中の二酸化炭素と水を取り込んでセルロースを形成し酸素を吐き出す光合成の出来る生物です。
その仕組み光合成は化学式では
6co2+6h2o+太陽熱エネルギー→c6h12o6(ブドウ糖)+6o2
だそうです。
そして私が木を燃やしたり、木が腐って土に還ると・・・・
c6h12o6+6o2→6co2+6h2o+熱エネルギー
となるのです。
根から水を吸って葉の葉緑素が太陽光エネルギーでもってco2とH2oを反応させて栄養を作っている・・・それ位までは理解していましたが、実際の化学式まで出てくると目からウロコでしたね。
そして木をエネルギーとして使うと逆の計算になる・・・なるほど
植物はco2を固定化できるのでco2の缶詰みたいな存在と言えます。
でも必要なのは長期間に渡って固定化してくれる事であり、草のように一年で固定しては枯れて再びco2に戻る(微生物による草の分解過程で発生する)ショートサイクルでは大気中のco2量の削減には貢献しないと言うものです。
植物における「木」と「草」の違いってご存知でしょうか?
竹は「草」の分類です、植物の中で成長をし続けるものを「木」と呼び、一定の成長で止まってしまうものを「草」と分けるそうです。ブドウやイチゴなども「樹」であり「草」とは呼ばないのもこういう理由です。
ですから二酸化炭素の長期固定には草は不向きであり、木が向いている訳です。
木は樹齢も長く、固定化した状態で長く使うことができますからね。
それとて長期では循環しているサイクルでありco2を地球上から消している訳ではありません。
木はどんどんco2を吸収して固定します、スギでそのサイクルは90年程度らしいです。
つまり90年生のスギはco2吸収は飽和してしまい、それ以降はほとんど吸収しなくなるというデータがあるそうです。これは森林を学ぶにあたり興味深いデータですね。
これ位の樹齢の木を切って木は木材として使う、そして新しい木を植えてどんどんco2の固定化を図る、こういう事が今求められているのです。
木を構成する成分は、化学式ではc6h12o6(ブドウ糖)が変化したものだそうです。
炭素6に水素12酸素6、重量は1/2がcなので1kgの木材を作るには0.5kgのCと、1.83kgのco2が必要という計算になるそうです。
木の重さが分かれば、その木がどれだけのco2を固定化しているのか数値化できる訳ですね。
長期間に渡って木を使いつづけること、そして新しい木を育てること、これがco2をより多く固定化させる為に求められています。
さて建築の話です。
現在の日本の木造の寿命は25年程度と言われています。
これをもっと長期化できればco2削減には貢献できる事になります。
解体された家屋は燃やされたり腐ったりして固定化していたco2を再び大気中に放出させてしまうからです。
そんな事言っても"傷んだ古い家"になんか誰も住みたくない、古い家は今のライフスタイルにそぐわない、それはそうだと思います。
私も生まれてすぐに築100年を迎えた家で育ちましたから・・・
昔の家は構成している材料は「木」「石」「紙や縄など植物原料のもの」「土(瓦)」とガラス程度でした。
文明が進むと電線が張られ「自然に帰せない材料」が加わり、補強と称して金属が加わりました。
現在建てられる木造の家は「サイディング」という再利用も難しい材料に「ビニールクロス」だとか「石膏ボード」とか「合板」という接着剤の塊などで構成されています。やれ24時間換気だの空調だのと沢山の電化製品が取り付けられ、プラスチックも沢山使われています。
屋根もコロニアルとかいう合成樹脂の塊です。
新建材と呼ばれるそれらが作られる際には膨大な量のco2が排出されています。
古い家は壊しても廃棄物の大半は自然に還す事が出来るものばかりです。
今の家は壊すと埋め立て処分するしかないものが沢山出来ます。
今産業廃棄物の処理コストは上昇し続けています。
私が手がけているログハウス、建物を構成するのはほとんど全部「木」です。
壁は木オンリー、床下と天井にウールやガラスの断熱材を使いますが、壁は木のみです。
組み合わせるドアや窓も木製です。
僅かに金属とガラスを使いますが、処分に困る樹脂やアルミサッシはほとんど使いません。
ここに建材を作り出すために必要なエネルギーを比較した表があります。

基礎のコンクリートや釘金物も多少は使っていますが、コンクリート造りの家や鉄骨作りの家が如何に大きな環境負荷をかけて作られるかイメージ出来そうです。
私がログハウスを好きな理由は、
建物として作られるまでの環境負荷が少ない事
建物が自然素材たる木でほぼ構成されている事
室内空間が快適で精神的にも良い事(シックハウスは無縁です)
建物が地震に対してメチャクチャ強い構造体である事
建物のデザインも内装もカッコいい事
これだけ膨大な量の木を使って作っている割に「安い」事
建物としてシンプルな事(メンテナンスが易い)
大切に使えば一生使いつづけられる程の耐久性がある事
(つまり老後にボロボロのマイホームで暮らさなくても良いって事)
鉄砲で撃たれても弾が貫通して来ない事(西部劇の見すぎ?)
環境にも住む人にとっても優しい建物という事で、ログハウスに住んでログハウスを作るという仕事をしています。
もちろん昔ながらの木をふんだんに使った在来工法もやっています。
だから暖房も化石燃料をやめて薪ストーブを燃やして賄っている訳です。
地球温暖化が叫ばれ、大気中のco2濃度の上昇が元凶であるとする説が有力視され支持を集めています。
その矢面に立たされているのが化石燃料であることは周知の通りですね。
地下深く封印されていた過去の時代のco2の塊たる化石燃料、原油に天然ガスなど、私達はこれらを資源として地上へ持ち出し、使い終わったカスとしてco2化して大気中にバラマクという行為をこの僅か100数十年の間に急速に行いました。
その結果地球を覆っているオゾン層にオゾンホールが・・・
という訳で「木」が注目されています。
なぜなら「木は地球上で唯一co2を長期固定化できる物質だからです」
だからどんどん木を育て、木を使って温暖化を防止しようなどと言われています。
ここで多くの誤解が生じています。
「地球温暖化を防止する為にはco2の削減が必要である」 これはyesだと思います。
「その為に木を植えましょう」 これはNOです。
「その為に植物を育てましょう」これは△です。
co2削減の為にはエネルギーの消費絶対量を減らす必要があります。
化石エネルギーを非化石エネルギーで代替する事が必要であるとされ、バイオマス発電だのペレット燃料だのと言われています。
もし、大気中に放出されてしまったco2がどこにも吸着、固定されないとすれば、例えバイオマスだろうとペレットだろうと原子力だろうと、大気中のco2は減りません。ただ増加スピードが鈍くなるだけですね。
発生するco2を環境負荷なく固定できる能力を持っているのは植物のみです。
植物は大気中の二酸化炭素と水を取り込んでセルロースを形成し酸素を吐き出す光合成の出来る生物です。
その仕組み光合成は化学式では
6co2+6h2o+太陽熱エネルギー→c6h12o6(ブドウ糖)+6o2
だそうです。
そして私が木を燃やしたり、木が腐って土に還ると・・・・
c6h12o6+6o2→6co2+6h2o+熱エネルギー
となるのです。
根から水を吸って葉の葉緑素が太陽光エネルギーでもってco2とH2oを反応させて栄養を作っている・・・それ位までは理解していましたが、実際の化学式まで出てくると目からウロコでしたね。
そして木をエネルギーとして使うと逆の計算になる・・・なるほど
植物はco2を固定化できるのでco2の缶詰みたいな存在と言えます。
でも必要なのは長期間に渡って固定化してくれる事であり、草のように一年で固定しては枯れて再びco2に戻る(微生物による草の分解過程で発生する)ショートサイクルでは大気中のco2量の削減には貢献しないと言うものです。
植物における「木」と「草」の違いってご存知でしょうか?
竹は「草」の分類です、植物の中で成長をし続けるものを「木」と呼び、一定の成長で止まってしまうものを「草」と分けるそうです。ブドウやイチゴなども「樹」であり「草」とは呼ばないのもこういう理由です。
ですから二酸化炭素の長期固定には草は不向きであり、木が向いている訳です。
木は樹齢も長く、固定化した状態で長く使うことができますからね。
それとて長期では循環しているサイクルでありco2を地球上から消している訳ではありません。
木はどんどんco2を吸収して固定します、スギでそのサイクルは90年程度らしいです。
つまり90年生のスギはco2吸収は飽和してしまい、それ以降はほとんど吸収しなくなるというデータがあるそうです。これは森林を学ぶにあたり興味深いデータですね。
これ位の樹齢の木を切って木は木材として使う、そして新しい木を植えてどんどんco2の固定化を図る、こういう事が今求められているのです。
木を構成する成分は、化学式ではc6h12o6(ブドウ糖)が変化したものだそうです。
炭素6に水素12酸素6、重量は1/2がcなので1kgの木材を作るには0.5kgのCと、1.83kgのco2が必要という計算になるそうです。
木の重さが分かれば、その木がどれだけのco2を固定化しているのか数値化できる訳ですね。
長期間に渡って木を使いつづけること、そして新しい木を育てること、これがco2をより多く固定化させる為に求められています。
さて建築の話です。
現在の日本の木造の寿命は25年程度と言われています。
これをもっと長期化できればco2削減には貢献できる事になります。
解体された家屋は燃やされたり腐ったりして固定化していたco2を再び大気中に放出させてしまうからです。
そんな事言っても"傷んだ古い家"になんか誰も住みたくない、古い家は今のライフスタイルにそぐわない、それはそうだと思います。
私も生まれてすぐに築100年を迎えた家で育ちましたから・・・
昔の家は構成している材料は「木」「石」「紙や縄など植物原料のもの」「土(瓦)」とガラス程度でした。
文明が進むと電線が張られ「自然に帰せない材料」が加わり、補強と称して金属が加わりました。
現在建てられる木造の家は「サイディング」という再利用も難しい材料に「ビニールクロス」だとか「石膏ボード」とか「合板」という接着剤の塊などで構成されています。やれ24時間換気だの空調だのと沢山の電化製品が取り付けられ、プラスチックも沢山使われています。
屋根もコロニアルとかいう合成樹脂の塊です。
新建材と呼ばれるそれらが作られる際には膨大な量のco2が排出されています。
古い家は壊しても廃棄物の大半は自然に還す事が出来るものばかりです。
今の家は壊すと埋め立て処分するしかないものが沢山出来ます。
今産業廃棄物の処理コストは上昇し続けています。
私が手がけているログハウス、建物を構成するのはほとんど全部「木」です。
壁は木オンリー、床下と天井にウールやガラスの断熱材を使いますが、壁は木のみです。
組み合わせるドアや窓も木製です。
僅かに金属とガラスを使いますが、処分に困る樹脂やアルミサッシはほとんど使いません。
ここに建材を作り出すために必要なエネルギーを比較した表があります。

基礎のコンクリートや釘金物も多少は使っていますが、コンクリート造りの家や鉄骨作りの家が如何に大きな環境負荷をかけて作られるかイメージ出来そうです。
私がログハウスを好きな理由は、
建物として作られるまでの環境負荷が少ない事
建物が自然素材たる木でほぼ構成されている事
室内空間が快適で精神的にも良い事(シックハウスは無縁です)
建物が地震に対してメチャクチャ強い構造体である事
建物のデザインも内装もカッコいい事
これだけ膨大な量の木を使って作っている割に「安い」事
建物としてシンプルな事(メンテナンスが易い)
大切に使えば一生使いつづけられる程の耐久性がある事
(つまり老後にボロボロのマイホームで暮らさなくても良いって事)
鉄砲で撃たれても弾が貫通して来ない事(西部劇の見すぎ?)
環境にも住む人にとっても優しい建物という事で、ログハウスに住んでログハウスを作るという仕事をしています。
もちろん昔ながらの木をふんだんに使った在来工法もやっています。
だから暖房も化石燃料をやめて薪ストーブを燃やして賄っている訳です。
Posted by ウエストガーデン at 21:25│Comments(0)
│木を学ぶ