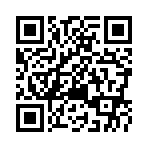2009年02月26日
ダブテイルは要注意
ダブテイルというノッチについて触れたらコメントを頂きました。
そこでふと思い出したのがダブテイルノッチの弱点です。
それは・・・
オーバースクライブ出来ない
事です。

このダブテイルノッチ、セトリングしたらどうなるのか?
Aの部分が1セトリングすれば、断面積がAの約2倍あるBは2セトリングしますね。
(セトリングとは木材の乾燥収縮により木が痩せる=サイズが小さくなる事です)
つまりBはAの二倍セトリングが起きるわけですね。
すると最初は上面と下面が接しているCですが、BとAのセトリング差によってセトリングが進行していけばCに隙間が空いてしまうことになります。
各段の密着は進みますがノッチ部分には隙間が出来てしまいますね。

ハンドカットのダブテイルは最初から段と段の間が空いています。
Aがセトリングし初めても、段の間が狭くなりBのセトリングはノッチに影響しません。
ましてやAのセトリングが終わる頃には段と段の間がくっ付いてしまいそうな隙間が用意されています。
このログ断面とノッチ断面の違いで生ずるセトリング量のズレを吸収させる為に
オーバースクライブ
と言ってズレそうな分だけ予め隙間を設けるスクライブ(墨付=寸法出し)をするのです。
ダブテイルの場合はノッチ部分でオーバースクライブ出来ないのでログとログの間にその代を取っています。
ハンドカットログの場合、ノッチを刻む際にオーバースクライブラインでノッチを刻む事は基本です。
オーバースクライブしておかないと、セトリング進行でログとログの間に隙間が生じやすくなります。
マシンカットのノッチでもオーバースクライブされています。
マシンカットの場合、そもそも材が人工乾燥されているのでセトリングが起きる量がごく僅かです。
それでも数パーセントは縮みます、材の乾燥度のバラツキが少ないのでセトリング量も予想出来、その分はノッチの重なり部分を空かす事でオーバースクライブされています。
これでお分かりになると思います。
ダブテイルノッチのマシンカット画像、ネットから拾ったものなのですが・・・
つまりああいう風に最初にピッタリになるように作ってしまうと・・・
セトリング終了時に問題が起こる訳です。
セトリングを見越し、セトリングが終わったときにピッタリになるように作れると良いのですが、こればっかりは経験値の世界なのでとても難しいですね。
ハンドカットもマシンカットも、ログは木の乾燥収縮たるセトリング対策が上手く出来ないと良い建物は作れません。
ログハウスを見たけど壁から隙間風が・・・(←オーバースクライブしてないか量が足りなかった)
とにかくセトリング対策は難しいのです、ただ積めばいいってもんじゃないです。
そこでふと思い出したのがダブテイルノッチの弱点です。
それは・・・
オーバースクライブ出来ない
事です。

このダブテイルノッチ、セトリングしたらどうなるのか?
Aの部分が1セトリングすれば、断面積がAの約2倍あるBは2セトリングしますね。
(セトリングとは木材の乾燥収縮により木が痩せる=サイズが小さくなる事です)
つまりBはAの二倍セトリングが起きるわけですね。
すると最初は上面と下面が接しているCですが、BとAのセトリング差によってセトリングが進行していけばCに隙間が空いてしまうことになります。
各段の密着は進みますがノッチ部分には隙間が出来てしまいますね。

ハンドカットのダブテイルは最初から段と段の間が空いています。
Aがセトリングし初めても、段の間が狭くなりBのセトリングはノッチに影響しません。
ましてやAのセトリングが終わる頃には段と段の間がくっ付いてしまいそうな隙間が用意されています。
このログ断面とノッチ断面の違いで生ずるセトリング量のズレを吸収させる為に
オーバースクライブ
と言ってズレそうな分だけ予め隙間を設けるスクライブ(墨付=寸法出し)をするのです。
ダブテイルの場合はノッチ部分でオーバースクライブ出来ないのでログとログの間にその代を取っています。
ハンドカットログの場合、ノッチを刻む際にオーバースクライブラインでノッチを刻む事は基本です。
オーバースクライブしておかないと、セトリング進行でログとログの間に隙間が生じやすくなります。
マシンカットのノッチでもオーバースクライブされています。
マシンカットの場合、そもそも材が人工乾燥されているのでセトリングが起きる量がごく僅かです。
それでも数パーセントは縮みます、材の乾燥度のバラツキが少ないのでセトリング量も予想出来、その分はノッチの重なり部分を空かす事でオーバースクライブされています。
これでお分かりになると思います。
ダブテイルノッチのマシンカット画像、ネットから拾ったものなのですが・・・
つまりああいう風に最初にピッタリになるように作ってしまうと・・・
セトリング終了時に問題が起こる訳です。
セトリングを見越し、セトリングが終わったときにピッタリになるように作れると良いのですが、こればっかりは経験値の世界なのでとても難しいですね。
ハンドカットもマシンカットも、ログは木の乾燥収縮たるセトリング対策が上手く出来ないと良い建物は作れません。
ログハウスを見たけど壁から隙間風が・・・(←オーバースクライブしてないか量が足りなかった)
とにかくセトリング対策は難しいのです、ただ積めばいいってもんじゃないです。
Posted by ウエストガーデン at 02:08│Comments(7)
│ログライフ
この記事へのコメント
はじめまして!
ダブテイルを建てようとしているものです。
ダブテイルに関してかなり調べまくっているので写真を見た瞬間にピンときたのですが、この写真は田上材木店さんのログですね。
田上材木店さんは、「乾燥した檜」を使っているのですが、ウエストガーデンさんは、セトリングの理由を木材の乾燥による、と記述しておられます。だとすると、ピッタリでも問題ないように思います。
自分は生木を加工しているのですが、乾燥による収縮は心材に比べて辺材でより大きく発生しています。
太鼓ログなのですが、平面だった部分が収縮により湾曲しているのが証拠でしょうし、ログに発生するひび割れも、辺材がより大きく収縮することが原因といわれています。
だとすれば、オーバースクライブするといっても、直線ではダメで、心材部分はあまり収縮せず、辺材は大きく収縮するのだから、ノッチ部分はお椀のように心材部分がより大きく削られた形にしないと都合が悪いことになりませんでしょうか?
ただ、自分のような素人にそのような器用なことはできませんので、
今は仮組しておいて、ノッチ部分がきつくなったら、そこをサンダーで削ってかみ合わせる、削り過ぎたらチンキングで塞ぐ、という対処で凌ごうかと思っています。
スマートな方法があれば教えてください。
ダブテイルを建てようとしているものです。
ダブテイルに関してかなり調べまくっているので写真を見た瞬間にピンときたのですが、この写真は田上材木店さんのログですね。
田上材木店さんは、「乾燥した檜」を使っているのですが、ウエストガーデンさんは、セトリングの理由を木材の乾燥による、と記述しておられます。だとすると、ピッタリでも問題ないように思います。
自分は生木を加工しているのですが、乾燥による収縮は心材に比べて辺材でより大きく発生しています。
太鼓ログなのですが、平面だった部分が収縮により湾曲しているのが証拠でしょうし、ログに発生するひび割れも、辺材がより大きく収縮することが原因といわれています。
だとすれば、オーバースクライブするといっても、直線ではダメで、心材部分はあまり収縮せず、辺材は大きく収縮するのだから、ノッチ部分はお椀のように心材部分がより大きく削られた形にしないと都合が悪いことになりませんでしょうか?
ただ、自分のような素人にそのような器用なことはできませんので、
今は仮組しておいて、ノッチ部分がきつくなったら、そこをサンダーで削ってかみ合わせる、削り過ぎたらチンキングで塞ぐ、という対処で凌ごうかと思っています。
スマートな方法があれば教えてください。
Posted by shige02 at 2009年05月03日 21:51
shige02さん
まず画像はネットから拾いました。
ダブテイルをお建てになるそうですが、建築確認申請はクリアしていますか?
ダブテイルでの確認取り付けは「かなりの難題です」
>ピッタリでも問題ないように思います。
皆そう思うんですよね、そして実際にやって失敗しているんですよね。
「乾燥した檜」って「どれくらい乾燥した檜」なんでしょうかね?
マシンカットラミネートログでもセトリングはクリアできていません。
それと、セトリングは材の乾燥のみでなく、屋根荷重による事は言うまでもありません。
>自分は生木を加工しているのですが
ある程度は含水率を下げた材でないと難しいでしょうね。
画像の二枚目はカナダのものですが、一般にダブテイルノッチは角材にして用いるものです。
タイコ挽きや丸いログでダブテイルノッチは刻みません。
それは、辺材が暴れて納めにくいからです。
>スマートな方法があれば教えてください。
ダブテイルは二枚目の画像の様にログとログの間を広く開けておき、ノッチ部分だけを重ねます。
そして間は
最初からバックアップ材とチンキング
で仕上げる作り方です。
ログとログの間をログだけでキッチリ納めることは無理なんです。
だからダブテイルは広がらないんです。
自己満足で作るのと、業として作ることは一緒に出来ません。
まず画像はネットから拾いました。
ダブテイルをお建てになるそうですが、建築確認申請はクリアしていますか?
ダブテイルでの確認取り付けは「かなりの難題です」
>ピッタリでも問題ないように思います。
皆そう思うんですよね、そして実際にやって失敗しているんですよね。
「乾燥した檜」って「どれくらい乾燥した檜」なんでしょうかね?
マシンカットラミネートログでもセトリングはクリアできていません。
それと、セトリングは材の乾燥のみでなく、屋根荷重による事は言うまでもありません。
>自分は生木を加工しているのですが
ある程度は含水率を下げた材でないと難しいでしょうね。
画像の二枚目はカナダのものですが、一般にダブテイルノッチは角材にして用いるものです。
タイコ挽きや丸いログでダブテイルノッチは刻みません。
それは、辺材が暴れて納めにくいからです。
>スマートな方法があれば教えてください。
ダブテイルは二枚目の画像の様にログとログの間を広く開けておき、ノッチ部分だけを重ねます。
そして間は
最初からバックアップ材とチンキング
で仕上げる作り方です。
ログとログの間をログだけでキッチリ納めることは無理なんです。
だからダブテイルは広がらないんです。
自己満足で作るのと、業として作ることは一緒に出来ません。
Posted by WSG at 2009年05月08日 22:54
解説ありがとうございます。
作っているのは小さなものですので確認は不要と思っています。
10平米以下です。
確かに、角材にしているものは多いですし、ログを重ねているものは少ないようです。
太鼓ログの場合も、丸い面は上下にきていて、間を詰め物で塞いでいるものが多いようですが、そういう理由があるんですね。
見た目、ストライプになって、個性的かなと思います。
ダブテイルっていうのは、あまり見ないので、珍しいので作ってみました。
たしかに商売でやるとなると、要求されるハードルは相当高そうですね。
近所で柱の木目が気に入らない、という理由で建築代金を支払わない人がいましたが、そういう人だと、木がひび割れただけで大クレームでしょうね。
作っているのは小さなものですので確認は不要と思っています。
10平米以下です。
確かに、角材にしているものは多いですし、ログを重ねているものは少ないようです。
太鼓ログの場合も、丸い面は上下にきていて、間を詰め物で塞いでいるものが多いようですが、そういう理由があるんですね。
見た目、ストライプになって、個性的かなと思います。
ダブテイルっていうのは、あまり見ないので、珍しいので作ってみました。
たしかに商売でやるとなると、要求されるハードルは相当高そうですね。
近所で柱の木目が気に入らない、という理由で建築代金を支払わない人がいましたが、そういう人だと、木がひび割れただけで大クレームでしょうね。
Posted by shige02 at 2009年05月16日 20:50
タブテイルのセトリングについてですが。少しおかしくないですか?
1本の丸太について言えばAとBのセトリングは正しいですが、階高全体で考えるとノッチ部もログ壁部も階高は同じです。理論的にはセトリング量も同じはずです。なぜなら、ノッチ部はX方向とY方向の丸太でセトリングするからです。
1本の丸太について言えばAとBのセトリングは正しいですが、階高全体で考えるとノッチ部もログ壁部も階高は同じです。理論的にはセトリング量も同じはずです。なぜなら、ノッチ部はX方向とY方向の丸太でセトリングするからです。
Posted by yuuki at 2010年04月19日 21:20
Yuukiさん
>理論的にはセトリング量も同じはずです。
理論的にも違います、さらにログは縮む素材なので理論は通用しません。
X方向Y方向じゃないんですよ、実際には南北でセトリング量も異なります。
理屈だけならオーバースクライブは必要ないのです。
どれだけオーバースクライブしておくかは経験と勘の世界ですね。
>理論的にはセトリング量も同じはずです。
理論的にも違います、さらにログは縮む素材なので理論は通用しません。
X方向Y方向じゃないんですよ、実際には南北でセトリング量も異なります。
理屈だけならオーバースクライブは必要ないのです。
どれだけオーバースクライブしておくかは経験と勘の世界ですね。
Posted by WSG at 2010年04月23日 20:29
始めまして。ログハウス業界のプロです。
ダブテイルログについての記述がありますが、訂正をお願いしたい部分があります。
まず、ダブテイルのセトリングについてABCでの説明がありますが、これは勘違いされている部分があります。
マシンログでの説明ではC(ノッチの間上下)に隙間ができるとありますが、
ノッチには隙間はできません。隙間ができる可能性があるのはノッチ以外のログとログの間(グルーブの部分、カナダの写真でのD)です。
材木の収縮というのは乾燥した木、生木にかかわらず、辺材(いわゆる白太周辺)の収縮率が多いのでBの収縮がAの2倍とは単純にはなりません。
また、AとBを比べるのも少し違うように思います。
収縮率(シュリンク量)をくらべるとすれば、まずBからAを引かなければなりません。(ログ一本分の幅Bの中にAがあるのだから当然ですよね)
これをEとします。そしてEとAの収縮率を比べることで、シュリンク量の差(隙間の発生する場所)を調べる意味があると思われます。
※セトリングでの隙間の検討をするのであれば、ココが一番重要なところです。
このAとEの収縮率の差はA(心材)よりもEの方(辺材)が当然シュリンク量が多くなります。
このAとEの高さ寸法は、マシンカットの例ですと、ほぼ等しいです。(カナダの例に使われている写真のログもほぼ同じです)
上記を前提とし、同じ高さ寸法で収縮率が大きい方がより縮むという事は・・・
ログを積んだ場合、隙間が開いてくるのはどちらかというのは言うまでもありませんね。
なので、ダブテイルログのノッチ部分には隙間は出来るどころか、荷重がかかることによって、さらにタイトになります。
そしてグルーブがピッタリと収まったマシンのダブテイルログに関しては隙間が出来るとすれば、グルーブ側に出来ることになります。
ただ、これに関しても、グルーブ(実)のスライド幅を深くとったりすることで、雨風が吹き込むような問題が起こるようなことにならないようにすることは可能だと思います。
また、ハンドクラフトでのダブテイルの場合は、殆どの場合がチンキングをするスタイルなので、同じくこちらも隙間の問題は技術的にも全く問題ありません。
フィンランド等のマシンカットログのノッチ部分(スクエアノッチ)の上下にクリアランスがとってあるのは心材よりも辺材のほうがより収縮するのも一つの理由ですよね。ここにクリアランスの無いログはどうなると思われますか?
ちなみに、オーバースクライブの考えを利用してグルーブをピッタリ収めたハンドクラフトのダブテイルログも豊富な経験があれば十分可能だそうです。
これは、本場カナダで10年以上ダブテイルログを刻み続けているプロのログビルダーに教わった話しですので間違いありません。
私の個人的意見ですが、
ダブテイルログも木の特性、技術、知識を駆使すれば、”十分に業として” ”住まいとして”通じると思っています。
(日本の建築基準法に適合云々は別の話しとして)
ただ、個人的には、あまりにも完璧な納まりのダブテイルログよりも、隙間を藁で詰めているような感じのラフなダブテイルの方が素敵だと思っていますが・・・
あと、カナダでのダブテイルログ事情ですが、
一般には角材ではありませんよ。内外壁の面をフラットにしたタイコ挽きがノーマルです。
また、丸ログでのダブテイルもカナダの道を走っていればちょくちょく見られますよ。想像でお話しされているのでは?
長文、お許しください。
普段、このようなコメントをすることは無いのですが、
ダブテイルログの勉強をしている者、ログ業界のプロとしては黙っていることが出来ませんでした。
私は目立ちたがりではありませんので、今回は名前を伏せさせていただいてますが、
必要であれば、自分の立場を明かす覚悟を充分持ってコメントを投稿させてもらってます。
この記事についての何らかの加筆をいただけることを希望いたします。
ダブテイルログについての記述がありますが、訂正をお願いしたい部分があります。
まず、ダブテイルのセトリングについてABCでの説明がありますが、これは勘違いされている部分があります。
マシンログでの説明ではC(ノッチの間上下)に隙間ができるとありますが、
ノッチには隙間はできません。隙間ができる可能性があるのはノッチ以外のログとログの間(グルーブの部分、カナダの写真でのD)です。
材木の収縮というのは乾燥した木、生木にかかわらず、辺材(いわゆる白太周辺)の収縮率が多いのでBの収縮がAの2倍とは単純にはなりません。
また、AとBを比べるのも少し違うように思います。
収縮率(シュリンク量)をくらべるとすれば、まずBからAを引かなければなりません。(ログ一本分の幅Bの中にAがあるのだから当然ですよね)
これをEとします。そしてEとAの収縮率を比べることで、シュリンク量の差(隙間の発生する場所)を調べる意味があると思われます。
※セトリングでの隙間の検討をするのであれば、ココが一番重要なところです。
このAとEの収縮率の差はA(心材)よりもEの方(辺材)が当然シュリンク量が多くなります。
このAとEの高さ寸法は、マシンカットの例ですと、ほぼ等しいです。(カナダの例に使われている写真のログもほぼ同じです)
上記を前提とし、同じ高さ寸法で収縮率が大きい方がより縮むという事は・・・
ログを積んだ場合、隙間が開いてくるのはどちらかというのは言うまでもありませんね。
なので、ダブテイルログのノッチ部分には隙間は出来るどころか、荷重がかかることによって、さらにタイトになります。
そしてグルーブがピッタリと収まったマシンのダブテイルログに関しては隙間が出来るとすれば、グルーブ側に出来ることになります。
ただ、これに関しても、グルーブ(実)のスライド幅を深くとったりすることで、雨風が吹き込むような問題が起こるようなことにならないようにすることは可能だと思います。
また、ハンドクラフトでのダブテイルの場合は、殆どの場合がチンキングをするスタイルなので、同じくこちらも隙間の問題は技術的にも全く問題ありません。
フィンランド等のマシンカットログのノッチ部分(スクエアノッチ)の上下にクリアランスがとってあるのは心材よりも辺材のほうがより収縮するのも一つの理由ですよね。ここにクリアランスの無いログはどうなると思われますか?
ちなみに、オーバースクライブの考えを利用してグルーブをピッタリ収めたハンドクラフトのダブテイルログも豊富な経験があれば十分可能だそうです。
これは、本場カナダで10年以上ダブテイルログを刻み続けているプロのログビルダーに教わった話しですので間違いありません。
私の個人的意見ですが、
ダブテイルログも木の特性、技術、知識を駆使すれば、”十分に業として” ”住まいとして”通じると思っています。
(日本の建築基準法に適合云々は別の話しとして)
ただ、個人的には、あまりにも完璧な納まりのダブテイルログよりも、隙間を藁で詰めているような感じのラフなダブテイルの方が素敵だと思っていますが・・・
あと、カナダでのダブテイルログ事情ですが、
一般には角材ではありませんよ。内外壁の面をフラットにしたタイコ挽きがノーマルです。
また、丸ログでのダブテイルもカナダの道を走っていればちょくちょく見られますよ。想像でお話しされているのでは?
長文、お許しください。
普段、このようなコメントをすることは無いのですが、
ダブテイルログの勉強をしている者、ログ業界のプロとしては黙っていることが出来ませんでした。
私は目立ちたがりではありませんので、今回は名前を伏せさせていただいてますが、
必要であれば、自分の立場を明かす覚悟を充分持ってコメントを投稿させてもらってます。
この記事についての何らかの加筆をいただけることを希望いたします。
Posted by 山 at 2010年07月05日 10:42
山さん
コメントありがとうございます。
この記事をUPした背景に、ビギナーの方が手探りでログを作ろうとし、杉の角材でダブテイルを作っていた背景があります。
その方は確か治具を作って簡単にノッチを刻まれ「簡単に出来る」みたいな事を言っていたような・・・それに対してダブテイルではノッチでオーバースクライブしてセトリング量の調整が出来ない=「将来グループに隙間ができる」
という事を少しややこしく書いたものです。
これは素人さんが陥りやすいノッチ部Aと本体Bのセトリング量の違いでいろいろと問題が起きるという点を説明したかったのです。
理屈っぽく説明しているので単純に2倍などとしていますが、実際には貴殿のご指摘の通り芯部と辺部ではシュリンクは異なり、その見極めは経験がものを言うアナログな世界ですね。
ログをセルフビルドする方には理屈っぽい方が多く(オマエも十分理屈っぽいと言われるかもしれませんが・・)、芯と辺の違いとか説明しても受け入れてくれない訳です。
「理論的にはセトリング量は一緒」とコメントがされているように、素人さんはそう考えがちです。
この記事の「オーバースクライブできない」問題の結論としての答えは書いていないのですが、
グリン材の角材でピッタリのダブテイルを作ると
将来グループ間に隙間が生じる可能性が高い
グループに隙間が出来ないとすればノッチに隙間が出来る
という事を伏せて説明したつもりだったのですが、背景を知らずに読まれるとこのようなご指摘を頂く事になってしまいますね。
記事を書いていて私も頭の中が混乱する事がたたあり、改めてこの記事を読み直すと言葉足らずな部分もかなりあると感じました、ただそういう書き方をしたのは意図的にそうしたはず(その理由はよく覚えていません)
個人的にはダブテイルは嫌いではありません
ただ素人さんに「簡単」と言われるほど簡単なものではないという事を記したくて書いたような気がしています。
セルフビルドで流通角材でログを作ろうとすれば、スクウェアノッチでヤトイ実あたりが一番簡単なのではないかと思っています。
そのひとつの答えが古のばってんノッチなのかもしれません。
今でも素人工事でピーセンピースを作ろうとしている現場があります。
筋交いいれてパスさせているようです。
ログハウスも構造は単純ですが、奥は深いし質を問われるとその幅の大きさと言えば・・・・
それらをサラリと「ログなんて壁から隙間風入るからダメだよねぇー」なんて言われるととても辛いですね。
こちら方面では「酷い工事」が少なくありません。
コメントありがとうございます。
この記事をUPした背景に、ビギナーの方が手探りでログを作ろうとし、杉の角材でダブテイルを作っていた背景があります。
その方は確か治具を作って簡単にノッチを刻まれ「簡単に出来る」みたいな事を言っていたような・・・それに対してダブテイルではノッチでオーバースクライブしてセトリング量の調整が出来ない=「将来グループに隙間ができる」
という事を少しややこしく書いたものです。
これは素人さんが陥りやすいノッチ部Aと本体Bのセトリング量の違いでいろいろと問題が起きるという点を説明したかったのです。
理屈っぽく説明しているので単純に2倍などとしていますが、実際には貴殿のご指摘の通り芯部と辺部ではシュリンクは異なり、その見極めは経験がものを言うアナログな世界ですね。
ログをセルフビルドする方には理屈っぽい方が多く(オマエも十分理屈っぽいと言われるかもしれませんが・・)、芯と辺の違いとか説明しても受け入れてくれない訳です。
「理論的にはセトリング量は一緒」とコメントがされているように、素人さんはそう考えがちです。
この記事の「オーバースクライブできない」問題の結論としての答えは書いていないのですが、
グリン材の角材でピッタリのダブテイルを作ると
将来グループ間に隙間が生じる可能性が高い
グループに隙間が出来ないとすればノッチに隙間が出来る
という事を伏せて説明したつもりだったのですが、背景を知らずに読まれるとこのようなご指摘を頂く事になってしまいますね。
記事を書いていて私も頭の中が混乱する事がたたあり、改めてこの記事を読み直すと言葉足らずな部分もかなりあると感じました、ただそういう書き方をしたのは意図的にそうしたはず(その理由はよく覚えていません)
個人的にはダブテイルは嫌いではありません
ただ素人さんに「簡単」と言われるほど簡単なものではないという事を記したくて書いたような気がしています。
セルフビルドで流通角材でログを作ろうとすれば、スクウェアノッチでヤトイ実あたりが一番簡単なのではないかと思っています。
そのひとつの答えが古のばってんノッチなのかもしれません。
今でも素人工事でピーセンピースを作ろうとしている現場があります。
筋交いいれてパスさせているようです。
ログハウスも構造は単純ですが、奥は深いし質を問われるとその幅の大きさと言えば・・・・
それらをサラリと「ログなんて壁から隙間風入るからダメだよねぇー」なんて言われるととても辛いですね。
こちら方面では「酷い工事」が少なくありません。
Posted by WSG at 2010年07月07日 10:21