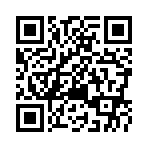2009年02月21日
木研第132回
大分県木造建築研究会
略して木研と呼ばれる組織に参加しております。
大分大学工学部の井上教授が事務局長を務めるこの研究会、在来工法や木造の構造物などについていろいろと勉強したり、情報交換する設計士さんなどが中心の会です。
私は「建築士資格を持ってない」し、そもそも大学の工学部などにも縁の無い人間です。
しかし木造建築の中の木造建築たるログハウス(丸太組工法)のプロを自負していることは確かです。
木についての勉強は尽きることが無いと思っています。
この会に参加して判った事、それは・・・
「大学の建築学部では木造建築の事は勉強しない」
という事です。S造(鉄骨)やRC造(鉄筋コンクリート)については散々勉強するらしいのですが、木造については基本的なカリキュラムではほとんど出てこないそうです(本当なんでしょうか?)
確かにログハウスの建築法規たる「丸太組工法」について熟知している建築士って日本中でも100人居るか居ないか位だと思います。(法規改正もあったので旧法とも違う)
最も建築士さんにとっては多少勉強すれば法規はマスターできる事なのでしょうけど。
でもログハウスでは経験値なくして語れない分野です。
新参者の無理な設計で「悪夢のログハウスに暮らす」事態に陥っているオーナーさん、結構多いんですよね・・
そういう意味では私なんざめずらしい存在なのかもしれません。
というのも設計士は現場で釘を叩いたり、実際に施工に携わることってほとんどありません、私は設計もするし現場にも入るし(忙しくなったら入れない)、入るの好きですし、そして営業してオーナーとなるお客さんといろんな提案したりと「なんでもやってしまう」んですよね。
今回で132回目の例会
テーマは「木材・木質資源の利用技術に関する講習会」
建築のみならず、木製ガードレールとか木橋とか、木を使った構造物など木を有効利用する為の技術についてや、そもそもどうして木を沢山使ってゆく必要があるのか?などについてお勉強です。
講師は研究者の方が多いので「何でもとりあえず疑問符」です。
今私達が地球温暖化だと騒ぎ、その元凶はco2である。
研究者からすればそこから疑問符が付くのですが、それは前提が崩れるのでそこは置いといて・・・
京都議定書の言わんとする事はあーこーであり、そーこーだから今は木材を積極的に使っていきましょうという結論になる訳です。
で「木」という天然資源の特性についてもおさらいし、問題点なども。
まぁ木は腐りますからね、間違った使い方をすればとんでもない事にもなる訳です。
ログハウスという建物は構造のほとんど全てを木で作ります、ゆえに木の特性や強度などを十分に理解していないと危険な建物を作ってしまう事に繋がるのですが、基本的な事柄から専門的な事柄まで勉強できるのがこの研究会の面白いところです。
実際の施工例と失敗例を見ていると「オイオイ、そりゃマズイっしょ?」ってつっこみたくなるような事を平気でやっている訳ですからね。
昨年夏「腐り始めているログハウスの修繕」の模様をupしていますが、私達にとっては当たり前のようなことでもまだまだ建築業界では一般認知されていないんだなぁと愕然。
ちなみに私は江戸末期築の生家で18まで過ごし、木造校舎の日土小学校で6年間です。
略して木研と呼ばれる組織に参加しております。
大分大学工学部の井上教授が事務局長を務めるこの研究会、在来工法や木造の構造物などについていろいろと勉強したり、情報交換する設計士さんなどが中心の会です。
私は「建築士資格を持ってない」し、そもそも大学の工学部などにも縁の無い人間です。
しかし木造建築の中の木造建築たるログハウス(丸太組工法)のプロを自負していることは確かです。
木についての勉強は尽きることが無いと思っています。
この会に参加して判った事、それは・・・
「大学の建築学部では木造建築の事は勉強しない」
という事です。S造(鉄骨)やRC造(鉄筋コンクリート)については散々勉強するらしいのですが、木造については基本的なカリキュラムではほとんど出てこないそうです(本当なんでしょうか?)
確かにログハウスの建築法規たる「丸太組工法」について熟知している建築士って日本中でも100人居るか居ないか位だと思います。(法規改正もあったので旧法とも違う)
最も建築士さんにとっては多少勉強すれば法規はマスターできる事なのでしょうけど。
でもログハウスでは経験値なくして語れない分野です。
新参者の無理な設計で「悪夢のログハウスに暮らす」事態に陥っているオーナーさん、結構多いんですよね・・
そういう意味では私なんざめずらしい存在なのかもしれません。
というのも設計士は現場で釘を叩いたり、実際に施工に携わることってほとんどありません、私は設計もするし現場にも入るし(忙しくなったら入れない)、入るの好きですし、そして営業してオーナーとなるお客さんといろんな提案したりと「なんでもやってしまう」んですよね。
今回で132回目の例会
テーマは「木材・木質資源の利用技術に関する講習会」
建築のみならず、木製ガードレールとか木橋とか、木を使った構造物など木を有効利用する為の技術についてや、そもそもどうして木を沢山使ってゆく必要があるのか?などについてお勉強です。
講師は研究者の方が多いので「何でもとりあえず疑問符」です。
今私達が地球温暖化だと騒ぎ、その元凶はco2である。
研究者からすればそこから疑問符が付くのですが、それは前提が崩れるのでそこは置いといて・・・
京都議定書の言わんとする事はあーこーであり、そーこーだから今は木材を積極的に使っていきましょうという結論になる訳です。
で「木」という天然資源の特性についてもおさらいし、問題点なども。
まぁ木は腐りますからね、間違った使い方をすればとんでもない事にもなる訳です。
ログハウスという建物は構造のほとんど全てを木で作ります、ゆえに木の特性や強度などを十分に理解していないと危険な建物を作ってしまう事に繋がるのですが、基本的な事柄から専門的な事柄まで勉強できるのがこの研究会の面白いところです。
実際の施工例と失敗例を見ていると「オイオイ、そりゃマズイっしょ?」ってつっこみたくなるような事を平気でやっている訳ですからね。
昨年夏「腐り始めているログハウスの修繕」の模様をupしていますが、私達にとっては当たり前のようなことでもまだまだ建築業界では一般認知されていないんだなぁと愕然。
ちなみに私は江戸末期築の生家で18まで過ごし、木造校舎の日土小学校で6年間です。